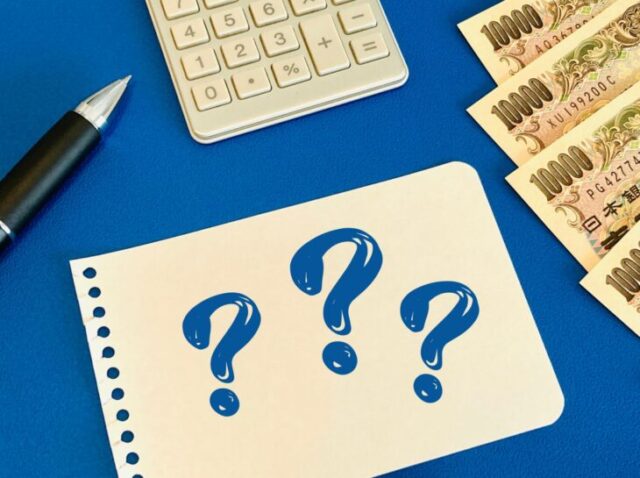交通事故で軽傷だった場合の示談金の相場は?慰謝料の算定方法や弁護士に相談すべきケースについて解説

執筆者 花吉 直幸 弁護士
所属 第二東京弁護士会
依頼者の方の問題をより望ましい状況に進むようにサポートできれば、それを拡充できればというやりがいで弁護士として仕事をしています。

この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「交通事故で軽傷だったときの示談金はどのくらいなのか」
「交通事故で軽傷の場合にどんな賠償金を請求できるのか」
交通事故によって軽傷ではあるものの怪我を負った方の中には、示談金についてこのような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。
交通事故によって生じた損害についての賠償問題は、当事者間で話し合いによって解決を図ることが一般的です。
このような解決を示談と呼び、示談が成立した場合に加害者側から被害者に対して支払われる賠償金を示談金といいます。
示談金にはさまざまな項目が含まれ、交通事故によって生じた怪我が軽傷の場合であっても、怪我の治療費や傷害(入通院)慰謝料などの項目について賠償を受けることが可能です。
示談金の中でも高額化しやすいのが傷害(入通院)慰謝料であり、治療期間によって受け取ることができる金額が変動します。
例えば、治療期間が1週間程度の場合には約1~5万円ですが、1か月程度まで長引いた場合には約3~19万円程度が相場となります。
もっとも、慰謝料の具体的な金額は、治療の頻度や算定基準によって異なるため、注意が必要です。
本記事では、交通事故による怪我が軽傷の場合に受け取ることができる傷害(入通院)慰謝料の相場やほかの示談金の項目などについて解説します。
- 交通事故による怪我が軽傷の場合であっても、怪我の治療費や傷害(入通院)慰謝料などの損害について賠償を受けることができる
- 軽傷の場合の傷害(入通院)慰謝料の金額は治療期間や頻度によって変動し、数万円から数十万円が相場となる
- 怪我の程度が軽い場合にも、必ず医療機関を受診し、適切な期間と頻度で治療を行うことが適正な賠償金を獲得するためにも大切
1.治療期間別|軽傷の場合の慰謝料の相場

交通事故によって怪我を負った場合には、医療機関を受診して治療を行うことで、傷害(入通院)慰謝料を受け取ることができます。
傷害(入通院)慰謝料は、交通事故によって怪我を負った精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
交通事故による怪我が軽傷の場合であっても、傷害(入通院)慰謝料を請求し、受け取ることが可能です。
傷害(入通院)慰謝料は、治療期間によって具体的な金額が変動し、採用する算定基準によっても異なります。
算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあり、最も高い金額が算出されやすいのが裁判所基準です。
一方、最も低い金額が算出されやすいのが自賠責基準です。
以下では、治療期間別に軽症の場合の傷害(入通院)慰謝料の相場について解説します。
(1)治療期間が1週間程度の場合
治療期間が1週間程度で終了し、完治した場合には、以下のような水準となることが多いです。
| 算定基準 | 傷害(入通院)慰謝料の相場 |
| 自賠責基準 | 約1~3万円 |
| 裁判所基準 | 4~5万円 |
自賠責基準は、賠償金のベースとなる基準で、以下の算定式に基づいて算出されます。
- 4,300円×対象日数
対象日数は、「治療期間」または「実通院日数×2」のうち、いずれか少ない方の日数です。
例えば1週間のうち2日に1回以上の頻度で通院していた場合には、「実通院日数×2」よりも「治療期間(=7日)」の方が日数が少なくなるため、
- 4,300円×7日=30,100円
となり、1回だけ通院した場合には、「治療期間」より「実通院日数×2」の方が日数が少なくなるため、
- 4,300円×2日=8,600円
となります。
これに対して、裁判所基準では、基本的には、実通院日数が何日であっても、治療期間に基づいて算定されます。
裁判所基準は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤本)という書籍に記載されている過去の裁判例に基づいて作成された算定表を用いて算出します。
この算定表に従って算定すると、4~5万円となります。
このように、自賠責基準と裁判所基準では、算出される金額に違いが見られることに注意しましょう。
なお、任意保険基準は加害者側の保険会社が用いる基準であり、詳細は非公開となっているものの、概ね自賠責基準と同程度か少し高い程度の金額となることがほとんどです。
そのため、1週間程度の治療で完治した場合、多くても5万円程度が慰謝料の相場となるといえるでしょう。
(2)治療期間が1か月程度の場合
1か月程度にわたって治療を行い、完治した場合には、傷害(入通院)慰謝料の相場は以下のとおりです。
| 算定基準 | 傷害(入通院)慰謝料の相場 |
| 自賠責基準 | 約2~13万円 |
| 裁判所基準 | 19万円程度 |
怪我の程度によるものの、打撲や軽い捻挫の場合には、治療期間が1か月程度となることが多いです。
自賠責基準の算出方法は、先ほど述べた算定式を用いるため、具体的な金額は通院期間あるいは実通院日数によって変動するため、上記の表のように金額に幅があります。
裁判所基準では、1か月であれば19万円程度になるのが一般的です。
(3)治療期間が3か月程度の場合
3か月程度の治療期間を経て完治した場合には、以下の金額が相場となります。
| 算定基準 | 傷害(入通院)慰謝料の相場 |
| 自賠責基準 | 約10~30万円 |
| 裁判所基準 | 53万円程度 |
先ほど述べたように、自賠責基準の算出方法は同じで、一般的には10~30万円程度になる傾向があります。
また、裁判所基準では、3か月であれば53万円程度になるのが一般的です。
具体的な算定方法やポイントについては、以下の記事も参考になります。
なお、交通事故の怪我の中でも比較的生じやすいむちうちの場合は、治療期間が3か月程度となることが多いです。
ただし、症状の程度によっては、3か月でも完治せず、さらに治療を要することもある点にも注意しましょう。
むちうちの治療と傷害(入通院)慰謝料の相場については、以下の記事も参考になります。
2.慰謝料以外に受け取ることができる示談金の項目

上記のように、交通事故による怪我が軽傷の場合には、治療期間や算定基準によって、傷害(入通院)慰謝料の金額が変動します。
なお、傷害(入通院)慰謝料のほかにも、損害状況によって、様々な損害項目を示談金として請求し、受け取ることが可能です。
代表的なものとしては、以下のようなものがあります。
- 治療費
- 通院交通費
- 休業損害
- 物的損害
順にご説明します。
(1)治療費
怪我の治療に要した費用は、交通事故と怪我の因果関係が認められる範囲で実費の補償を受けることができます。
なお、加害者側が任意保険に加入している場合には、その保険会社が治療費を支払う「一括対応」が行われることが一般的です。
そのため、被害者は自己負担なく治療を行うことができ、金銭面で心配する必要はありません。
もっとも、一括対応はあくまで保険会社のサービスであるため、保険会社から支払を拒否されたり打ち切られたりしても、支払を強制することができない点に注意が必要です。
特に被害者側の過失が高い場合や治療の頻度が低い場合には、支払の拒否や打ち切りとなる可能性が高まります。
しかし、加害者側から打ち切りを打診されても、医師が治療を継続することが必要であると判断している場合には、しっかりと怪我の治療を続けることが重要です。
また、支払を拒否されたり打ち切られたりしても、健康保険などを利用して治療費を立て替えることで、後の示談交渉で補償を受けることができる可能性があります。
交通事故の怪我の治療で健康保険を利用する際の注意点については、以下の記事も参考になります。
(2)通院交通費
怪我の治療のために通院する際にかかった交通費についても、示談金として受け取ることができます。
ただし、補償を受けることができるのは、交通事故と怪我の間に因果関係があり、怪我の治療のために必要な範囲の支出であると認められたものです。
そのため、必要以上の支出と判断された場合には、請求できない可能性があります。
例えば、バスや電車などの公共交通機関を利用することで通院できるにもかかわらず、タクシーで通院した場合は、必要な支出とは認められない可能性が高いです。
その場合は、タクシー代ではなく、公共交通機関を利用した場合の代金が支払われることとなります。
このように、通院交通費として認められるためには、客観的に見てその支出が必要であったことを立証する必要があります。
なお、負担した金額を証明するために、領収書などを残しておく必要があることにも注意しましょう。
交通事故の通院交通費を請求するためのポイントについては、以下の記事も参考になります。
(3)休業損害
休業損害は、交通事故の怪我によって仕事を休まなければならなくなったことで収入が減少した場合に請求することができるものです。
休業損害は、会社員や自営業者だけでなく、家事従事者や学生なども受け取ることが可能です。
1日あたりの基礎収入に休業日数をかけて算出するため、休んだ日数に応じて請求できる金額が変動します。
また、休業損害にも複数の算定基準があり、どの算定基準に基づいて算出するかによっても金額が変動するため、適切な算定基準を用いて計算を行う必要があることも押さえておきましょう。
休業損害を受け取るための条件などについては、以下の記事も参考になります。
また、休業損害の算定基準と計算方法については、以下の記事もご参照ください。
(4)物的損害
交通事故によって、車両などに損壊が発生している場合には、その損害について賠償を受けることができます。
物的損害に含まれるのは、以下のような項目です。
- 車の修理費(分損の場合)または車両時価額と買替諸費用(全損の場合)
- 評価損
- 休車損害
- 代車料 など
物的損害は、分損の場合と全損の場合で請求できる費用が異なるため、まずは分損か全損かの確認をしましょう。
物的損害は、実際の損害額に基づいて賠償を受けることができます。
もっとも、具体的な金額は事故の状況や損害の内容によって異なり、また、すべてについて賠償を受けることができるとは限らないことに注意しましょう。
なお、車両の損壊などの物的損害だけでなく、怪我などの人的損害も生じている場合には、先に物的損害についてのみ示談交渉を行うことが一般的です。
物的損害の詳細や示談交渉を進める際の注意点については、以下の記事で解説しています。
3.交通事故による怪我が軽傷の場合にもすべきこと

交通事故に遭った場合には、その怪我が軽傷であったとしても、必ず専門の医療機関を受診して治療を行うことが大切です。
怪我が軽傷の場合でも、傷害(入通院)慰謝料を請求し、受け取ることはできますが、検査を受けて医療機関で治療を行うことが前提となります。
適正な示談金を獲得するためにも、以下の点に注意が必要です。
- 事故直後は必ず警察に通報する
- 加入している保険会社に連絡する
- 速やかに医療機関を受診する
- 必要に応じて人身事故に切り替えを行う
順にご説明します。
(1)事故直後は必ず警察に通報する
怪我が比較的軽い場合や事故直後に目立った外傷などがない場合にも、必ず警察に通報することが大切です。
そもそも交通事故に遭った場合には、道路交通法で警察への通報が義務付けられています。
警察への通報を怠った場合、道路交通法違反となり、3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑事罰を受けるおそれがあるほか、交通事故証明書の交付を受けられなくなってしまいます。
この証明書がない場合には、事故の発生自体に争いが生じ、本来であれば受け取ることができる保険金を請求できない可能性があります。
したがって、適正な賠償金を獲得するためにも、事故直後に必ず警察に通報しましょう。
(2)加入している保険会社に連絡する
警察への通報や対応を済ませた後は、ご自身が加入している保険会社にも連絡をすることが重要です。
契約内容によっては、ご自身の任意保険からも保険金を受け取ることができる場合があります。
しかし、保険会社への連絡が遅れた場合には、十分な補償を受けられない可能性もあるため、必ず連絡をしておきましょう。
なお、交通事故の被害者が利用できる保険については、以下の記事で詳しく解説しています。
(3)速やかに医療機関を受診する
軽傷の場合や目立った外傷・自覚症状がない場合でも、必ず整形外科などの専門の医療機関を受診し、精密検査を受けるようにしましょう。
自力で怪我の治療を行った場合、通院をしていないため、たとえ怪我を負っていたとしても、傷害(入通院)慰謝料を受け取ることはできません。
また、事故直後に自覚症状が見られない場合にも、時間が経過するにつれて痛みや痺れなどの症状が現れることもあります。
しかし、事故から時間が経過するほど、事故と症状との間の因果関係を証明することが難しくなり、治療費や慰謝料を受け取ることができないリスクが高まる点に注意が必要です。
示談交渉で不利に扱われる可能性があるため、症状の有無にかかわらず、なるべく事故直後に整形外科などを受診し、事故との因果関係を証明するための対応を行いましょう。
なお、事故から時間が経過してから痛みや痺れなどが現れた場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
(4)必要に応じて人身事故に切り替えを行う
交通事故は、当事者に明らかな外傷などがない場合には、物損事故(物件事故)として警察に処理されます。
ただし、後日怪我が明らかになった場合は、手続を行うことで人身事故への切り替えが可能です。
人身事故として処理されると、事故状況について詳細に記載された「実況見分調書」が作成されます。
実況見分調書には、事故態様や事故当時の路面状況などについて詳しく記載されるため、示談交渉においては当事者の過失割合を立証する際に有益です。
特にドライブレコーダーや防犯カメラなど、事故態様を客観的に証明する資料が不足している場合には、実況見分調書が活用できるため、人身事故に切り替えるメリットが大きくなります。
必ずしも人身事故に切り替える必要はありませんが、事故の状況を証明する資料が不足している場合には、被害者の過失が高く見積もられてしまい、十分な賠償を受けることができないリスクもあるため、注意が必要です。
なお、事故から日数が経過しすぎると、受理されない可能性があるため、人身事故に切り替える場合には、できる限り早めに切り替えの手続を行いましょう。
実況見分調書が示談交渉に与える影響や実況見分の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
なお、人身事故への切り替えを行う場合には、医療機関を受診し、診断書を作成してもらう必要があります。
人身事故への切り替えを行う流れや切り替えを行わないデメリットについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
4.怪我が軽傷の場合でも弁護士に相談・依頼すべきケース

先ほども述べたように、軽傷の場合でも治療を行うことで、治療費や慰謝料などを加害者側に請求し、受け取ることが可能です。
もっとも、骨折などの重傷の場合とは異なり、受け取ることができる示談金は低くなる傾向があります。
そのため、怪我が軽傷の場合には、弁護士に依頼しても増額幅を弁護士費用が上回る「費用倒れ」が生じるケースもあるのです。
しかし、以下のような場合には、たとえ怪我が軽傷であっても、弁護士に相談・依頼するメリットが大きいといえます。
- 通院が長期にわたっている場合
- 治療費の打ち切りを打診されている場合
- 後遺症が残った場合
- 示談金の提示があった場合
なお、被害者が加入している保険に弁護士費用特約が付与されている場合は、その制度を利用することで、弁護士費用の負担がなくなる場合が多いです。
弁護士費用特約の補償内容や利用すべきケースなどの詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
(1)通院が長期にわたっている場合
交通事故によって発生した怪我が軽い場合でも、6か月ほど通院による治療を続けている場合には、弁護士に相談することがおすすめです。
通院が長期に及ぶ場合には、傷害(入通院)慰謝料も高額になる可能性があり、加害者側の保険会社も支出を抑えるために厳しい姿勢で示談交渉に臨む可能性が高まります。
例えば、治療期間が6か月程度の場合には、裁判所基準では80~90万円が相場となり、このような場合には、費用倒れが生じる可能性は低いです。
しかし、裁判所基準で算出した傷害(入通院)慰謝料を請求し、受け取るためには弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
そのため、より高額な傷害(入通院)慰謝料を受け取りたい場合には、まずは弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談することで、獲得できる賠償金の見込みについて説明を受けることができるだけでなく、費用倒れのリスクについても説明を受けることができます。
なお、交通事故の相談については、相談料を無料としている法律事務所もあるため、費用倒れの心配がある場合にも、まずは弁護士に相談してみましょう。
(2)治療費の打ち切りを打診されている場合
加害者側の保険会社から一括対応の打ち切りを打診された場合も、弁護士に相談しましょう。
先ほども述べたように、加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社が治療費について支払を行う「一括対応」が行われます。
一方で、治療費を永久に支払ってもらえるわけではありません。
怪我が軽傷であれば、打撲の場合は平均的な治療期間が1か月程度、むちうちの場合には3か月程度であり、それぞれの期間が経過した頃に打ち切りを打診されることが多いです。
ただし、安易に加害者側の保険会社の打診に応じて治療をやめてしまうと、傷害(入通院)慰謝料が減額されてしまい、十分な賠償を受けられない可能性があります。
また、治療をやめたことによって症状が悪化し、後遺症となってしまった場合にも、治療を中断したことで後遺症となったと評価されて、後遺障害等級の認定で不利に扱われかねません。
あくまで治療の必要性を判断するのは医師であり、保険会社ではないため、主治医が治療を継続する必要性があると判断している場合には、治療をやめないようにしましょう。
もし相手方から打ち切りを打診された場合には、弁護士に相談することで、保険会社との間で一括対応の延長を交渉できることがあります。
そのため、一括対応の打ち切りを打診された場合には、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
なお、むちうちの場合に打ち切りの打診を防ぐ方法や打診された際の対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。
(3)後遺症が残った場合
打撲やむちうちなどの怪我の治療を6か月以上にわたって治療したものの、完治せずに症状固定となった場合にも弁護士に相談することがおすすめです。
症状固定とは、一定期間にわたって治療を行ったものの、症状が一進一退となり、これ以上治療を継続しても医学的に改善しない状態をいいます。
この時点で残存している症状を後遺症といい、それが後遺障害等級に認定されれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の請求が認められます。
なお、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の金額は、認定される等級によって数十万円〜数百万円単位で変動するため、適切な等級の認定を受けることが最も重要です。
後遺障害等級の認定を受けるためには、交通事故と症状に因果関係があることや症状を医学的に証明・説明できることなどが求められます。
しかし、軽傷の場合には、レントゲンやMRIなどの画像所見上では異常が見られないことも多いため、適切な等級に認定されるためには工夫が必要となる点に注意しましょう。
もっとも、専門知識や実務経験がなければ、どのような点に注意すべきかは判断が難しく、適切な等級の認定を受けられないだけでなく、等級非該当となるリスクもあります。
したがって、症状固定の診断を医師から受けた場合には、どのような後遺障害等級に認定される可能性があるのかについて弁護士に相談することがおすすめです。
特に交通事故の対応に慣れた弁護士に相談することで、後遺障害等級の認定手続を依頼することもできます。
症状固定と後遺障害等級の関係については、以下の記事が参考になります。
また、後遺障害等級の意義や認定手続の流れなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(4)示談金の提示があった場合
保険会社が提示する金額に疑問を感じたときも、弁護士に相談することをおすすめします。
加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社が示談金を支払いますが、提示してくる金額が必ずしも適正であるとは限りません。
これは、加害者側の保険会社が提示する示談金が自賠責基準又は任意保険基準に基づいて算出されることに理由があります。
先ほども述べたように、任意保険基準は自賠責基準と同程度の水準であることが多く、提示される示談金も低額な水準であることがほとんどです。
また、被害者の過失が高く見積もられていたりすることもあるため、安易に保険会社の提案を受け入れると、適正な額の示談金を受け取ることができないリスクがあります。
そのため、示談金の提示があったとしても、安易に応じず、まずは弁護士に相談の上で適正な相場であるかどうかのチェックを受けることが大切です。
まとめ
交通事故による怪我が軽傷であっても、医療機関を受診して治療を行うことで、加害者側に示談金を請求し、受け取ることができます。
そのため、怪我の内容や程度が軽い場合でも、自己判断せずにまずは整形外科などの専門の医療機関を速やかに受診し、治療を行うことが大切です。
怪我が軽い場合には、受け取ることができる示談金は低額になることが多いですが、怪我の治療に時間がかかっていたり、後遺症が残ったりした場合には、弁護士に相談するメリットが大きいといえます。
交通事故による怪我の治療や加害者側の保険会社への対応に不安や悩みがある場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、怪我の治療や示談交渉についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
交通事故で
こんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、保険会社・相手方とどんな風に対応すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を受けたいけど、後遺障害認定申請や示談交渉などさっぱりわからない・・・

事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 花吉 直幸 弁護士
所属 第二東京弁護士会
依頼者の方の問題をより望ましい状況に進むようにサポートできれば、それを拡充できればというやりがいで弁護士として仕事をしています。