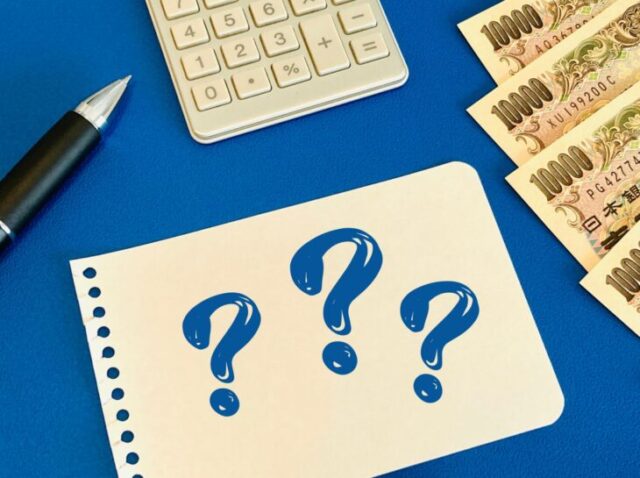後遺障害14級の認定を受けるデメリットは?申請方法や認定を受けるためのポイントも弁護士が解説

執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。
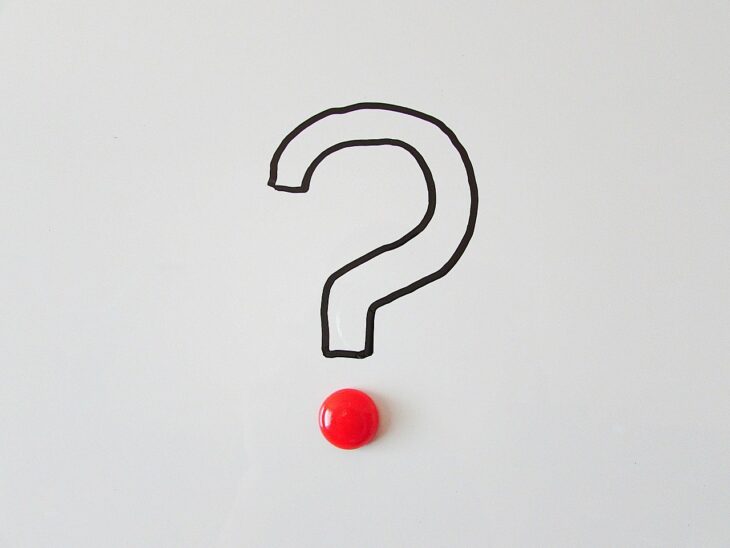
この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「後遺障害の14級の認定を受けることでどんな弊害があるのか」
「後遺障害等級で適切な等級の認定を受けるためには何に注意すべきなのか」
後遺障害等級の認定申請をしようと思っている方の中には、14級の認定を受けるメリットとデメリットを調べている方もいると思います。
後遺障害は、交通事故の怪我によって何らかの症状が残存してしまった場合に、そこから発生する損害を交通事故の賠償金に反映させるための制度です。
そのため、後遺障害の認定を受けることで、請求が認められる損害項目が増え、適正な賠償金を獲得することにもつながります。
もっとも、症状の内容や程度に応じた適切な等級の認定を受ける必要があり、認定手続の準備や申請方法など、注意すべきポイントは多岐にわたります。
本記事では、後遺障害14級の概要やデメリットの有無、申請方法のポイントなどについて解説します。
- 後遺障害等級の認定を受けることにデメリットはなく、認定を受けることで後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益について追加で賠償を受けることができる
- 後遺障害14級の認定を受けるためには、適切な期間と頻度で治療を行うなど、怪我の治療からいくつかの注意点がある
- 交通事故による怪我の治療が始まった段階で弁護士に相談することで、後遺障害等級の認定を視野に入れた対策を行うことができる
1.後遺障害14級の認定を受けるデメリットとは

結論からいえば、後遺障害等級の認定を受けることにデメリットはありません。
先ほども述べたように、後遺障害は交通事故の損害賠償に関わる制度です。
交通事故に遭うと、被害の状況によっては、さまざまな損害が発生します。
具体的には、以下のように分類することが可能です。
- 傷害による損害
- 後遺障害による損害
- 死亡による損害
- 物的損害
このうちの後遺障害による損害は、原則として後遺障害等級の認定を受けなければ、請求が認められません。
もし後遺障害等級の認定を受けることができれば、以下のような損害項目について、追加で賠償を受けることが可能です。
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
なお、これらの損害項目は、認定される等級によって金額の相場が定められています。
後遺障害等級は1~14等級まで存在し、最も低い等級が14級です。
そのため、後遺障害等級の認定を受けること自体にデメリットはないのですが、より上の等級認定の要件を満たしているにもかかわらず14級として認定されると、適切な賠償金額を受け取れないこととなります。
また、後遺障害等級は、医師から症状固定の診断を受けることによって申請を行うことができるようになります。
症状固定とは、交通事故による怪我の症状が一進一退となり、これ以上治療を継続しても医学的に改善しない状態のことです。
症状固定の診断を受けると、それ以降の治療費については、原則として交通事故による損害とは認められず、自己負担となる可能性が高いという点に注意が必要です。
交通事故による怪我と後遺障害の意義については、以下の記事も参考になります。
等級ごとの後遺障害慰謝料の金額については、以下の記事もご覧ください。
また、症状固定の基本概念や賠償に与える影響などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
2.後遺障害14級の概要

先ほども述べたように、14級は後遺障害等級の中で最も低い等級です。
後遺障害14級には、9つの号が設けられており、以下のような症状の場合に認定がされます。
| 号 | 症状(認定基準) |
| 1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
| 2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
| 4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
| 5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
| 6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
| 7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
| 8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
| 9号 | 局部に神経症状を残すもの |
14級の中でも、事例が多いのは神経症状の9号です。
交通事故の怪我の多くを占めるむちうちによる痛みや痺れが残った場合に認定される可能性がある等級です。
もっとも、認定申請を行う際にはいくつかのポイントを押さえておくことが重要です。
特に等級認定の手続には申請方法が2つあり、どちらの方法を選択するかによって等級認定に大きく影響を及ぼす可能性もあります。
そのため、症状固定の診断を受けた際には、なるべく早期に弁護士に相談することがおすすめです。
後遺障害14級の認定を受けられる可能性がある症状や個別の認定基準の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
3.認定申請の方法によるメリット・デメリット

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という第三者機関が行います。
認定を受けるためには、以下のいずれかの方法によって申請を行う必要があります。
- 事前認定
- 被害者請求
もっとも、申請方法によって、メリットとデメリットがあるため、比較した上で申請を行うことが望ましいです。
(1)事前認定
事前認定は、被害者が、加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)への申請手続を依頼する方法です。
被害者自身で複雑な手続を行う必要がない点が最大の特徴といえます。
具体的な手続の流れについては、以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてご参照ください。
#1:メリット
事前認定のメリットは、手続の手間を省くことができる点です。
被害者側で準備すべき書類は医師に作成してもらう後遺障害診断書のみであり、申請に必要となるほかの書類作成については、すべて加害者側の保険会社に任せることができます。
そのため、手続に必要な書類の作成や収集の手間を省くことが可能です。
#2:デメリット
事前認定は、加害者側の保険会社が中心となって手続を行うため、被害者に不利な認定結果が出る可能性が高まります。
後遺障害認定は、基本的には提出した書類に基づいて判断されるため、書類に記載する内容や添付書類はとても重要となります。
事前認定では、被害者は、加害者側の保険会社が作成する書類の内容を事前に確認できないため、認定の際に被害者に不利になるような記載や、不十分な記載があったとしても訂正や修正を求めることができません。
これによって、本来であれば認定を受けることができた等級よりも低い等級が認定されたり、等級非該当とされたりするリスクがあります。
このように、事前認定は、書類の不足や不備などによって適切な等級に認定されないリスクが高い申請方法といえるでしょう。
(2)被害者請求
被害者請求は、被害者自身で加害者側の自賠責保険に必要書類を提出し、申請を依頼する方法です。
被害者自身が必要書類を全て用意し、手続を主導する点に特徴があります。
具体的な手続の流れについては、以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてご参照ください。
#1:メリット
事前認定とは異なり、申請に必要な書類や資料は被害者側が主導して作成・収集を行うことになるため、提出書類などを工夫することで適切な等級に認定される可能性を高めることができます。
具体的には、後遺障害等級の記載内容を補強するための検査結果や医師の意見書などを添付することで、症状の内容や程度を医学的に証明・説明することが可能です。
また、被害者請求によって等級が認定されると、後遺障害による損害に対する保険金の一部が示談成立前に支払われることもメリットといえます。
#2:デメリット
被害者請求は、事前認定と比べると準備に手間がかかる点がデメリットです。
被害者自身が手続を進めなければならないため、後遺障害診断書をはじめとする書類や資料をすべて被害者側で準備し、提出する必要があります。
具体的には被害者請求の場合には、以下のような書類や資料について被害者側で準備をしなければなりません。
- 後遺障害診断書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診療報酬明細書
- 検査結果(レントゲン、CT、MRI) など
もっとも、弁護士に手続を依頼することで、書類作成や資料収集のサポートを受けることが可能です。
また、適切な等級の認定を受けた後に、引き続き示談交渉を弁護士に依頼することもできます。
弁護士に示談交渉を依頼することで、裁判所基準と呼ばれる算定基準を用いた交渉を行うことができるため、弁護士に依頼しない場合と比較して、より高額な示談金を受け取ることが可能です。
症状に合った適切な等級に認定されるためにも、まずは弁護士に相談の上、手続を依頼することをおすすめします。
4.後遺障害14級の認定を受けるためのポイント

後遺障害14級では、認定される可能性を高めるという観点から、被害者請求による認定申請を行うことがおすすめです。
また、以下のようなポイントを押さえることで、認定される可能性をさらに高めることにつながります。
- 事故から間を置かずに医療機関を受診する
- 必要な検査を受ける
- 適切な期間と頻度で治療を行う
- 残存している症状を正確に伝える
順にご説明します。
(1)事故から間を置かずに医療機関を受診する
事故から間を置かずに医療機関を受診しましょう。
後遺障害として認定されるためには、怪我と交通事故との間に因果関係が認められる必要があります。
一般的には、事故から1週間程度が経ってから受診すると、怪我が事故によって生じたものかがわからなくなるので、怪我と事故との間の因果関係が認められにくくなってしまいます。
そのため、交通事故に遭った場合には、事故後すぐに整形外科などの専門の医療機関を受診しましょう。
また、怪我によっては交通事故の直後には自覚症状が現れないケースもあり、事故から時間が経過することによって徐々に何らかの症状が現れる場合もあります。
これらの理由から、事故直後に自覚症状がなくても、症状を自覚したら直ちに医療機関を受診することをおすすめします。
早めの受診は、怪我の完治を目指すとともに、適正な賠償金を獲得することにもつながります。
交通事故から時間が経過してから痛みなどの症状が現れた場合に受診すべき診療科や、早期に受診しないことによる損害賠償上のリスクについては、以下の記事もご覧ください。
(2)必要な検査を受ける
怪我の原因を証明するために、早期に必要な検査を受けましょう。
後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者本人の自覚症状だけでなく、他覚所見なども踏まえて、症状の原因を医学的に証明あるいは説明できなければなりません。
必要な検査の例としては、レントゲン検査やMRI検査、神経学的検査などが挙げられます。
なお、後遺障害14級9号の認定を目指すことが多いむちうちの症状は、筋肉や靭帯などの軟部組織が損傷を受けることで生じます。
軟部組織の異常はレントゲン検査では写らないため、MRI検査や神経の伝達を調べる神経学的検査を受けることが大切です。
怪我の内容などによって、受けるべき検査の内容は異なってくるため、どのような検査を受けるのがよいかについては、弁護士に相談することをおすすめします。
なお、むちうちの主な症状や分類については、以下の記事でも解説しています。
また、むちうちの後遺症の場合にMRI検査を受ける必要があるケースについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
このほか、後遺障害14級に認定される可能性があるものとしては、傷跡もあります。
傷跡が後遺障害14級に認定されるためのポイントについては、以下の記事も参考になります。
(3)適切な期間と頻度で治療を行う
適切な期間と頻度で怪我の治療を行うことも重要です。
一般的に、後遺障害等級の認定を受けるためには、6か月以上にわたって治療を継続し、症状固定に至っていることが必要です。
また、治療期間だけでなく、どのような頻度で治療を行ったかについても、認定審査の際に見られるポイントとなります。
治療期間が短かったり治療の頻度が少なかったりすれば、後遺障害が認められるほどの怪我ではないと評価され、等級非該当とされる可能性があります。
なお、むちうちや打撲などの場合には、事故後3か月程度経過した時点で、加害者側の保険会社から、症状固定の時期に関する打診とともに、治療費の一括対応を打ち切る旨の連絡がされることもあります。
これに応じて治療を止めてしまうと、その時点で症状固定となってしまい、後遺障害等級の認定申請を行ったとしても等級非該当となるリスクがあります。
そのため、保険会社からこのような連絡があったとしても、医師から治療が必要であると言われている場合には、医師の指示に従って治療を継続することが重要といえます。
また、弁護士に相談することで、一括対応の延長を交渉することも可能です。
後遺障害14級の認定を受けるための通院日数の考え方については、以下の記事も合わせてご参照ください。
(4)残存している症状を正確に伝える
担当医に残存している症状を正確に伝えることも大切です。
先ほども述べたように、後遺障害等級は、医師が作成する後遺障害診断書の内容をもとに審査・認定が行われます。
記載内容に不備などがあれば、等級非該当とされてしまうことがあります。
自覚症状は本人にしか分からないため、どの部位にどの程度の痛みが生じているかについて、具体的かつ正確に医師に伝えるようにしましょう。
また、後遺障害として認定されるためには、症状が一貫して現れており、天候などの要因に左右されていないことも重要です。
例えば、以下のような記載の場合には、等級非該当となる可能性があります。
- 事故直後は首に痛みがあったが、治療の経過で腕に痛みが移った
- 雨などの特定の日に痛みや症状が現れる
そのため、医師から後遺障害診断書を作成してもらった際には、自身が把握している症状と照らし合わせて、記載内容が正しいものになっているかを確認することも大切です。
なお、後遺障害診断書の記載項目やポイントについては、以下の記事で解説しています。
また、医師に症状を伝える際のポイントについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
5.後遺障害について弁護士に相談するメリット

怪我の内容や程度によっては完治するケースがあるものの、完治せずに後遺症となってしまった場合には、適切な後遺障害等級の認定を受けることで、適正な賠償金を獲得することができます。
そのため、交通事故の怪我の治療を開始した時点で弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、具体的には以下のようなメリットがあります。
- 治療に関するアドバイスを受けることができる
- 後遺障害診断書のチェックを依頼できる
- 被害者請求による申請のサポートを受けられる
順にご説明します。
(1)治療に関するアドバイスを受けることができる
弁護士から治療に関するアドバイスを受けることができます。
先ほど述べたように後遺障害等級の認定結果は、事故後にどのように治療をしてきたかによっても左右されるため、審査の段階でマイナスの評価を受けないように適切な治療を行うことが大切です。
弁護士に早期に相談すれば、後遺障害等級の認定申請を見越した対策を行うことができます。
特に交通事故の対応に慣れた弁護士であれば、適切な等級に認定されるためのポイントについても熟知しています。
弁護士のアドバイスの下で治療を行うと、適切な等級認定を受けられる可能性を高めることが可能です。
(2)後遺障害診断書のチェックを依頼できる
弁護士に後遺障害診断書のチェックを依頼することもできます。
後遺障害診断書の内容によって、後遺障害等級の認定がされるか否かや、認定される等級が変わるため、不備や漏れのないように細かく目を通すことが大切です。
担当医は、認定を受けるために必要な情報やポイントをすべて把握しているわけではありません。
作成してもらった後遺障害診断書が等級認定の際に適切なものであるかどうかは、交通事故の対応の専門家である弁護士にしか判断ができないということもあります。
また、弁護士に内容の確認を依頼し、修正などが必要な場合には、担当医に修正や訂正をお願いするためのサポートを受けることも可能です。
(3)被害者請求による申請のサポートを受けられる
被害者請求によって認定手続を行う場合には、弁護士から申請のサポートを受けることができます。
手続を進めるためには、被害者ご自身で必要書類や資料を揃えなければなりませんが、弁護士からアドバイスやサポートを受けることで、スムーズに進めることが可能です。
まとめ
後遺障害14級の認定を受けること自体にデメリットはありません。
症状に応じた適切な等級に認定されることで、適正な賠償金を獲得することにつながります。
もっとも、後遺障害等級の認定申請をする際は、適切な等級の認定を受けられるように治療に専念し、適切な申請方法によって手続を進める必要があります。
治療や手続に関して、弁護士に相談することで、適切な等級認定を受けられる可能性を高めることができます。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、後遺障害の認定手続などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
交通事故で
こんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、保険会社・相手方とどんな風に対応すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を受けたいけど、後遺障害認定申請や示談交渉などさっぱりわからない・・・

事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。