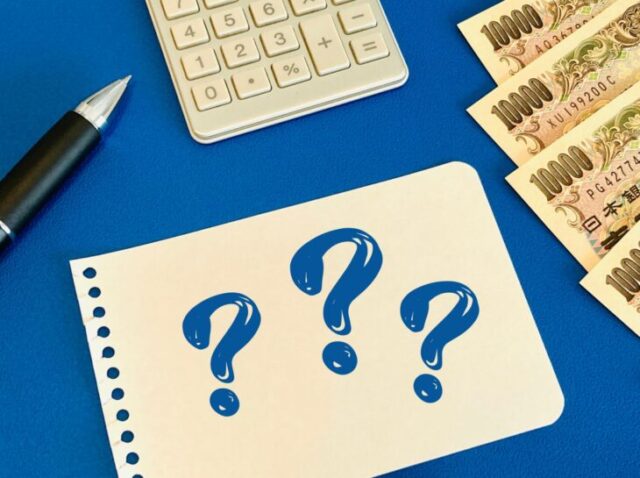過失割合が10対0の事故で怪我なしの場合の示談金の相場は?後から怪我が判明した場合の対応についても解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「過失割合が10対0で怪我がなかったときはどのくらいの示談金を受け取れるのか」
「過失割合が10対0で後から怪我が判明したときはどうしたらいいのか」
交通事故に遭った方の中には、このような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。
交通事故によって発生した損害の賠償については、事故の当事者等で話し合って金額などを決めることが多いです。
このように話し合いで解決する方法を「示談」といい、示談が成立したときに加害者側から支払われる損害賠償金を特に「示談金」と呼びます。
交通事故による損害が車両などの物のみに生じた場合には、その物的損害のみを加害者側に請求することになります。
もっとも、交通事故による怪我の症状は時間が経過してから現れることもあるため、すぐに示談に応じてしまうと適正な賠償を受けられないリスクがあります。
本記事では、過失割合が10対0の場合に怪我が生じなかった事故の示談金の相場や後から怪我が判明した場合の対処法などについて解説します。
- 交通事故に遭い、怪我がなく車両などの損壊のみが生じた場合には、物的損害のみを示談金として受け取ることができる
- 過失割合が10対0とされた場合には、被害者に過失がまったくないため、示談金が過失相殺によって減額されることはない
- 後から怪我が判明した場合には、示談が成立する前であれば、医療機関の受診と治療などの対応を行うことで、怪我の治療に関する賠償金を受け取ることができる
1.過失割合が10対0の場合に怪我が生じなかった事故の示談金

交通事故に遭ったものの、怪我が生じず、車両などの物の損壊のみが発生した場合には、物的損害のみを加害者側に請求し、受け取ることができます。
また、過失割合が10対0とされた場合には、示談金について過失による減額(過失相殺)が行われることはありません。
以下では、過失割合が10対0の怪我が生じなかった事故について、過失割合による影響がないことや具体的な示談金の相場について解説します。
(1)過失割合が10対0の場合に示談金に与える影響
過失割合とは、交通事故の発生に関する当事者の責任を割合で示したもので、「10対0」や「9対1」などと表されるのが一般的です。
過失割合が10対0というのは、一般的に被害者にまったく過失がないことを意味します。
過失割合が10対0となるのは以下のような事故態様のケースです。
- 被害者の車が赤信号で停止中に加害者の車が追突した
- 加害者の車がセンターラインを超えて対向車線を走行していた被害者の車に衝突した
- 交差点を青信号で走行していた被害者の車に対向車線の赤信号を無視して走行してきた加害者の車が衝突した など
交通事故の示談金は、過失相殺といって、過失割合に応じて金額が減額されることになります。
つまり、被害者側にも過失がある場合、示談金は減額されてしまいます。
例えば、損害の総額が100万円の場合、過失割合によって、以下のように最終的な示談金の額が変動します。
| 過失割合(加害者:被害者) | 被害者が受け取る最終的な示談金額 |
| 10:0 | 100万円×(1−0)=100万円(減額なし) |
| 9:1 | 100万円×(1−0.1)=90万円(1割減額) |
| 8:2 | 100万円×(1−0.2)=80万円(2割減額) |
過失割合が10対0とされた場合には、過失相殺が行われず、過失によって示談金が減額されることはありません。
過失割合は、事故の状況によって客観的に決まるものですから、示談の場合は当事者間の話し合いによって決められる事柄です。
目安として、過失割合について類型ごとに裁判所の考えをまとめたものがあり(別冊判例タイムズ38号)、そこでは動いている車同士の事故である場合、ほとんど双方に過失が認められるようになっています。
そのため、自分に過失がないと思っていても、10対0の過失割合となることはそれほど多くないことに注意が必要です。
過失割合が10対0とされるケースの詳細については、以下の記事もあわせてご覧ください。
また、過失割合の概要や意義、具体的な決め方などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)怪我なしの場合の示談金の項目と相場
交通事故に遭ったものの、怪我が生じず、車両などの損壊のみが発生した場合には、物損事故(物件事故)として扱われます。
物損事故の場合、車両の損壊などの物的損害について加害者側から示談金の支払を受けることが可能です。
物的損害に該当するものには、以下のような項目が挙げられます。
| 損害項目 | 内容 |
| 車両の修理費 | 事故によって損壊した部分の修理に要する費用(修理費用が車両の時価額を超える場合(経済的全損)を除く) |
| 時価額および買替諸費用 (経済的全損の場合) |
事故時の車両時価額および買替にかかる法定費用・手数料など |
| 評価損 | 車両の損傷が大きく修理後も評価額の減少が認められる場合の価値下落分の補填 |
| 代車使用料 | 修理・買替が完了するまでの間に必要な代車の費用 |
| 休車損害 | 業務用の車両が損壊した場合に、修理・買替が完了するまでの間の業務損害 |
以上のような損害について、実際に発生したものが賠償の対象となります。
そのため、車両の損害の程度等によって金額は変動するものであり、一概に相場を決めることはできません。
物的損害の各項目の詳細などについては、以下の記事もご覧ください。
2.示談交渉を行う際の注意点

先ほど述べたように、交通事故に遭ったものの、怪我を負わずに車両などの損壊のみが生じた場合には、物的損害の賠償のみを受けることになります。
また、過失割合が10対0の場合には、過失相殺による減額がされず、損害の全額について受け取ることが可能です。
ただし、このようなケースでも以下のようにいくつかの注意点があります。
- その場で示談をしない
- 被害者は自身の示談代行サービスを利用できない
- 過失や損害の立証を行わなければならない
順にご説明します。
(1)その場で示談をしない
交通事故に遭い、怪我や自覚症状がない場合でも、その場で示談を行うことは避けましょう。
示談は、一度成立すると原則として後から撤回することができません。
目立った怪我や外傷がなくても、事故直後は興奮状態で気づいておらず時間が経過して痛みや痺れなどが現れることもあります。
示談が成立してしまうと、後から損害が判明しても追加で賠償を受けることができなくなるリスクがあるため、すべての損害が確定してから行うことが大切です。
したがって、加害者から事故現場ですぐに示談を持ちかけられたとしても、これに応じないようにしましょう。
なお、事故後、徐々に痛みや痺れなどの症状が現れた場合には、示談が成立していなければ、通院による治療などの必要な対応を行うことで、治療費や慰謝料などを受け取ることが可能です。
以上から、事故直後に怪我や自覚症状が見られない場合にも、その場で安易に示談を進めることがないようにしましょう。
交通事故に遭った際の初期対応の流れやポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)被害者は自身の示談代行サービスを利用できない
過失割合が10対0の場合、被害者は自身が加入している任意保険の示談代行サービスを利用することができません。
過失がある場合は対物・対人保険利用の可能性があるため、保険会社は当事者として示談交渉を代行することができます。
しかし、過失がない被害者に代わって保険会社が示談交渉を進めることは、弁護士法で禁止されている非弁行為にあたるからです。
そのため、被害者ご自身で示談交渉を進める必要があることに注意しましょう。
なお、加害者側の保険会社の担当者は被害者に比べて交通事故の交渉についての知識・経験があるため、被害者が有利に示談交渉を進めることには困難が伴います。
保険会社との交渉に不安や悩みがある場合には、弁護士に相談し、示談交渉を依頼することでスムーズに交渉を進めることが可能です。
(3)過失や損害の立証を行わなければならない
被害者に過失がない場合、被害者が加害者側に対して過失や損害の立証を行わなければならない可能性があります。
過失割合が10対0の場合でも、示談交渉の結果、被害者にも過失があるとされれば、過失相殺によって示談金が減額されてしまいます。
加害者が任意保険に加入している場合、示談金はその保険会社が支払うことになり、被害者に過失が認められる分だけ加害者側の保険会社は支払う金額を低く抑えることが可能です。
そのため、加害者の保険会社が被害者の過失を主張してくる可能性があります。
加害者側に過失の主張をされた場合は、これに反論しなければなりません。
また、物的損害の発生についても、被害者自身が主張する必要があります。
これらの過失や損害の主張や反論を行う際は、加害者保険会社に対して根拠となる資料を示して主張しなければなりません。
しかし、どのような資料に基づいて過失の反論や損害の立証を行うべきかは判断が難しいことがほとんどで、被害者自身で的確に立証を行うことは困難です。
客観的には過失割合が10対0のケースでも、交渉がスムーズに進行するとは限らないため、まずは専門家である弁護士に相談することが望ましいといえます。
3.後から痛みなどが現れた場合の対応の流れ

先ほども述べたように、事故直後に目立った外傷や自覚症状がなく、怪我が発生していないと思っていても、時間が経過することで痛みなどが現れることがあります。
しかし、示談が成立する前であれば、必要な対応を行うことで、怪我の治療費や傷害(入通院)慰謝料などを受け取ることが可能です。
具体的には、以下の流れで対応を行いましょう。
- 直ちに医療機関を受診する
- 保険会社に連絡する
- 完治または症状固定まで治療を継続する
- 必要に応じて人身事故への切り替えを検討する
- 後遺症が残った場合には後遺障害等級の認定申請を検討する
- 認定結果ももとにして示談交渉を行う
順に見ていきましょう。
(1)直ちに医療機関を受診する
痛みや痺れなどの症状が現れた時点で、直ちに整形外科などの専門の医療機関を受診しましょう。
事故から時間が経過すればするほど、怪我と事故との因果関係を証明することが難しくなります。
事故と怪我との因果関係を医学的に証明できなければ、その怪我が事故によって生じているものだとしても、治療費や傷害(入通院)慰謝料を受け取ることができなくなってしまうリスクが高まるため、注意が必要です。
しかし、早期に医療機関を受診することで、事故と症状との間の因果関係が認められやすくなります。
受診の際は外傷を専門にしている医師に見てもらうことが必要ですので、整形外科を受診するようにしましょう。
(2)保険会社に連絡する
初診後に、加害者側の保険会社に連絡することが重要です。
加害者が任意保険に加入している場合には、治療費についてその保険会社が支払を行う「一括対応」が行われるのが一般的です。
治療費の支払を受けるためには、加害者側の保険会社に受診した旨を連絡しなければなりません。
ここで、加害者側の保険会社に連絡をせずに勝手に治療を開始すると、治療費の支払を断られたり、場合によっては事故による受傷を否定されたりといったトラブルに発展する可能性があります。
そこで、できれば医療機関を受診して治療を開始する前に、遅くとも受診した直後には連絡することが必要です。
自身の保険の契約内容によっては保険金を受け取ることができる可能性がありますので、自身が加入している保険会社にも連絡をしておきましょう。
この場合も、連絡が遅れると、保険金の支払が遅れたり、場合によっては支払を受けられなかったりするリスクがあります。
交通事故の被害者が利用できる保険の種類や補償内容については、以下の記事もあわせてご参照ください。
(3)完治または症状固定まで治療を継続する
治療を開始したら、完治または症状固定の診断を受けるまで治療を継続しましょう。
症状固定とは、一定期間にわたって治療を行ったものの、症状が一進一退となり、これ以上治療を続けても改善がないと認められる状態のことです。
完治または症状固定となった場合は、賠償の対象となる治療は終了となります。
示談交渉は治療が終了するまでは開始されないため、まずは怪我の治療に専念することが最も重要です。
(4)必要に応じて人身事故への切り替えを検討する
事故による怪我であることを医師に診断して貰った後は、必要に応じて人身事故への切り替えを検討しましょう。
交通事故が発生すると警察は損害の内容によって以下のいずれかの処理を行います。
| 分類 | 損害の内容 |
| 物損事故(物件事故) | 車両の損壊などの物的損害のみが生じている |
| 人身事故 | 事故の当事者に生命や身体に関する損害が生じている |
交通事故の当事者に怪我がない場合はもちろん、当事者が軽傷である場合も、警察は原則として物損事故(物件事故)として処理を行います。
この場合も、警察に診断書を提出して届け出を行うことで人身事故への切り替えをすることが可能です。
人身事故への切り替えが行われる最大のメリットは、実況見分調書と呼ばれる書類が作成されることにあります。
実況見分調書には、事故態様や事故当時の路面状況などについて詳細に記載されるため、示談交渉における過失割合の主張・立証などに活用することができます。
そのため、ドライブレコーダーや防犯カメラなどの客観的に事故状況を証明できる資料や証拠が不足している場合には、人身事故に切り替えた方が後の示談交渉を有利に進めることにつながります。
人身事故への切り替えは必須というわけではありませんが、過失割合について争いが生じることが見込まれる場合には、切り替えを行うことを検討してみましょう。
切り替えを行う際の手続の流れについては、以下の記事も参考になります。
(5)後遺症が残った場合には後遺障害等級の認定申請を検討する
怪我の治療を行ったものの、完治に至らず症状固定となった場合には、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討しましょう。
先ほど述べたように、一定期間にわたって治療を行っても医学的に改善が難しいと医師が判断したら症状固定となります。
症状固定の診断を受けた時点で残存している症状を後遺症といい、これが自賠法に定められている後遺障害として認定を受けることができれば、以下の項目について賠償が認められます。
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
具体的な金額は、認定される等級によって異なり、等級が1つ異なるだけで数百万円の差が生じることもあります。
また後遺症が残っても必ず何らかの等級に認定されるわけではありません。
申請書類の内容が不十分であったり、そもそも認定基準を満たしていなかったりすると、等級非該当と判断される可能性があります。
後遺障害等級の認定を受けられなければ、加害者側に対して後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求することができなくなる点に注意しましょう。
なお、申請を行うためには医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
後遺障害診断書の記載項目や作成してもらう際のポイントについては、以下の記事もご覧ください。
(6)認定結果ももとに示談交渉を行う
後遺障害等級の認定結果が出たら、それももとにして加害者側と示談交渉を行います。
なお、後遺症が残らなかった場合や等級非該当となった場合でも、怪我の治療費や傷害(入通院)慰謝料、休業損害などの賠償金を受け取ることは可能です。
これらの各項目を算定の上、金額について示談交渉によって定めていくことになります。
後遺障害等級が非該当となった場合に受け取ることができる示談金の項目については、以下の記事も参考になります。
4.怪我が判明した場合に弁護士に相談するメリット

上記のように、後から怪我が判明した場合には、速やかに医療機関を受診して治療を行うなどの対応を行うことで、怪我に関する損害についても賠償を受けることができます。
ただし、過失割合が10対0とされる場合には、被害者自らで示談交渉を進めなければならず、加害者側の主張次第では交渉が難航することも多いです。
また、事故と怪我との間の因果関係を疑われ、治療費の支払などを巡ってトラブルになる可能性もあります。
そのため、怪我が後から判明した場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。
- 治療の注意点などについてアドバイスを受けることができる
- 後遺症が残った場合に後遺障害等級の認定申請を依頼できる
- 保険会社への対応や示談交渉を一任できる
- 示談金の増額が期待できる
順に解説します。
(1)治療の注意点などについてアドバイスを受けることができる
弁護士に相談することで、治療における注意点についてアドバイスを受けることができます。
人的損害の項目のうち、傷害(入通院)慰謝料は、治療の期間あるいは日数によって具体的な金額が決まります。
適正な傷害慰謝料を受け取るためには、怪我の内容や程度に応じた適切な頻度や期間で治療を継続することが重要です。
例えば、症状が軽いからといって、医師の指示に従わず通院をしないままでいると、加害者側からは怪我の程度が軽いと判断され、傷害慰謝料を減額される可能性が高まります。
反対に、必要以上に通院の頻度が高かったり、治療の期間が長期に及んだりすると、今度は過剰診療を疑われて治療費の支払を打ち切られるリスクが高まってしまいます。
このように、通院の頻度が多すぎても少なすぎても慰謝料が減額されてしまうリスクがあります。
怪我の治療が始まった段階で弁護士に相談することで、治療のポイントについて説明やアドバイスを受けることができ、適正な示談金を獲得することにつながります。
(2)後遺症が残った場合に後遺障害等級の認定申請を依頼できる
後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定申請の手続を弁護士に依頼することができます。
症状の内容や程度に応じた適切な等級の認定を受けることで、残存した後遺症に関する損害についても、示談金に反映することが可能です。
後遺障害等級の認定にあたっては、医師が作成する後遺障害診断書の記載内容が最も重視されます。
もっとも、診断書のどのような項目にどのような記載が必要かなどについては、認定を目指す等級によっても異なり、専門知識や実務経験が求められる事柄です。
交通事故の対応に習熟した弁護士であれば、等級の認定を受けるためのポイントについて熟知しています。
そのような弁護士に相談の上で手続を依頼すれば、書類作成や資料収集に関するアドバイスやサポートを受けることができ、適切な等級に認定される可能性を高めることが可能です。
(3)保険会社への対応や示談交渉を一任できる
弁護士に相談の上で保険会社への対応や示談交渉を一任できる点も大きなメリットです。
繰り返しになりますが、過失割合が10対0の場合には、被害者自身で加害者側と交渉を進める必要があります。
しかし、加害者側の保険会社の担当者は交渉のプロであり、専門知識や交渉経験がなければ、交渉を進めることには困難が伴います。
また、怪我の治療を行いながら示談交渉を進めることには、精神的・身体的負担も大きいです。
そのような場合には、弁護士に相談の上で保険会社との交渉を依頼することで、負担から解放され、安心して治療に専念することができます。
(4)示談金の増額が期待できる
示談交渉を弁護士に一任することで、示談金の増額が期待できます。
示談金の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあります。
このうち、自賠責基準は交通事故の被害者の損害について、最低限度の補償を行うことを目的としているため、最も低額な水準です。
また、加害者側の保険会社が用いる任意保険基準も自賠責基準と同程度の水準にとどまることがほとんどです。
これらに対して、裁判所基準は過去の裁判例をもとにした算定基準であり、最も高額な示談金が算出されやすい点に特徴があります。
被害者自身で加害者側の保険会社と示談交渉を行う場合にも、裁判所基準に基づいて示談金を算出し、支払を求めることは可能です。
もっとも、そのような場合には、保険会社が裁判所基準での支払に応じることはほとんどありません。
しかし、弁護士が示談交渉を行うことで、裁判所基準での支払に応じることが多いです。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼することで、最終的に受け取ることができる示談金の増額が期待できます。
まとめ
交通事故に遭い、怪我を負わずに車両などの物的損害のみが生じた場合には、その物的損害に関する賠償のみを受けることができます。
また、過失割合が10対0とされる事故態様では、被害者にまったく過失がないため、過失によって示談金が減額されることはありません。
もっとも、被害者に過失がまったくない場合には、被害者自身が加害者側の保険会社と示談交渉を行わなければならない点に注意が必要です。
また、事故から時間が経過して怪我や新たな損害に気づくこともあるため、安易にその場で示談に応じないことが最も重要といえます。
交通事故に遭い、示談交渉を含め、その後の法的対応に不安や悩みがある場合には、まずは専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、その後の対応の見通しを立てることができるほか、保険会社への対応や示談交渉を任せることもできます。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、過失がまったくないとされた場合の対応でお困りの被害者の方はお気軽にご相談ください。
交通事故で
こんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、保険会社・相手方とどんな風に対応すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を受けたいけど、後遺障害認定申請や示談交渉などさっぱりわからない・・・

事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。