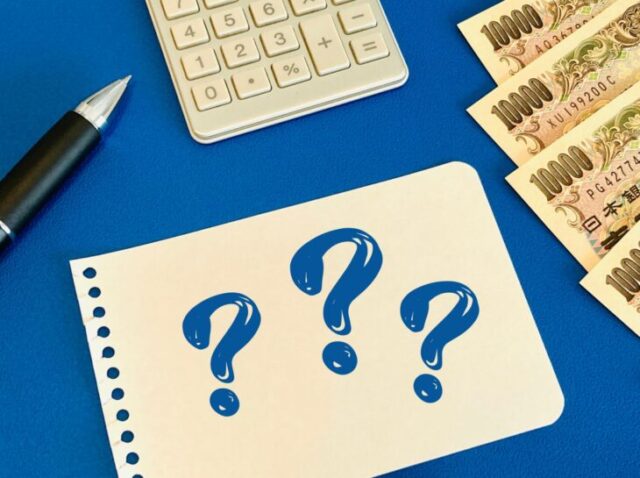交通事故で頭痛が生じる原因は?対処法や示談金の項目についても解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「交通事故で頭痛が生じたときはどうしたらいいのか」
「交通事故で頭痛が生じたときの示談金はどうなるのか」
交通事故によって頭痛が生じている方の中には、症状が発生した後の対応や示談金の項目などについて疑問や不安をお持ちの方もいると思います。
頭部や首に強い衝撃が加わることで、頭痛などの症状が現れることがあり、中には重大な怪我に発展するケースもあります。
そのため、交通事故によって頭痛が生じた場合には、早期に整形外科などの専門の医療機関で治療を受けることが欠かせません。
本記事では、交通事故で頭痛が生じる原因や対処法、示談金の項目等について解説します。
- 交通事故によって頭痛が生じる原因には、むちうち(頚椎捻挫)や脳挫傷が多い
- 頭痛が事故直後から現れている場合はもちろん、事故から時間が経過して現れた場合にも、速やかに整形外科などを受診して精密検査を受けることが大切
- 交通事故によって頭痛が生じた場合には、医療機関で治療を受けることで、治療費や傷害(入通院)慰謝料、休業損害などの項目について賠償を受けることができる
1.交通事故が引き起こす頭痛の原因

交通事故によって体に強い衝撃が加わると、頭痛の症状が現れることがあります。
脳自体に衝撃が加わることで引き起こされるほか、神経や筋肉が損傷を受けるなど様々な原因が考えられますが、以下のような傷病が原因となって頭痛が引き起こされることが多いです。
- むちうち
- 脳挫傷
これらの症状は、交通事故直後から現れることがあるものの、場合によっては数日経過してから徐々に現れるケースもあります。
特に事故直後は強い興奮状態にあり、痛みなどの症状に気づきにくいことがあります。
そのため、頭痛のほか、痺れや打撲などの症状や外傷が現れた時点で、直ちに医療機関を受診し、必要な検査や治療を受けることが重要です。
交通事故に遭った後に受診すべき診療科や速やかに医療機関を受診しないことによるデメリットなどについては、以下の記事も参考になります。
(1)むちうち
むちうちとは、強い衝撃を受けて首に大きな負荷がかかることで痛みが生じる症状の総称です。
診断書には、頚椎捻挫や外傷性頚部症候群と記載されます。
交通事故による強い衝撃が首に加わることで、頭部が大きく揺さぶられることによって生じることが多いです。
主に痛みや痺れ、頭痛などのほか、吐き気などの神経症状が現れます。
大体3か月から6か月程度の治療を行うことによって完治することが多いです。
もっとも、場合によっては6か月以上にわたって治療を継続したものの、完治には至らずに症状固定となってしまい、慢性的な痛みや痺れなどが残ってしまうこともあるため、注意が必要です。
そのような場合には、後述する後遺障害等級の認定申請を行うことを検討することになります。
むちうちの症状や治療期間の目安、治療を行う際の注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
(2)脳挫傷
脳挫傷は、頭部への強い衝撃によって、脳が損傷を受けたり、出血を起こしたりすることです。
これによって、激しい頭痛や吐き気のほか、体の麻痺や言語障害などの重篤な症状が現れることもあります。
このような場合には、早期に適切な治療を行わなければ、体の麻痺や言語障害などの後遺症が残るだけでなく、最悪の場合、命に関わる可能性があるため、直ちに専門の医療機関を受診しましょう。
なお、これらの症状は交通事故の直後から現れることもありますが、事故直後は目立った症状や外傷がなく、時間の経過によって出血が広がって徐々に症状が現れることもあります。
また、骨ではなく脳自体に損傷が生じることから、レントゲン検査では異常が見られないことがほとんどであり、CT検査やMRI検査を受けて初めて判明することが多いです。
したがって、頭を強く打ちつけた場合は、事故直後に目立った自覚症状がなくても、直ちに医療機関を受診し、CTやMRIなどの必要な検査を受けることが重要といえます。
頭蓋骨骨折の態様や派生傷害の症状、生じうる後遺症などについては、以下の記事もあわせてご参照ください。
2.交通事故によって頭痛が現れた場合の対処法

交通事故後に頭痛が生じた場合、上記のような怪我を負っている可能性があります。
症状が現れてからも適切な治療を行わなければ、症状が悪化するだけでなく、適正な賠償金を獲得することができないリスクが高まります。
そのため、交通事故後に頭痛が生じた場合には、以下の流れで対応を行うことが重要です。
- 直ちに専門の医療機関を受診する
- 後遺症が残った場合には後遺障害等級の認定申請を検討する
順にご説明します。
(1)直ちに専門の医療機関を受診する
交通事故の直後から頭痛が生じている場合はもちろん、事故から時間が経過してから症状が現れた場合にも、直ちに専門の医療機関を受診しましょう。
例えば、事故の衝撃で首に大きな負荷がかかった場合には、むちうちによる頭痛である可能性が高いため、整形外科を受診することがおすすめです。
また、頭を強く打ちつけた場合には、脳挫傷や骨折が生じている可能性もあるので、脳神経外科などを受診することも検討しましょう。
もっとも、事故から時間が経過して医療機関を受診すると、事故と怪我の因果関係を証明することができず、治療費などを交通事故による損害として請求することができなくなってしまう可能性があります。
そのため、症状の有無に関わらず、なるべく早期に医療機関を受診して精密検査などを受けることで、事故と怪我の因果関係を証明しやすくなります。
なお、医療機関を受診した際には、頭痛が生じた時期や部位、どのような痛みが生じているのかなどの自覚症状について細かく医師に伝えることが大切です。
また、目立った外傷などがない場合でも、脳が損傷を受けたことによって頭痛が生じている可能性もあるため、レントゲン検査だけでなく、CTやMRIなどの検査も追加で受けることを検討しましょう。
(2)後遺症が残った場合には後遺障害等級の認定申請を検討する
治療を続けても症状が改善しない場合、医師から症状固定の診断を受けることがあります。
症状固定とは、一定期間にわたって治療を継続したものの、症状が一進一退となり、これ以上治療を続けても医学的に改善しない状態のことです。
この時点で残っている症状を後遺症といい、症状に応じて、後遺障害の認定を受けられる可能性があります。
後遺障害等級の認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の請求をすることができます。
なお、後遺障害等級の認定を受けるためには、医師が作成する後遺障害診断書の内容が重要です。
もし書類等に不備などがあれば適切な等級に認定されない場合や等級非該当となる場合があります。
したがって、自覚症状の内容や現れ方などについては詳細に医師に伝えて、作成してもらった後も内容がご自身の症状を的確に表現できているか確認することが重要です。
後遺障害診断書の概要や記載項目、自覚症状の伝え方などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
後遺障害等級の認定申請には、事前認定と被害者請求の2つの方法があり、被害者の方が自由に選ぶことができます。
#1:事前認定
事前認定は、加害者側の任意保険会社に対して後遺障害等級の認定申請を依頼する方法です。
この方法では、被害者が準備する書類は後遺障害診断書のみで、認定手続を加害者側の保険会社に依頼することができるため、手続の手間を省くことができる点にメリットがあります。
しかし、加害者側の保険会社が準備する書類や資料をあらかじめ確認することができず、書類に不備などがあったとしても、訂正や修正を求めることができません。
つまり、適切な等級に認定されない場合や等級非該当となってしまう場合もあり、手続の透明性に疑問が残るというデメリットがあります。
事前認定の手続の特徴や流れについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
#2:被害者請求
被害者請求は、被害者ご自身で必要な書類や資料を収集した上で加害者側の自賠責保険を介して申請を行う方法です。
事前認定と比較すると、手続に必要な書類や資料をすべて被害者側で準備しなければならず、手間がかかるというデメリットがあります。
一方で、書類の書き方や追加資料の添付などによって、症状に適した等級の認定を受けられる可能性を高めることが可能というメリットがあります。
認定される等級で大きく示談金の金額が変わるため、なるべく事前認定ではなく、被害者請求で手続を行うことをおすすめします。
被害者請求の流れや必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
3.交通事故による頭痛で受け取ることができる示談金の項目

交通事故によって頭痛の症状が現れた場合には、上記の流れで対応することで、加害者側に対して示談金を請求し、受け取ることができます。
示談金には、交通事故によって生じた損害に対する賠償金が含まれており、具体的には、以下のような項目について受け取ることが可能です。
- 治療費
- 傷害(入通院)慰謝料
- 休業損害
- 入通院に関するその他の費用
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
なお、先ほども述べたように、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、後遺障害等級の認定を受けて初めて請求が認められます。
そのため、後遺症が残らなかった場合や後遺障害等級の認定を受けられなかった場合には請求を行うことができないことに注意が必要です。
(1)治療費
怪我の治療に要した費用については、実費を加害者側に請求して受け取ることができます。
もっとも、交通事故と怪我の間に因果関係が認められる範囲においてのみ支払を受けられることに注意が必要です。
なお、加害者が任意保険に加入している場合には、治療費については加害者側の保険会社が支払いをする「一括対応」を受けることができます。
そのため、被害者は治療費について自己負担をすることなく、怪我の治療に専念することが可能です。
ただし、示談交渉が始まる前に治療費の支払いを受けた場合には、示談交渉の際にその分が既払金として最終的に受け取ることができる示談金から差し引かれることを押さえておきましょう。
また、一括対応はあくまで保険会社のサービスであり、支払いを強制することはできないため、治療が不十分な段階で支払いを拒否されたり打ち切られたりすることもあります。
しかし、加害者側の保険会社から治療費の支払を拒否または打ち切られたとしても、医師が治療を継続する必要性があると判断している場合には、健康保険を利用するなどして怪我の治療を行うことが最も重要です。
なお、健康保険などを利用して自己負担した治療費については、示談交渉において加害者側に請求し、受け取ることができます。
一方で、上述のとおり、交通事故と怪我に因果関係が認められる範囲において支払を受けることができることに注意しましょう。
治療費を被害者ご自身で立て替える必要があるケースや自己負担した治療費を請求する流れについては、以下の記事が参考になります。
(2)傷害(入通院)慰謝料
傷害(入通院)慰謝料は、交通事故によって怪我を負ってしまった精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
3つの算定基準があり、どの基準に基づいて計算を行うかによって算出される金額が異なります。
具体的な算定基準は以下のとおりです。
| 算定基準 | 特徴 |
| 自賠責基準 | 自賠責保険が用いる。交通事故被害者の損害について最低限の補償を行うことを目的としているため、3つの算定基準の中では最も低額な水準。 |
| 任意保険基準 | 詳細は非公開であるものの、自賠責基準と同程度かやや上回る水準にとどまることが多い。 |
| 裁判所基準 | 裁判所が用いる。過去の裁判例をもとにした基準であり、3つの中では最も高額な算定基準。 |
いずれの算定基準においても、治療期間や治療日数に基づいて具体的な金額が算出されるため、適切な期間・頻度で治療を行うことが適正な傷害(入通院)慰謝料を受け取るために大切です。
具体的な算定方法や適正な金額を受け取るためのポイントについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
(3)休業損害
休業損害は、交通事故を原因とする怪我の治療のために仕事を休まざるを得なくなったことで減少した収入に対する補償です。
そのため、仕事を休まなかった場合や収入が変わらなかった場合には基本的には請求できません。
傷害(入通院)慰謝料と同様に3つの算定基準があり、いずれの算定基準でも、以下の算定式に基づいて計算することができます。
- 1日あたりの基礎収入×休業日数
自賠責基準では、収入にかかわらず一律に基礎収入の日額が定められています。
これに対して、裁判所基準では被害者の事故前の収入をもとに基礎収入が定められているため、より実際の減収額に近い金額を算出し、請求を行うことが可能です。
算定基準ごとの休業損害の計算方法や適正な金額を受け取るためのポイントについては、以下の記事が参考になります。
(4)入通院に関するその他の費用
怪我の治療のために入院・通院したことによって発生した費用についても、加害者側に請求を行い、受け取ることができます。
具体的には、以下のような費用について補償を受けることが可能です。
- 入院雑費
- 通院交通費
- 付添看護費・交通費
入通院中に発生した費用は請求できる可能性があるため、必ず領収書やレシートは保管しておきましょう。
なお、それぞれの具体的な算定方法については、以下の記事もあわせてご参照ください。
(5)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
認定される等級に応じて受け取ることができる金額が異なり、例えば、むちうちによる頭痛の後遺症は、以下のような後遺障害等級に認定される可能性があります。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判所基準 |
| 12級13号 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円(32万円) | 110万円 |
※()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合
上記のように認定される等級によって金額が変動するため、症状に応じた適切な等級の認定を受けることが適正な賠償金を獲得することにつながります。
なお、むちうちによる症状が後遺障害として認定されるためのポイントや等級ごとの認定基準の違いについては、以下の記事が参考になります。
(6)後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺障害を負ったことによる将来の収入の減少に対して支払われる賠償金です。
具体的には、以下の算定式に基づいて算出されます。
- 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
このうち、労働能力喪失率は、認定される後遺障害等級に応じて定められています。
なお、後遺障害等級の認定を受けることによって、どのような場合にも後遺障害逸失利益の請求が認められるわけではありません。
後遺障害によって仕事にどのような影響が生じているかについて、加害者側に対して具体的に主張・立証を行うことが重要です。
後遺障害逸失利益を受け取るための要件や具体的な算定方法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
4.示談交渉について弁護士に依頼するメリット

交通事故によって頭痛の症状が現れた場合には、速やかに専門の医療機関を受診することが怪我の治療を行うとともに適正な賠償金を獲得するために重要です。
また、事故後も頭痛が続くようであれば、後遺障害等級の認定申請を行うことで、後遺障害に認定され、追加で賠償金を受け取ることができる場合もあります。
交通事故による賠償問題は、加害者側との示談交渉によって決めることが一般的です。
しかし、示談交渉は専門知識や実務経験が必要となる場面が多く、交渉に慣れていない被害者の方がご自身で進めることには困難が伴います。
さらに、怪我の治療や頭痛の症状といった問題を抱えながら加害者側と交渉を行う必要があり、身体的負担も大きいです。
そのような場合には、なるべく早期に弁護士に相談し、示談交渉に関するアドバイスやサポートを受けることをおすすめします。
弁護士に相談・依頼するメリットは以下のとおりです。
- 保険会社への対応を一任することができる
- 後遺障害等級の認定手続を依頼できる
- 適切な過失割合の立証を行うことができる
- 最終的に受け取ることができる示談金の増額が期待できる
順にご説明します。
(1)保険会社への対応を一任することができる
弁護士に相談した上で、示談交渉を依頼することで、保険会社への対応を一任することができます。
保険会社は交渉のプロでもあり、専門的知識を持ち合わせていない被害者の方がご自身で対応することは難しい場合が多いです。
特に怪我の治療を行いながら加害者側の保険会社への対応を行うことは精神的にも身体的にも負担となることが考えられます。
また、知らず知らずのうちに加害者側に有利な内容で示談がまとまってしまうリスクもあります。
弁護士に交渉を任せることで、被害者は治療や私生活に専念することができるため、交渉にかかるストレスから開放される点が大きなメリットです。
(2)後遺障害等級の認定手続を依頼できる
弁護士に後遺障害等級の認定手続を依頼することもできます。
事故によって後遺症が残った場合、その内容や程度によっては、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討することになります。
加害者側の保険会社に手続を依頼することも可能ですが、それでは適切な書類等で申請が行われるとは限らず、等級非該当となるリスクもあるのです。
そのため、被害者請求による申請が理想ですが、手続に必要な書類や資料を用意するだけでも手間がかかるため、手続のハードルが高いといえます。
弁護士であれば、適切な等級に認定されるために必要な注意点等を把握しており、スムーズに手続を行うことができます。
認定される等級によって請求できる示談金の金額が大きく変動するため、弁護士の力を借りることによって適切な賠償金を受け取れる可能性を高めることが可能です。
(3)適切な過失割合の立証を行うことができる
弁護士であれば、加害者側に対して適切な過失割合を立証することができます。
過失割合は、最終的に受け取ることができる示談金の額に大きな影響を与えます。
被害者側に高い過失が認められてしまうと、その分だけ受け取ることができる示談金が減額されてしまうのです。
特に加害者側の保険会社は支払う示談金額を低く抑えるために被害者の過失を高く見積もって示談案を提示することがあります。
適切な過失割合を立証するためには、客観的な証拠が求められ、立証に必要な資料等を不足なく揃えなければなりません。
しかし、どのような証拠があれば適切な過失割合を証明できるのかは、専門知識や実務経験がなければ判断が難しいです。
弁護士は交渉のエキスパートであり、適切な過失割合を立証するためにどのような証拠が必要か熟知しており、効率よく準備を進めることが可能です。
(4)最終的に受け取ることができる示談金の増額が期待できる
弁護士に示談交渉を依頼することで、受け取ることができる示談金の増額が期待できます。
先述したように示談金の算定基準は3つあり、弁護士が示談交渉を担当することで、最も高額な示談金が算出されやすい裁判所基準を採用することが可能です。
これに対して、被害者ご自身で示談交渉を行う場合は、自賠責基準もしくは任意保険基準で算出された金額をベースに交渉を行うことになります。
自賠責基準や任意保険基準と裁判所基準を比べると、算出できる金額に大きな差が生じるため、示談金を増額させたい方は弁護士に示談交渉を依頼することが大切です。
まとめ
本記事では、交通事故で頭痛が生じる原因や法的対処法応の流れ、示談金の項目等について解説しました。
交通事故によって頭痛が生じた場合は、直ちに専門の医療機関を受診し、完治もしくは症状固定となるまで適切な頻度で治療を行い、示談交渉に臨むことが大切です。
もし、症状固定の診断を受けた場合は、示談交渉が始まる前に後遺障害等級の認定申請を行うことも検討しましょう。
このように、交通事故の示談交渉では、考慮すべきポイントが多岐にわたります。
専門知識や実務経験がない状態で、被害者ご自身で示談交渉を行う場合は、交渉が難航する可能性があります。
そのため、示談交渉を進めることに不安や疑問がある場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、事故による怪我の治療や示談交渉でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
交通事故で
こんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、保険会社・相手方とどんな風に対応すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を受けたいけど、後遺障害認定申請や示談交渉などさっぱりわからない・・・

事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。