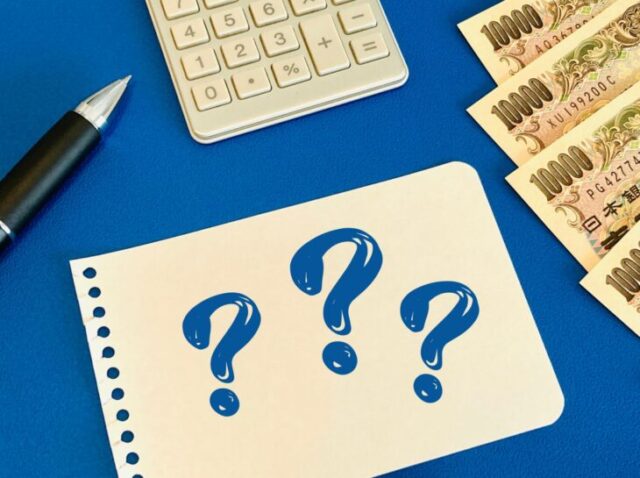交通事故の示談金を計算する方法とは?適切な示談金を請求するためのポイント

執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「交通事故の示談金はどうやって計算できるのか」
「適切な示談金を請求するために気をつけることは何なのか」
交通事故の被害に遭われた方の中には、どのくらいの示談金を請求できるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
示談金とは、交通事故によって発生した損害に対する賠償金のことで、様々な項目が含まれています。
交通事故によって発生する損害のうち、一部の損害項目については算定基準を用いて計算して金額を算出するものもあります。
本記事では、交通事故の示談金を計算する方法や適切な示談金を請求するためのポイント等について解説します。
- 交通事故の示談金の中でも、傷害(入通院)慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料については、算定基準を用いて算出することができる
- 算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあり、裁判所基準が最も高額な金額が算出されやすい
- 加害者側の保険会社が提示する示談金は必ずしも適正な金額とはいえないため、弁護士に相談の上で増額の余地がないか説明を受けることがおすすめ
1.交通事故の示談金を計算する方法

示談金とは、交通事故によって生じた損害に対する賠償金のことです。
具体的な金額は、まず、加害者側との交渉を決めることになり、示談交渉では金額に折り合いがつかなかった場合、最終的には裁判所が判断することとなります。
金額を決める際の基準となるのが後述する算定基準です。
賠償金の総額は各損害の合計額によって決まります。
損害項目には主に以下のようなものがあります。
- 傷害に関する項目(治療費、休業損害、通院交通費、傷害慰謝料など)
- 物損に関する項目(修理費、車両時価額、買替諸費用、代車料、休車損など)
- 後遺障害に関する項目(後遺障害慰謝料、逸失利益など)
- 死亡に関する項目(死亡慰謝料、葬祭費など)
この中でも、怪我の治療費や物損に関する項目などは、交通事故と因果関係がある限り、発生した実費が損害となります。
また、以下のような損害項目には、算定するための基準があり、これに従って金額が決められます。
- 傷害(入通院)慰謝料
- 休業損害
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
以上の損害項目の算定基準には、以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準
各損害項目を算定基準ごとにご紹介します。
(1)自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険から支払われる保険金を算定する基準です。
自賠責保険は交通事故の被害者に対して、迅速に最低限度の補償を行うことを目的とした制度であるため、自賠責基準は3つの算定基準の中では最も低額な水準となっています。
また、傷害部分(治療費、休業損害、通院交通費、傷害慰謝料など)について支払われる金額には120万円の上限があることにも注意が必要です。
そのため、傷害部分120万円を超過した分など、他の基準との差額については別途加害者側に対して請求を行うことになります。
#1:傷害(入通院)慰謝料
傷害(入通院)慰謝料は、怪我によって生じた精神的苦痛を補償するものです。
自賠責基準では、以下の算定式に基づいて算出されます。
- 4,300円×対象日数
ここでいう対象日数は、治療期間と、実際の治療日数×2のいずれか短い方です。
たとえば、治療期間が60日で治療日数が20日の場合は、治療日数×2の40日の方が短いため、対象日数は40日となります。
具体的な日数の計算方法やケース別の相場については、以下の記事もあわせてご覧ください。
#2:休業損害
休業損害は、交通事故の怪我や治療によって仕事を休まざるを得なくなったことによる収入の減少に対する補償です。
自賠責基準では、以下の算定式に基づいて計算されます。
- 6,100円×休業日数
被害者の職業などに関わらず、一律にこのような算定式が設けられているため、計算を行いやすい点に特徴があります。
ただし、資料を提出することにより、実際の減収が1日6,100円を超えることを証明できれば、1日1万9000円を限度に損害が認められる場合があります。
自賠責基準を用いた計算のポイントや注意点については、以下の記事も参考になるので、あわせてご参照ください。
#3:後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
後述する後遺障害等級の認定を受けることで、認定された等級に応じて受け取ることができます。
金額は等級ごとに定められており、1つ等級が違うだけで請求できる金額に大きな差が生じるようになっています。
等級ごとの具体的な金額については、以下の記事をご参照ください。
#4:死亡慰謝料
死亡慰謝料は、事故によって被害者が亡くなったことによる精神的苦痛に対する補償で、被害者本人のものと遺族固有のものの2つがあります。
このうち、被害者本人の死亡慰謝料は400万円と定められています。
遺族固有の慰謝料については、請求権者の人数によって異なります。
具体的な算定方法や被害者が死亡した場合に受け取ることができるその他の賠償項目については、以下の記事もご参照ください。
(2)任意保険基準
任意保険基準は、任意保険会社が用いる算定基準です。
加害者側の保険会社が示談金の提示を行う場合には、この基準に基づいて算出されています。
算定方法の詳細は非公開となっており、これに基づく金額を正確に算定することはできません。
ただし、実際に任意保険会社から提示される金額は、自賠責基準と同程度かやや上回る金額であることがほとんどです。
(3)裁判所基準
裁判所基準は、裁判所が使用している算定基準であり、3つの算定基準の中では、最も高額な金額が算出されやすくなっています。
なお、被害者本人が任意保険会社と裁判所基準での支払を求めて交渉しても、応じてもらえることは少なく、ほとんどの場合は弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
#1:傷害(入通院)慰謝料
裁判所基準では、一般に、骨折などの重傷と、むちうちや打撲などの軽傷で異なる基準が用いられます。
東京地方裁判所などが用いている「民事交通事故訴訟損害賠償基準」(通称「赤い本」)では、重傷の場合と軽傷の場合で異なる算定表を用いて区別しています。
具体的な算定表については、以下の記事をご参照ください。
なお、裁判所によっては別の基準を用いることがあるので注意が必要です。
#2:休業損害
自賠責基準とは異なり、職業(給与所得者、自営業、家事従事者など)ごとに基礎収入の考え方が異なります。
職業ごとに金額を計算できるため、自賠責基準よりも、実収入に近い金額が認められやすいといえるでしょう。
詳細な金額を知りたい場合は、弁護士に相談して見通しを確認するのがおすすめです。
なお、具体的な計算方法や注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
#3:後遺障害慰謝料
裁判所基準でも、等級に応じて受け取ることができる金額が定められています。
自賠責基準と比較すると、その差は最低でも数十万円、高い等級の場合には1000万円以上になることもあるため、十分な賠償を受けるためには裁判所基準に基づいた算定を行うことが重要です。
具体的な相場や請求のポイントについては以下の記事も参考になるので、あわせてご参照ください。
#4:死亡慰謝料
裁判所基準では、被害者本人のものと遺族固有のものが合算された金額が定められています。
この点、被害者本人のものと遺族固有のものを分けて算出する自賠責基準と異なっています。
さらに、その金額は、亡くなった人が家庭内でどのような立場であったかによって変動するようになっており、収入の大部分を担っている一家の支柱だと2800万円、そのほかだと最低で2000万円というのが基準額です。
死亡慰謝料も裁判所基準と自賠責基準では大きく金額が変動しますし、交通事故の態様などによって増額が可能な場合もありますので、こちらも弁護士に相談の上で示談交渉を依頼するのがおすすめです。
具体的な相場や請求のポイントについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
2.示談金を受け取るまでの流れ

事故の発生から示談金を受け取るまでの流れはある程度決まっています。
主な流れは以下のとおりです。
- 怪我の治療
- 後遺障害等級の認定申請
- 示談交渉
- 示談成立・示談金の受領
順にご説明します。
なお、以下の記事もご参照ください。
(1)怪我の治療
事故によって怪我をしたら、まずは治療に専念しましょう。
治療期間は、怪我が完治するか、または症状固定の診断を受けるまでの期間となります。
症状固定とは、治療を継続しても改善が見込めない状態のことで、その診断は、基本的には主治医が行います。
もっとも、もし症状固定時期の争いになった場合には、最終的には裁判所の判断で決まります。
なお、症状固定の意義については以下の記事で詳しく解説しています。
(2)後遺障害等級の認定申請
怪我が完治に至らず、症状固定の診断を受けた場合は、残った症状の程度によっては後遺障害等級の認定を受けられる可能性がありますので、その申請を検討することになります。
後遺障害等級の認定申請は、加害者側の保険会社に申請をしてもらう事前認定と被害者本人が申請を行う被害者請求があります。
適切な等級の認定を受けるためには、提出資料の内容をしっかり確認することができる被害者請求で行うのがおすすめです。
被害者請求による申請のメリットや手続の流れについては、以下の記事もあわせてご参照ください。
また、手続に必要な書類については、以下の記事も参考になります。
(3)示談交渉
治療が完治、もしくは後遺障害等級の認定を受けたら示談交渉を行います。
示談交渉では、怪我の治療経過や、事故状況から被害者にも過失が認められる場合にはその過失割合などから示談金の金額を話し合うのが一般的です。
この際、どの基準を採用するかによって示談金の金額が変動するので、弁護士に相談して裁判所基準を採用することをおすすめします。
また、示談交渉における過失割合の意義については、以下の記事で詳しく解説しています。
(4)示談成立・示談金の受領
示談交渉がまとまったら示談書を作成し、示談を成立させます。
加害者側の任意保険会社との示談の場合、示談の成立後、1週間から2週間くらいで指定口座に振込みが行われます。
加害者本人との示談の場合には、支払の期日も示談の中で決めることになります。
なお、示談書の記載内容や作成する際のポイントなどについては、以下の記事もご参照ください。
3.適正な示談金を請求するためのポイント

適正な示談金を請求するうえで、いくつか気をつけるポイントがあります。
主なポイントは以下のとおりです。
- 加害者側の主張を鵜呑みにしない
- 客観的な証拠を揃える
- 弁護士に示談交渉を依頼する
順にご説明します。
(1)加害者側の主張を鵜呑みにしない
加害者側の主張を鵜呑みにしないことが大切です。
特に加害者側の保険会社は、支払う賠償金の金額を抑えるために、例えば被害者の過失割合を高めに主張する形で示談案を提示することがあります。
加害者側の主張が必ず正しいものとは限らないので、安易に応じないことが重要です。
相手の提案に応じて示談が一度成立してしまうと、後から撤回することができなくなってしまうため、提案された示談内容が適切か見直すようにしましょう。
また、少しでも疑問や不安がある場合には、示談案に応じる前に弁護士に相談し、内容について確認を受けることが重要です。
(2)客観的な証拠を揃える
示談交渉に移る前に、客観的な証拠を揃えましょう。
例えば、過失割合について有利になるように主張するとしても、客観的な証拠がなければそれが認められることはありません。
証拠をもとに立証しなければ、加害者側を納得させることができませんし、訴訟となった場合にも裁判所は証拠がなければ主張を取り上げてくれません。
ドライブレコーダーや現場周辺の監視カメラの映像、目撃者の証言など、証拠として活かせそうなものは用意しておきましょう。
(3)弁護士に示談交渉を依頼する
適正な示談金を獲得するためには、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に示談交渉を依頼することで、加害者側の保険会社と対等に交渉を進めることができます。
また、弁護士は被害者に有利になるように交渉を進め、裁判所基準で算定した賠償金で交渉を行うこともできるので、最終的に受け取ることができる示談金の増額も期待できます。
まとめ
交通事故の示談金の一部については、自賠責基準や裁判所基準を用いてご自身で計算することも可能です。
もっとも、過失割合などによっても金額は変動するため、正確な金額を知りたい場合には、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
特に交通事故の対応に慣れた弁護士であれば、加害者側に請求できる損害項目を漏らすことなく算定することが可能です。
また、最も高額な水準である裁判所基準を用いて示談金の交渉を行うこともできるため、適正な示談金を受け取れる可能性が高まります。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けているので、示談金についてご不明な点がある方はお気軽にご相談ください。
交通事故で
こんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、保険会社・相手方とどんな風に対応すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を受けたいけど、後遺障害認定申請や示談交渉などさっぱりわからない・・・

事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。