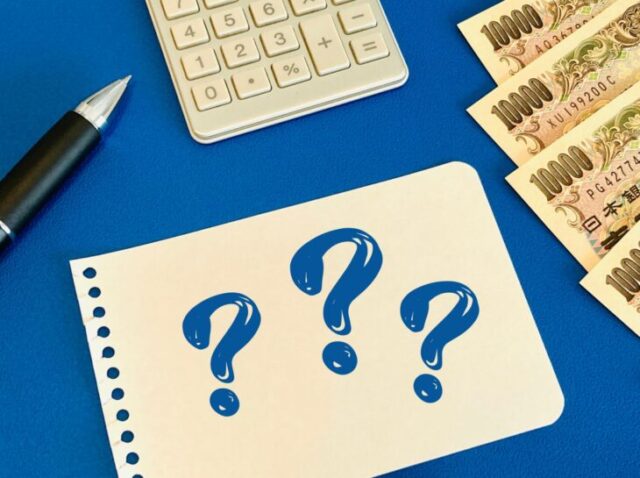交通事故の診断書とは?作成してもらわないデメリットについても解説

執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

「交通事故に遭ったが、診断書を書いてもらわないといけないのか」
「診断書を作成してもらわないとどのような不利益が生じるのか知りたい」
交通事故の被害者の方の中には、怪我の診断書について、このような疑問をお持ちの方もいると思います。
交通事故によって発生した損害については、加害者側に対して賠償金の請求を行い、受け取ることが可能です。
特に事故によって怪我を負った場合には、早期に医療機関を受診し、適切な治療を受けるとともに、怪我について診断書を作成してもらうことが重要です。
診断書は、加害者側の保険会社に対して保険金を請求するために必要となるほか、示談交渉をスムーズに進めるためにも重要な意義を持ちます。
本記事では、交通事故に遭った際に必要になる診断書や診断書を作成しないデメリット等について解説します。
- 交通事故に遭った場合には、速やかに医療機関を受診し、医師に診断書を作成してもらうことで、事故と怪我との因果関係を証明することができる
- 交通事故で作成が必要な診断書には、警察に提出する診断書、加害者側の保険会社に提出する診断書、後遺障害診断書の3つがある
- 適正な賠償を受けるためにも、診断書は適切なタイミングで作成してもらうことが大切
1.交通事故に遭った際に必要となる診断書

交通事故に遭って怪我を負った場合、医療機関を受診して治療を受けることで、治療に関する費用などの損害について、賠償金として受け取ることができます。
怪我をした場合の損害の主な項目は、以下のとおりです。
- 治療費
- 傷害(入通院)慰謝料
- 入院雑費
- 通院交通費
- 休業損害
もっとも、これらの損害項目を賠償金として受け取るためには、交通事故によって怪我を負ったということを証明しなければなりません。
そのような場合に、事故と怪我の因果関係を証明するために重要なのが、医師が作成する診断書です。
交通事故に遭った場合に必要となる診断書は、提出先によって果たす役割が異なり、以下のようなものがあります。
- 警察に提出する診断書
- 加害者側の保険会社に提出する診断書
- 後遺障害診断書
それぞれについて、ご説明します。
(1)警察に提出する診断書
警察に対して提出する診断書は、人身事故として届出を行う際に必要です。
当事者に明らかな怪我がない場合には、警察は原則として物損事故(物件事故)として処理を行います。
物損事故とは、当事者に怪我すなわち人的損害が発生していない事故のことです。
これに対して、怪我が生じている場合には、人身事故として処理がされ、事故状況などをまとめた実況見分調書という書類が作成されるのです。
警察に対して提出する診断書には、以下の項目について記載してもらう必要があります。
- 傷病名
- 全治までの期間
警察へ提出する診断書は、あくまで怪我と事故との間に因果関係があるかどうかを証明するための書類であり、記載項目はそれほど多くありません。
提出期限などは特に定められていないものの、事故から時間が経過すればするほど怪我と事故との因果関係を疑われることもあるため、事故発生日から10日以内に提出することでスムーズな処理がなされる可能性が高いです。
そのため、事故から時間が経過して痛みや痺れなどの症状が現れた場合には、直ちに医療機関を受診し、初診時に診断書を作成してもらうことが重要といえます。
警察に診断書を提出して受理されれば、事故から日数が経過していても人身事故として処理がなされ、実況見分調書を作成してもらうことが可能です。
なお、警察へ提出するための診断書の作成費用については、加害者側から支払ってもらえるケースが多いです。
人身事故と物損事故の違いについては、以下の記事もご覧ください。
また、人身事故に切り替える手続の流れや切り替えを行わないことによるデメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)加害者側の保険会社に提出する診断書
怪我の治療に関する費用は、加害者側に請求を行うことになるため、その際にも医師が作成する診断書が必要です。
なお、治療費を受け取る方法には以下の2つの方法があり、どちらに対して請求を行うかによって提出先が異なります。
- 一括対応
- 被害者請求
順に見ていきましょう。
#1:一括対応
加害者が任意保険に加入している場合には、加害者側の保険会社が直接病院等に対して治療費を支払う「一括対応」が行われるのが一般的です。
そのため、一括対応を受けることができる場合には、被害者は病院で治療費を自己負担することなく怪我の治療を行うことができます。
一括対応が行われる場合には、加害者側の保険会社が診断書を直接病院から取得するため、被害者が診断書を用意する必要はありません。
ただし、保険会社が医療機関から被害者の医療情報を取得するための「同意書」の作成を求められることになりますので、提出するようにしましょう。
一括対応が行われる場合、診断書の作成費用も加害者側の保険会社が負担することになるため、被害者が作成費用を用意する必要もないことを押さえておきましょう。
#2:被害者請求
加害者が任意保険に加入していない場合や任意保険に加入しているものの過失割合争いなどで一括対応がなされない場合には、加害者側の保険会社が直接治療費を支払ってはくれません。
そのような場合には、加害者側の自賠責保険に対して保険金の請求を行う「被害者請求」を行うことによって、治療費などの費用を回収することができます。
被害者請求を行う場合には、自賠責保険が指定する診断書の様式に従って作成を行う必要があります。
病院が書式を備えていることが多いですが、もしも病院がもっていない場合には自賠責保険から書式を取り付けることもできます。
被害者請求の場合には、治療費や診断書の作成費用は被害者が一旦立て替えることになります。
もっとも、保険金の請求を行った後に、治療費などの支払と合わせて診断書の作成費用についても補償を受けることが可能です。
なお、被害者請求の手続を行う際には、診断書のほかに診療報酬明細書も提出する必要があるため、破棄せずに保管しておきましょう。
被害者請求の流れや手続を行う際の注意点などについては、以下の記事もご覧ください。
(3)後遺障害診断書
後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定申請を行う際に必要となる診断書です。
怪我の治療を行ったものの、完治せずに症状固定となった時点で医師に作成してもらうことになります。
症状固定とは、一定期間にわたって怪我の治療を行った後に症状が一進一退となり、これ以上治療を続けても医学的に改善しない状態のことです。
症状固定の診断を受けた時点で残存した症状を後遺症といい、これが自賠法が定める後遺障害として認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という損害項目についても請求が認められます。
なお、怪我が完治して後遺症が残らなかった場合には、後遺障害は認定されませんから申請する必要はありません。
したがって、後遺障害診断書は、後遺症が残った場合にのみ作成を依頼することを検討することになります。
後遺障害の意義や等級認定の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
また、後遺障害診断書の記載項目や作成してもらう際のポイントについては、以下の記事もあわせてご参照ください。
2.診断書を作成してもらわないことによるデメリット
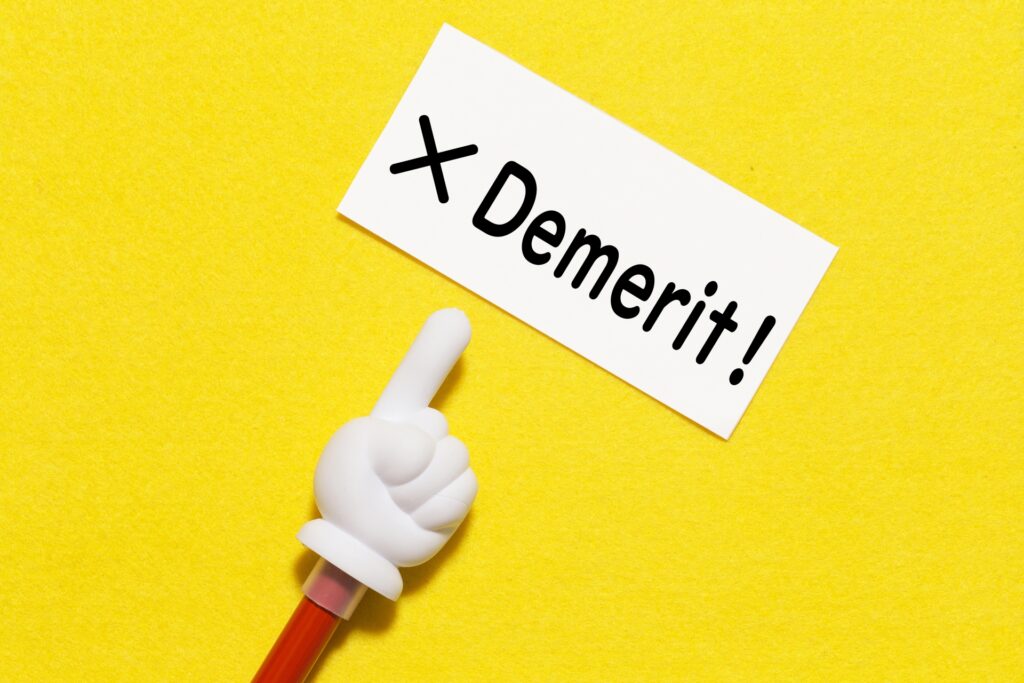
交通事故に遭った際に作成してもらう診断書は、主に3つあると述べましたが、実はこれらの書類を作成してもらわなければ、いくつかのデメリットが生じることがあります。
主なデメリットは以下のとおりです。
- 実況見分調書が作成されない
- 賠償金を受け取ることができない
- 後遺障害等級の認定を受けることができない
順にご説明します。
(1)実況見分調書が作成されない
先に述べましたが、警察へ提出する診断書は、人身事故への切り替えを行う際に必要となるため、診断書を作成してもらわなければ、人身事故への切り替えを行うことができません。
そして、人身事故への切り替えができない場合には、実況見分調書が作成されないというデメリットがあります。
実況見分調書には、事故態様や事故当時の路面状況などについて詳細な記載がされるため、示談交渉で過失割合を決める際に活用することが可能です。
そのため、事故態様や過失割合に争いが生じており、かつ当事者の双方がドライブレコーダーを搭載していなかったり、事故現場に防犯カメラがなかったりした場合には、実況見分調書が証拠として重要な意味を持ちます。
つまり、事故態様について客観的に証明できる証拠や資料が不足している場合には、人身事故への切り替えを行うことで、後の示談交渉を有利に進めることにもつながる場合があるのです。
しかし、警察へ診断書を提出しなければ、実況見分調書が作成されません。
したがって、事故状況について当事者双方の意見が食い違っている場合や過失割合で示談交渉が難航する可能性がある場合には、診断書を作成してもらう必要があるでしょう。
(2)賠償金を受け取ることができない
交通事故によって発生した怪我について診断書を作成してもらわなければ、受傷したことを証明できず、賠償を受けられない可能性があります。
事故の直後に目立った外傷や自覚症状がなかった場合にも、時間の経過とともに痛みや痺れなどの症状が現れることも珍しくありません。
このような場合、直ちに整形外科などの医療機関を受診し、診断を受けることが大切です。
「本当はずっと痛かったんだ」と主張をしても、診断がされていなければ受傷の事実が認められることはありません。
そのため、事故によって怪我を負ったことを客観的に示すものとして診断書が重要な意味を持つのです。
また、加害者側の自賠責保険に被害者請求を行う場合にも、診断書の作成をしてもらい、提出することが必要です。
なお、事故直後から加害者側の任意保険会社が一括対応を行う場合には、その保険会社が診断書の取り寄せを行います。
このような場合には、被害者が自身で診断書の作成を医師に依頼しなくても、治療費の支払などを受けることができるため、診断書の作成を被害者が依頼する必要はないといえるでしょう。
(3)後遺障害等級の認定を受けることができない
後遺障害診断書の作成をしてもらわなければ、後遺障害等級の認定を受けることもできません。
等級認定の審査は、後遺障害診断書に記載されている内容をもとに行われるため、診断書の提出をしていなければ、そもそも認定の対象外となります。
後遺障害等級の認定を受けることができなければ、加害者側に対して後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することもできなくなります。
3.診断書の作成・提出に関する注意点

怪我について診断書を作成してもらうことは、適正な賠償金を獲得するためにも重要といえます。
また、保険金の請求などの手続上で診断書の作成・提出が求められることもあるため、適切なタイミングで診断書の作成を依頼しましょう。
なお、診断書の作成・提出は、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
具体的には、以下のとおりです。
- 医師に作成してもらう
- なるべく早期に作成を依頼する
- 必ず原本を提出する
順に見ていきましょう。
(1)医師に作成してもらう
診断書は医師だけが作成できるものです。
交通事故の怪我の治療のために、整骨院や接骨院に通うケースも見られます。
しかし、整骨院や接骨院の先生は柔道整復師という、医師とは異なる資格なので、診断書を作成することができない点に注意しましょう。
軽い打撲やむちうちの場合でも、必ずまずは整形外科などの医療機関を受診して診断書を作成してもらうことが重要です。
(2)なるべく早期に作成を依頼する
交通事故による怪我の診断書は、具体的な提出期限が決まっているわけではありませんが、なるべく早期に作成を依頼しましょう。
特に、警察提出用の診断書と後遺障害診断書は、あまり日をおかないで作成してもらう方が良いでしょう。
警察提出用の診断書は、作成に時間がかかってしまうと、警察側が受理に難色を示す可能性があります。
というのも、多くの場合、診断書を受理した後に実況見分を行うため、事故から時間が経ちすぎてしまっていると、実況見分の信用性が下がってしまい、刑事事件の処理がうまく進まなくなってしまう可能性があるからです。
また、後遺障害診断書は、症状固定時点の状態を記載してもらう必要がありますが、もしも症状固定から数か月経ってから作成を依頼した場合、それが正しい内容と言えない可能性が出て来ます。
そのため、医師もあまりに時間が経過した場合には作成に難色を示すことがあります。
診断書は、作成して終わりではなく、これを利用して手続を進めたり立証活動を行ったりするためのものなので、適切なタイミングで作成するようにしましょう。
(3)必ず原本を提出する
診断書の提出を行う際には、必ず原本を用いることが大切です。
コピーを提出しても、認められることはほとんどありません。
もっとも、作成費用については加害者側の保険会社に支払ってもらえるため、作成費用の負担を考えずに必要な枚数の作成をしてもらいましょう。
なお、後遺障害診断書については、等級非該当となった場合には保険会社に作成費用を支払ってはもらえず、自己負担となってしまうことに注意が必要です。
4.交通事故の対応について弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故の対応は、専門的な知識が必要になる場合が多く、被害者ご自身で解決することには困難が伴います。
怪我の治療を行いながら、保険会社や警察への対応や手続をスムーズに進めることは、精神的にも身体的にも負担となることが考えられます。
そのため、交通事故の対応に不安や悩みがある場合には、専門家である弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士に相談・依頼するメリットには、以下のようなものがあります。
- 適正な賠償を受けるための治療のポイントについて説明を受けることができる
- 後遺障害診断書の内容のチェックを受けることができる
- 保険会社との対応や示談交渉を一任できる
- 示談金の増額が期待できる
順にご説明します。
(1)適正な賠償を受けるための治療のポイントについて説明を受けることができる
弁護士に相談することで、適正な賠償金を受け取るために治療で注意すべきポイントについてアドバイスを受けることができます。
怪我に関する賠償金の中でも、傷害(入通院)慰謝料は、治療の頻度や期間によって金額が変動します。
そのため、治療の頻度や期間が短い場合には、保険会社から怪我の程度が軽かったと評価されて、十分な傷害(入通院)慰謝料が認められない可能性があります。
他方で、治療の頻度が高かったり治療期間が長期にわたっていればよいかというと、今度は過剰診療を疑われて一括対応を打ち切られるリスクが高まります。
そのため、事故の大きさや怪我の状況に合わせた治療の仕方を考える必要があります。
治療が始まった時点で弁護士に相談することで、適正な賠償金を受け取るために注意すべきポイントについて、あらかじめ説明やアドバイスを受けることができます。
(2)後遺障害診断書の内容のチェックを受けることができる
後遺障害診断書を提出する前に、弁護士に記載内容のチェックを受けることができます。
後遺障害認定の審査においては、後遺障害診断書の記載内容が大きく影響を与えるため、適切な等級認定を受けるためには、何がどのように記載されているかがとても重要です。
もっとも、等級認定の可能性を高めるための記載となっているかどうかは、専門知識や実務経験に基づいて判断されるものであり、被害者ご自身でチェックを行うことは難しい場合がほとんどです。
交通事故の対応に慣れた弁護士は、適切な等級の認定を受けるためのポイントについて熟知しています。
医師に作成してもらった後遺障害診断書の内容のチェックを受けることで、残存する症状に合わせた適切な等級認定の可能性を高めることが可能です。
(3)保険会社との対応や示談交渉を一任できる
弁護士に依頼した場合、アドバイスだけではなく、保険会社との対応や示談交渉をそのまま一任することができます。
被害者自身が保険会社と交渉することも可能ですが、加害者側の立場の保険会社と交渉することは、大きな負担となる可能性が高いです。
また、交渉に慣れている保険会社を相手に、専門的な知識を持たない状態で有利に交渉を進めることは困難といえます。
弁護士に依頼すれば、交渉に関するストレスから開放されるだけでなく、有利な内容で示談がまとまる可能性を高めることができます。
(4)示談金の増額が期待できる
弁護士に示談交渉を依頼することで、示談金の増額が期待できます。
示談金の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つで、弁護士が交渉に介入することで、最も高額な示談金が算出されやすい裁判所基準を採用することが可能です。
被害者ご自身で交渉を行う場合でも、裁判所基準を用いて示談金の請求を行うこともできますが、そのような場合には保険会社は裁判所基準での支払に応じることはほとんどありません。
そのため、被害者ご自身で示談交渉を行う場合は、低額な示談金しか受け取ることができないことがほとんどです。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼することで、保険会社は裁判所基準を拒否すれば裁判を起こされてしまうと考えるので、裁判所基準での支払に応じるようになります。
これによって、最終的に受け取ることができる示談金の増額を期待することができます。
適正な賠償金を受け取るためには、弁護士に示談交渉を依頼することが大切です。
まとめ
交通事故に遭った方は、速やかに医療機関を受診し、医師の診断を受けるようにしましょう。
そうすることで、必要に応じて診断書を作成してもらうことができるようになります。
診断書は、実況見分調書を作成するためや、怪我や後遺障害の賠償を受けるためなど、いろいろな場面で必要になってきます。
適正な賠償を受けるためにも、受診後はなるべく早期に医師に診断書を作成してもらい、必要な手続を進めるようにしましょう。
もっとも、交通事故の直後はさまざまな対応を行う必要があり、知識や経験がなければ、どのような対応を行うべきか判断することは難しいといえます。
そのような場合には、なるべく早期に弁護士に相談し、示談交渉までの見通しなどについて説明を受けることがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、交通事故の被害に遭われた方で、対応についてお困りの方はお気軽にご相談ください。
交通事故で
こんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、保険会社・相手方とどんな風に対応すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を受けたいけど、後遺障害認定申請や示談交渉などさっぱりわからない・・・

事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。