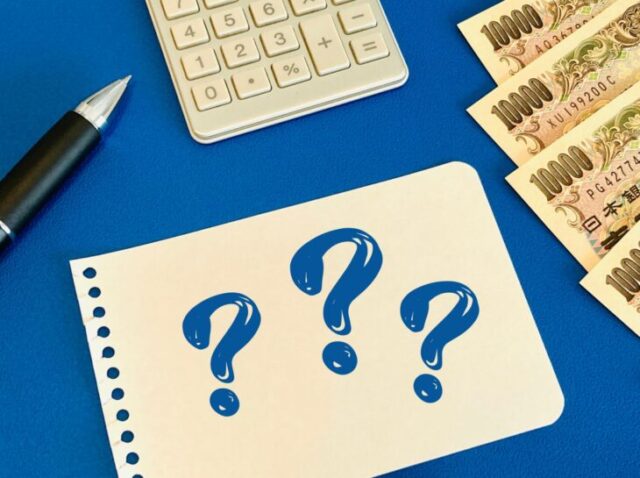交通事故で全身打撲を負ったときの対応とは?賠償金や後遺障害が残ったときの対応を解説

執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「交通事故で全身打撲を負ったときはどう対応したらいいのか」
「交通事故の全身打撲はどのくらいの賠償金を請求できるのか」
交通事故によって全身打撲を負った方の中には、どのように対応すべきか気になっている方もいるかと思います。
全身打撲は、体に強い衝撃が加わることで生じます。
打撲と聞くと、交通事故の怪我の中では比較的軽傷と思われるかもしれません。
しかし、全身打撲との診断を受けた場合、深刻な傷害を同時に負っていることに気が付かないこともあるため、注意が必要です。
本記事では、交通事故で全身打撲を負ったときの対応等について解説します。
- 全身打撲は、交通事故による強い衝撃が体の全体に加わることで、皮膚の下の組織が損傷を受けている状態をいう
- 目立った外傷などがない場合にも、骨や内臓に損傷が生じている可能性があるため、直ちに専門の医療機関を受診することが大切
- 手足の痛みや痺れなどの症状が残った場合には、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を追加で受け取ることができる
1.交通事故で全身打撲を負ったときにすべきこと

全身打撲とは、体の全身に打撲を負った状態、つまり強い衝撃が体の全体に加わることで、皮膚の下の組織が損傷している状態を意味します。
主に全身の痛みや内出血を伴うことが多く、その影響が体の全身に及んでいる可能性がある点が特徴です。
一見すると、目立った外傷や症状が現れていない場合でも、全身に衝撃が加わったことにより、骨折、内臓の損傷、脳内出血などの深刻な傷害が同時に生じている可能性もあります。
そのため、交通事故によって全身に大きな衝撃を受けたときには、直ちに整形外科などを受診することが大切です。
また、適正な賠償金を獲得するためにも、以下の点を押さえておきましょう。
- 医師の指示に従って完治を目指して治療する
- 症状を医師に具体的に説明する
- 後遺症が残ったら後遺障害等級認定の申請を検討する
順にご説明します。
(1)医師の指示に従って完治を目指して治療する
医師の指示に従って、完治を目指して適切な頻度で治療を行うことが大切です。
通院・入院して治療を受けなければ、加害者側から治療費や傷害慰謝料の支払を受けられなくなってしまいます。
なお、加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社が治療期間中、治療費を直接医療機関に支払う対応(一括対応)が行われることが一般的です。
一括対応は、あくまで保険会社が事故間もない被害者の負担を軽減するためにサービスで行うことなので、通院頻度が少なすぎたり多すぎたりすると、怪我の程度が軽い、または過剰診療を疑われて一括対応を打ち切られてしまうリスクがあります。
そのため、必ず医師の指示を守りながら適切な頻度で通院・治療を行うことが最も重要です。
なお、通院頻度が賠償に与える影響については、以下の記事もご参照ください。
(2)症状を医師に具体的に説明する
治療を始める段階で、怪我の症状を医師に具体的に説明しましょう。
全身打撲の場合、目立った外傷などがなければ、レントゲン検査やMRI検査などが行われない場合があります。
全身打撲は、骨折、内臓の損傷、脳内出血などが同時に生じている可能性がありますが、外から見て目立った外傷が見つけられないからと本来必要なはずのレントゲン検査やMRI検査などを受けられず、これによって以上のような別の傷害の発見が遅れてしまう可能性があります。
検査が必要かどうかを医師がしっかり判断できるように、症状を具体的に説明しましょう。
このとき、被害者ご自身にしか分からない自覚症状については、部位、痛みの種類(鈍い痛み、刺すような痛みなど)などを具体的に説明することが重要です。
(3)後遺症が残ったら後遺障害等級認定の申請を検討する
治療を継続したものの、怪我が完治せずに症状固定となった場合には、症状の内容や程度によっては後遺障害等級の認定申請を行うことも検討しましょう。
症状固定とは、治療を行ってもその効果としての改善が見込めないと判断される状態のことです。
この時点で残存している症状がいわゆる後遺症であり、これが自賠法上の後遺障害等級のいずれかに該当すると認定されれば、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を受け取ることができます。
後遺障害等級は、申請により、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という第三者機関が審査・認定を行います。
申請に当たっては、医師が作成する後遺障害診断書という書類が必要になります。
後遺障害が損害賠償上で持つ意義については、以下の記事で解説しています。
また、後遺障害診断書の記載項目や作成してもらう際のポイントについては、以下の記事もご覧ください。
2.交通事故による全身打撲で請求できる賠償金

交通事故による全身打撲で請求できる賠償金の項目がいくつかあります。
主な項目は以下のとおりです。
- 治療費
- 傷害(入通院)慰謝料
- 入通院に関する費用
- 休業損害
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
5と6に関しては、後遺障害等級の認定を受けることで受け取ることができる賠償項目です。
それぞれについて、解説します。
(1)治療費
症状が固定するまでにかかった病院の治療費や整骨院の施術費、薬局の調剤費を、加害者に請求することができます。
加害者が任意保険に加入している場合には、通常、その保険会社が治療費の支払を行う「一括対応」を受けることができます。
そのため、被害者は自己負担を気にすることなく治療を進めることが可能です。
ただし、一括対応が行われた場合には、後の示談交渉において既払金として示談金から治療費が差し引かれることに注意しましょう。
なお、一括対応はあくまで保険会社のサービスであるため、支払を拒否されたり打ち切られたりした場合には、これを強制する法的根拠はありません。
そのような場合には、治療費を一旦被害者ご自身で立て替え、後の示談交渉で加害者側の保険会社に請求し、交渉の結果合意できた場合にはその金額を受け取ることができ、合意ができなければ訴訟を検討することになります。
治療費を立て替える際に利用できる制度や請求する際の注意点などについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
(2)傷害(入通院)慰謝料
傷害(入通院)慰謝料は、交通事故を原因として怪我を負ったことによる精神的な損害に対する補償です。
以下の3つの算定方法があり、どの算定基準を採用するかによって金額が異なります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準
順にご説明します。
なお、傷害(入通院)慰謝料を請求する際のポイントについては、以下の記事も参考になります。
#1:自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険会社が用いる算定基準です。
具体的には、以下の算定式に基づいて算出されます(令和2年4月1日以降に発生した事故の場合)。
- 4,300円×対象日数
また、対象日数は、以下のうちのいずれか短い方が採用される点に注意しましょう。
- 治療開始から、完治または症状固定の日までの全治療期間
- 実際に入通院した日数の2倍
#2:任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険会社が用いる算定基準です。
保険会社が示談案を提示する場合には、この基準を用いて示談金の算定を行っています。
算定内容などの詳細は非公開になっていますが、自賠責基準と同程度か、それをやや上回る程度の水準であることが多いです。
その金額は、次に説明する裁判所基準によって計算した金額よりも低いことがあるので、提示された後は、適切な金額を確認するようにしましょう。
#3:裁判所基準
裁判所基準は、過去の裁判例の集積によって裁判所で確立された基準で、最も高額な金額が産出されやすい水準になっています。
そのため、示談交渉では裁判所基準で交渉することで、賠償金の増額を図ることが可能です。
ただし、被害者自身が裁判所基準で請求をしても、加害者側の任意保険会社が裁判所基準での交渉を受け付けないケースも多いため、裁判所基準を用いるためには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。
まずは、弁護士に相談して、どのくらいの賠償金を受け取ることができる可能性があるのかについて、説明を受けるようにしましょう。
裁判所基準の概要や請求のポイントについては、以下の記事でも解説しています。
(3)入通院に関する費用
入院や通院の際に発生した費用についても補償を受けることができます。
具体的には、入院中の日用雑貨などの雑費や通院交通費などがこれにあたります。
(4)休業損害
休業損害は、事故による怪我の治療で仕事を欠勤、遅刻または早退することを余儀なくされ、それによって収入が減少したことに対する補償です。
その金額は、以下の算定式に従って算出されます。
- 1日あたりの基礎収入×休業日数
基礎収入や休業日数の考え方は、算定基準によって異なることに注意が必要です。
具体的な計算方法やポイントについては、以下の記事もご参照ください。
(5)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺症を負ったことによる精神的な苦痛に対する補償です。
全身打撲では、内出血による神経や血管の圧迫によって、手足の痛みや痺れといった神経症状の後遺症が残存する可能性があります。
このような神経症状が後遺障害として認定されれば、等級に応じて以下のような金額の後遺障害慰謝料を受け取ることが可能です。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判所基準 |
| 12級13号 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円(32万円) | 110万円 |
※()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合
このように、裁判所基準を用いることで、大幅に賠償金が増加することがわかります。
(6)後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、事故による後遺障害によって将来得られるはずだった収入を失ったことに対する補償です。
たとえば、後遺障害によって転職せざるを得なくなり、収入が減った場合は、その損失分を請求できる可能性があります。
ただし、後遺障害を負っても、労働能力が低下せず、問題なく事故前と同じように労働を継続することができる場合は請求することができません。
算定方法や適切な金額を算定するためのポイントについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
3.後遺障害等級認定の申請方法

医師から症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討しましょう。
後遺障害等級認定の申請方法は以下の2つです。
- 事前認定
- 被害者請求
手続の手間はかかるものの、適切な等級の認定申請ができるため、被害者請求で行うのがおすすめです。
それでは、順にご説明します。
(1)事前認定
事前認定は、加害者側の任意保険会社に申請を依頼する方法です。
被害者ご自身で準備すべき書類は医師に作成してもらう後遺障害診断書のみであり、申請に必要なほかの書類の作成や提出をすべて加害者側の保険会社に依頼でき、申請の手間を省くことができます。
もっとも、認定結果を大きく左右する書類を加害者側の保険会社に一任することになり、適切な等級の認定を受けられない可能性があります。
また、手続に必要最低限の書類しか提出されない、後遺障害診断書の記載に誤りがあっても訂正されない、などの理由により、等級非該当となってしまうことも考えられるのです。
したがって、事前認定によって申請を行うかどうかは慎重に決める必要があります。
なお、認定結果が等級非該当になったとしても、認定に対する異議申立てを行うことはできます。
具体的な流れは以下の記事で解説しています。
(2)被害者請求
被害者請求は、被害者自らが自賠責保険会社に対して書類や資料を提出して行う申請方法です。
手続に必要な書類の作成や資料の収集をすべて被害者ご自身で行わなければならないため、事前認定と比較すると申請の手間がかかる点がデメリットといえます。
もっとも、書類の書き方を吟味したり、追加の資料を添付したりするなどの工夫を行うことで、後遺症の症状を具体的に主張することができるため、適切な等級の認定を受けられる可能性が高いです。
また、交通事故の対応に慣れている弁護士であれば、どのような書類や資料を提出すれば等級認定を受けられるかのポイントについて熟知しています。
そのため、交通事故の対応に習熟した弁護士に手続を依頼することで、適切な等級に認定される可能性を高めることができます。
被害者請求の具体的な流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
交通事故によって全身打撲を負った場合、まずは治療に専念し、治療がひと段落ついたら示談交渉を行います。
医師から症状固定の診断を受けた場合は、示談交渉に入る前に、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
後遺障害等級の認定を受けることができれば、受け取ることができる賠償項目が増えるため、賠償金も増額します。
示談交渉や後遺障害等級認定の申請で不安が点がある方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士法人みずきは、これまで数多くの交通事故の問題を解決してきました。
経験豊富な弁護士が親身にお話を伺いますので、交通事故の被害に遭われた方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
交通事故で
こんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、保険会社・相手方とどんな風に対応すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を受けたいけど、後遺障害認定申請や示談交渉などさっぱりわからない・・・

事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。