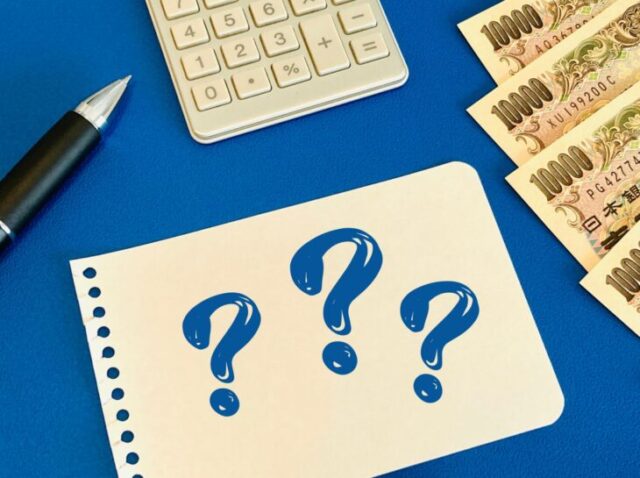交通事故によって退職した場合に休業損害はもらえるのか?休業損害をもらうための条件や必要な書類などについて解説

執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「交通事故に遭って、仕事を退職せざるを得なくなった」
「退職した後も、休業損害ってもらえるの?」
交通事故に遭ってしまい、職場を退職せざるを得なくなったというケースがあります。
被害者の方からすると、事故が原因で退職を余儀なくされたのだから、減ってしまった収入については相手方に賠償してほしいと思うのは当然のことです。
もっとも、退職した場合にも休業損害を受け取ることができるのか、と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
「休業損害」とは、交通事故による怪我の治療・療養のため、休業を余儀なくされた場合に受けた損失のことをいいます。
「休業」というと、職場に残りつつ仕事をお休みしている場合をイメージするかと思います。
しかし、職場を「退職」した場合であっても、相手方に休業損害を請求できる場合があります。
本記事では、退職後に相手方に休業損害を請求できる場合について、その条件や計算方法、必要書類などについて解説します。
この記事を読んで、交通事故によって退職をした場合に、休業損害を受け取るためのポイントを押さえ、適切な賠償金を獲得するための参考になれば幸いです。
なお、休業損害の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。
- 交通事故による怪我が原因で退職を余儀なくされた場合、条件を満たすことで、退職後も休業損害を受け取ることができるケースがある
- 退職後も休業損害を受け取るためには、退職証明書と医師の診断書が必要となる
- 弁護士に相談することで、退職後に休業損害を受け取ることができるのかどうかについて説明を受けられるほか、手続を依頼することもできる
1.交通事故による退職で休業損害を受け取るための条件

事故による怪我が原因で仕事を退職せざるを得ない場合、退職後も休業損害が認められる可能性があります。
しかし、どのような場合でも認められるわけではありません。
どのような条件が必要か見ていきましょう。
- 怪我と退職との間の因果関係がある
- 職場復帰が困難である
- 会社都合の退職である
- 再就職が困難である
(1)怪我と退職との間の因果関係がある
まず、休業損害を受け取るためには、お仕事を休んだ原因が交通事故であると立証できなければなりません。
事故がなくてもお仕事を休んでいたという場合には、仮に収入が減少したとしても、それは事故のせいとは言えないため、休業損害を受け取ることはできないということです。
同じように、退職の場合も、事故の怪我によって退職することになったという因果関係が必要となります。
元々上司とウマが合わずに辞める予定だった、より待遇の良い会社へ転職することになった、等の理由では事故によって損害を被ったとは認められません。
ですので、退職して休業損害を受け取るためには、あくまで今回の退職が、「交通事故に遭ったせいでやむなく退職することとなってしまった」ということを立証できる必要があります。
(2)職場復帰が困難である
仕事を続けられないほど怪我が重症である場合や、肉体労働に従事していて仕事の継続が困難な場合など、職場に復帰することが困難な場合は、退職後の休業損害が認められる可能性が高いです。
また、交通事故で足を骨折してしまった被害者が、会社に出社するためには、電車に乗ることと階段の上り下りが避けられないことから退職を余儀なくされた場合も同様です。
これらの場合に共通していることは、たとえ仕事を辞めていなくても、職場を休業せざるを得ない状態が続いているということです。
このように、休業していれば損害の賠償を受けられたといえる場合には、退職したからと言って請求ができなくなるのは不合理であり、休業損害として請求できるといえます。
(3)会社都合の退職である
会社に解雇された場合や自主的な退職でない場合にも、退職後の休業損害は認められやすいでしょう。
もっとも、会社としては、従業員を簡単には解雇できないため、退職勧奨がされるなど、自主的な退職を促してくる場合があります。
この場合に自主退職(自己都合退職)をしてしまうと、事故によって退職せざるを得なかったといえるかどうかに疑いが生じやすくなってしまいます。
そのため、あくまで会社都合の退職としてもらうよう、会社に相談するのが良いかと思います。
(4)再就職が困難である
交通事故による怪我が重大であり、再就職が困難な場合にも、退職後の休業損害が認められる可能性があります。
怪我が長引いてすぐに再就職できない場合などがこれに当たります。
この場合、交通事故による怪我が原因で働けない状況にあるため、休業を余儀なくされているといえ、休業損害が認められやすいでしょう。
2.退職後の休業損害の算定方法

休業損害として請求できる金額は、基本的には「基礎収入の日額×休業日数」で計算されます。
具体的なポイントは、以下のとおりです。
- 基礎収入の日額の考え方
- 休業日数の考え方
- 再就職するまでの期間の損害
順にご説明します。
(1)基礎収入の日額の考え方
会社員やアルバイトなどの給与所得者の場合、原則として事故前3か月分の給与額を稼働日数で割った金額が基礎収入の日額となります。
給与額とは、手取りではなくて額面の支給金額(本給+付加給)をいいます。
これらの考え方は、勤務先を退職した場合であっても同じです。
事故が原因で稼働できなくなったのですから、もし会社で稼働していたならば得られたはずの収入を基礎として、休業損害を計算します。
もっとも、完全休業中や退職後は、休業日数を期間でとらえることとなります。
そのため、この場合には、稼働日数ではなく、所定休業日を含めた90日で割って日額を出すこととなります。
(2)休業日数の考え方
休業損害の対象となる休業日数は、基本的には、完治または症状固定までの間に、治療のために仕事を休んだ日数となります。
症状固定とは、これ以上治療しても症状が改善しないと判断された状態をいいます。
もっとも、完全休業や退職後は、実際に働いたであろう日数を算出することが難しい場合も多いため、期間で算定することが多いです。
(3)再就職するまでの期間の損害
休業損害の対象となるのは、原則として怪我の状態から休業が必要であると判断される範囲です。
もっとも、退職した後に、稼働可能な状態にまで怪我が回復しても、すぐに新たな就業先が見つかるとは限りません。
このような場合には、休業の必要性がなくなった後も一定程度の期間について休業補償が認められる可能性があります。
3.退職後の休業損害を受け取るために必要な書類
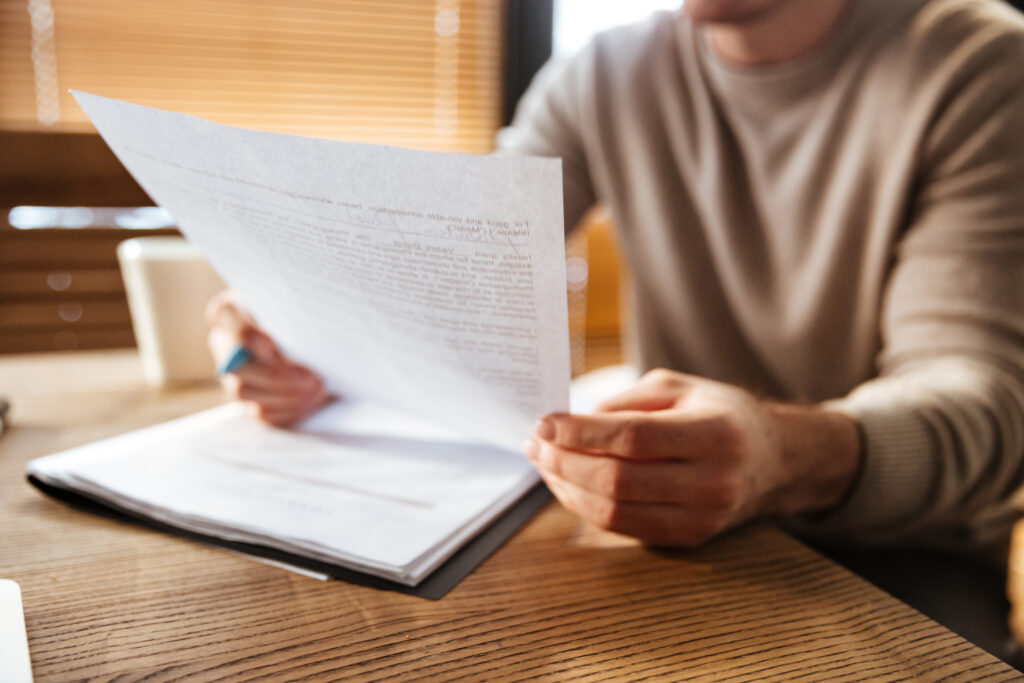
通常、休業損害を請求する際には、勤務先に休業損害証明書という書面を作成してもらうことで、休業の事実及び減収の事実を証明します。
しかし退職後はこれを作成してもらうことはできないため、他の書類を準備する必要があります。
具体的には、以下のものが挙げられます。
- 退職証明書
- 医師の診断書
順に解説します。
(1)退職証明書
退職理由が交通事故の怪我であることを証明するために、会社に退職証明書を書いてもらいましょう。
退職証明書とは、企業が発行する、退職した事実を証明するための書類で、退職した事実や在職中の契約内容、退職の理由などについて記載されています。
もっとも、会社は、退職理由が事故の怪我であるという内容の退職証明書を書くことになかなか応じない可能性があります。
会社から退職勧奨がされた場合でも、従業員が自主的に退職願を出すと、退職の理由の欄に「自主退職(自己都合退職)」と記載される可能性が高くなるので注意が必要です。
あくまで退職願は出さずに、退職勧奨に応じた会社都合退職であることを記載してもらいましょう。
なお、発行時期は、退職後2年以内となっています。
退職から2年が経過すると、会社側には退職証明書を用意する法的義務はなくなるので注意が必要です。
(2)医師の診断書
退職しなければならないほどの怪我を実際に負ったこと、退職した時点で怪我が治っていなかったことを証明するために、医師の診断書も有効な書類です。
多少費用は掛かってしまいますが、勤務先から退職証明書の作成に協力を得られない場合等には、医師に退職時点の診断書を作成してもらうことも検討しましょう。
4.弁護士に相談するメリット

退職後の休業損害は、論点となる部分が多いため、適切に受け取ることができるように、専門家である弁護士に相談するのがよいでしょう。
主なメリットは、以下のとおりです。
- 休業損害を受け取ることができるかについて説明を受けることができる
- 請求に必要な書類や資料の作成・収集のアドバイスを受けることができる
- 示談交渉を依頼することができる
順にご説明します。
(1)休業損害を受け取ることができるかについて説明を受けることができる
これまでご説明した通り、退職後の休業損害が認められるためには、退職の原因が交通事故であるといえる必要があります。
しかし、個々の状況によっても違いますし、専門的な判断を要します。
ご自身の状況で、休業損害が認められる可能性があるのか、退職前にご相談いただくと、その後の見通しを立てやすくなり不安も解消されます。
(2)請求に必要な書類や資料の作成・収集のアドバイスを受けることができる
勤務先から退職証明書を取得すべきであることは上で説明しました。
退職後にしばらくしてからこれを元勤務先に作成依頼をすることが、心理的に抵抗があるという方は少なくありません。
そのため、あらかじめ退職前にどのような書類を準備しておけばいいかの確認ができれば、スムーズに書類の収集をすることができます。
(3)示談交渉を依頼することができる
アドバイスだけでなく、実際に休業損害を計算し、これを相手方に請求するまでを弁護士に依頼することができます。
退職後の休業損害がいつまでの期間認められるのか、どのように計算するのかといった点で相手方保険会社が反論してくることは珍しくありません。
そのため、適切に証拠に基づく主張をして、こちらの請求を認めさせる必要があります。
まとめ
本記事では、交通事故によって退職してしまった場合に休業損害を受け取るための条件や計算方法などについて解説しました。
交通事故の怪我などによって退職した場合であっても、一定のケースでは休業損害を受け取ることができることもあります。
もっとも、退職後の休業損害については、示談交渉で争いとなることが多いです。
適正な賠償金を獲得するためにも、不安や疑問がある場合には、専門家である弁護士に一度相談することをおすすめします。
交通事故で
こんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、保険会社・相手方とどんな風に対応すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を受けたいけど、後遺障害認定申請や示談交渉などさっぱりわからない・・・

事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。