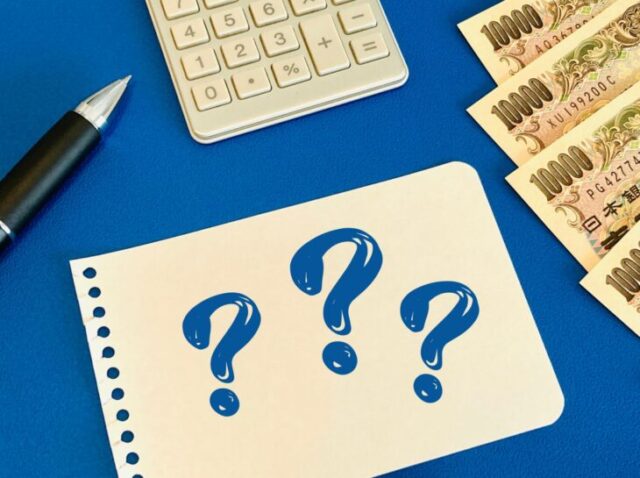交通事故の示談金とは?含まれる項目や変動要素などについて弁護士が解説

執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「交通事故の示談金って具体的にどんな費用が含まれているのか」
「交通事故の示談金はどのように決められるのか」
交通事故の被害に遭われた方の中には、示談金について詳しく知りたい方もいるのではないでしょうか。
示談金とは、交通事故によって生じた損害に対する賠償金を指し、怪我の治療に要した費用や物の損害に対する補償など、様々なものが含まれています。
本記事では、示談金に含まれる項目をはじめ、適正な示談金を受け取るためのポイントについて解説します。
- 示談金は、傷害(怪我の治療)に関する項目、後遺障害に関する項目、物損に関する項目、死亡に関する項目に分けられる
- 示談金の具体的な金額は、発生した損害の内容以外にも、過失割合や算定基準などの要素によって変動する
- 交通事故の示談交渉について弁護士に相談・依頼することで、損害項目を漏らすことなく請求でき、最終的に受け取る示談金の増額が期待できる
1.示談金に含まれる主な項目

示談金とは交通事故によって発生した損害賠償金で、示談交渉の結果、相手方から支払われる金額のことをいいます。
簡単に言えば、「これだけ払ったらお互い解決にしましょう」と決めた金額です。
どのような損害項目について賠償金を受け取ることができるかは個別具体的に異なりますが、大きく以下の4つに分けられます。
- 傷害に関する項目
- 後遺障害に関する項目
- 物損に関する項目
- 死亡に関する項目
順にご説明します。
なお、示談金の相場や具体的な計算方法などについては、以下の記事もご覧ください。
(1)傷害に関する項目
傷害に関する項目は、交通事故によって怪我を負った場合に発生するものです。
具体的には、以下のような項目が挙げられます。
- 治療費
- 傷害(入通院)慰謝料
- 入通院に関する費用
- 休業損害
順にご説明します。
#1:治療費
怪我の治療にかかった費用を治療費として請求することができます。
治療費として認められるためには、その怪我の治療として妥当かつ相当な範囲の治療がなされたと認められる必要があります。
なお、加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社が治療費について支払う一括対応が行われることが一般的です。
このような場合には、示談金から治療費が既払金として差し引かれる点に注意が必要です。
なお、一括対応はあくまで保険会社の任意であるため、対応を拒否されたり途中で打ち切られたりした場合には、自己負担が生じる可能性があります。
そのような場合でも、健康保険を利用するなどして完治または症状固定まで治療を継続した分について、示談交渉において保険会社に請求し、受け取ることが可能です。
詳細については、以下の記事が参考になりますので、合わせてご参照ください。
#2:傷害(入通院)慰謝料
交通事故を原因として怪我を負ったことや、それによって入通院しなければならなくなったことによる精神的苦痛に対する補償を傷害(入通院)慰謝料として受け取ることが可能です。
主に、入通院の期間あるいは日数をもとに具体的な金額が定められます。
そのため、途中で通院等をやめてしまうと受け取ることができる慰謝料は減額されるので、怪我が治癒するまで、または症状が固定するまでは、医師の指示に従って治療に専念することが大切です。
また、傷害(入通院)慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つの算定方法があり、どの算定基準で算出するかによって金額が異なります。
具体的な算定方法やポイントについては、以下の記事もあわせてご参照ください。
#3:入通院に関する費用
入院や通院の際に発生した費用も示談金に含まれます。
主に入院中の日用雑貨などの雑費や通院交通費などがこれにあたり、交通事故によって負担を強いられた費用について補償を受けることが可能です。
なお、通院交通費に関しては、主に自家用車を利用した場合や、電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の費用が該当し、タクシーで自宅から通院する場合などはその必要性が認められない限りはタクシーの費用を請求できない可能性があります。
また、負担した金額を証明しなければならないため、タクシーを利用した場合は領収書を残しておくことも重要です。
費用項目や算定方法については、以下の記事もあわせてご覧ください。
#4:休業損害
怪我の治療によって仕事を休まざるを得なくなったり、十分に働くことが出来なくなったりしたことによる収入の減少に対する補償です。
休業損害の金額は被害者が事故前に得ていた収入と休業日数に基づいて算出されるのが一般的です。
具体的には、以下の算定式に基づいて算出されます。
なお、基礎収入の日額は、被害者が事故前に得ていた収入から算定します。
- 基礎収入の日額×休業日数
なお、交通事故の怪我が原因で有給休暇を取得した場合であっても、その日数を休業日数に含めて計算することが可能です。
休業損害も自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つの算定方法があり、このうち、自賠責基準では休業損害の日額が原則として6,100円として定められています。
これに対して、裁判所基準では被害者の職業をもとに基礎収入の日額を割り出すため、より適正な休業損害を算出することが可能です。
休業損害の具体的な算定方法や注意点などについては以下の記事もご覧ください。
(2)後遺障害に関する項目
怪我の治療を行ったものの完治せずに何らかの後遺症が残存した場合、症状の内容や程度によって後遺障害等級の認定申請を行うことを検討することになります。
後遺障害等級の認定を受けることができれば、以下の補償を受けることが可能です。
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
順に解説します。
#1:後遺障害慰謝料
後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
受け取ることができる金額は認定される等級によって以下のように定められています。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判所基準 |
| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
| 4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
| 6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 13級 | 57万円(57万円) | 180万円 |
| 14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |
※()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合
等級が1つ異なるだけで数百万円の差が生じることもあり、適切な等級の認定を受けることが重要です。
そのため、申請の際は、適切な等級の認定を受けられるように後遺障害診断書の記載内容を細かくチェックし、提出書類に漏れがないように気をつけましょう。
なお、等級ごとの後遺障害慰謝料の相場や算定基準などについては以下の記事もご参照ください。
#2:後遺障害逸失利益
後遺障害を負ったことによる将来の収入の減少に対する補償を請求することもできます。
具体的な算定方法は、以下のとおりです。
- 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
受け取ることができる金額は、等級ごとに定められている労働能力喪失率によって変動するのが特徴です。
後遺障害等級に応じた労働能力喪失率の目安は、一般的には以下の表のとおりです。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
| 1級 | 100% |
| 2級 | 100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35% |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
もっとも、後遺障害等級の認定を受ければ、その等級に応じた労働能力喪失率がそのまま認められるわけではないことに注意しましょう。
算定方法や適正な金額を算定するためのポイントについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
(3)物損に関する項目
交通事故によって、車両や積載物に損壊が生じた場合にも補償を受けることができます。
主に車両の修理費や代車費用などがこれにあたります。
なお、物的損害のほかにも人的損害が生じている人身事故の場合には、先に物的損害部分のみを示談交渉で確定させることが一般的で、その後に人的損害に関する賠償についての交渉に移ります。
なお、物損のみが生じた事故では、慰謝料を請求することはできません。
物損に関する賠償項目については以下の記事も参考になります。
(4)死亡に関する項目
被害者が亡くなった場合は、怪我による損害とは別に損害賠償項目が設けられています。
主な費用は以下のとおりです。
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
死亡慰謝料とは、被害者本人と被害者遺族の両方が受け取ることができるものなので、被害者が亡くなったからという理由で、本来被害者が受け取ることができるはずだった死亡慰謝料が無くなるわけではありません。
順にご説明します。
#1:死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者がなくなったことによる精神的苦痛に対する補償です。
金額は、被害者の家庭における地位(一家の支柱、配偶者など)や扶養家族の有無によって変動します。
死亡慰謝料の具体的な算定方法や金額相場については、以下の記事も参考になります。
#2:死亡逸失利益
死亡逸失利益は、被害者が死亡したことによる収入の減少に対する補償です。
被害者が会社員や自営業者だった場合だけでなく、学生や専業主婦(夫)だった場合でも請求することができます。
また、被害者の年齢や職業、収入などによって金額が異なるのも特徴です。
具体的な算定方法や適正な金額を算定するためのポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
2.示談金額が変動する要素

示談金額が変動する要素はいくつかあります。
具体的には、以下の要素によって増加または減少する場合があります。
- 算定基準
- 過失割合
- 増額事由
- 素因減額
これらの要素を把握しておくことが、適正な示談金の算定のためにも重要です。
(1)算定基準
示談金のいくつかの項目については、算定基準に従って算出されるものがあります。
算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあり、このうち、自賠責基準は自賠責保険が用いる基準であり、交通事故の被害者の損害について最低限度の補償を行うことを目的としているため、最も低額な水準です。
また、任意保険基準は加害者側の保険会社が用いる算定基準であり、詳細は非公開となっているものの、自賠責基準と同等かやや上回る水準にとどまる傾向にあります。
これに対して、裁判所基準は過去の裁判例をもとにした算定基準であり、3つの算定基準の中で最も高額な水準です。
どの算定基準を採用するかによって示談金が変動するので、適切な基準に基づいて算出を行う必要があります。
示談金の中でも慰謝料についての相場や目安については、以下の記事も参考になるので、あわせてご参照ください。
(2)過失割合
過失割合は、事故の発生について、当事者のどちらに、どれだけ不注意(過失)があったのかを割合で示したものです。
事故の証拠等によって過失割合を決め、被害者にも過失が認められる場合は、過失割合に応じて損害賠償金が減額されます。
被害者の過失割合に応じて損害賠償金が減額されることを過失相殺といい、過失割合は示談金の金額に大きな影響を及ぼす要素です。
たとえば、加害者と被害者の間で過失割合が8対2となった場合は、被害者が受け取ることができる示談金は2割減額されます。
そのため、被害者側に高い過失割合が認められてしまうと、受け取ることができる示談金が大幅に減少してしまう可能性が高いことに注意が必要です。
特に加害者側の保険会社は、支払う示談金を低く抑える目的で、被害者側の過失を高く見積もって示談金の提案をしてくる可能性があります。
当事者間の過失割合は、示談交渉において決められるものであり、保険会社から不適切な過失割合を提示されても、適切に反論・立証を行うことが重要です。
過失割合による示談金の考え方や具体的なケースについては、以下の記事も参考になります。
なお、上の説明は裁判所基準で相手方と交渉する場合のものですが、自賠責基準では、被害者の救済という観点から、過失相殺に関しては特別な処理がなされます。
詳細については、以下の記事もご参照ください。
(3)増額事由
示談金の中でも慰謝料に関しては、算定基準に基づいて算出された金額相場よりも増額されるような事由があります。
主な事由は以下のとおりです。
- 加害者の行為態様が悪質である、または加害者に故意もしくは重過失があること
- 加害者の態度が著しく不誠実であること
- 被害者や家族に対する経済的・精神的影響
特に加害者の事故の際の故意・重過失だけでなく、事故の後の態度によっても示談金が増額されることがある点を押さえておきましょう。
また、被害者や家族が事故をきっかけに精神疾患にり患して治療が必要になるなど、経済的な影響や精神的な影響がある場合も増額されることがあります。
実際に相場よりも増額が認められた裁判例などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。
(4)素因減額
素因減額とは、事故による影響と、被害者が交通事故の前から持つ事情が合わさることによって、損害が発生・拡大した場合に、損害賠償金を減額することです。
たとえば、通常であれば打撲程度の怪我しかしないような衝撃の事故だったものの、被害者が骨粗しょう症だったために骨折してしまったというような場合、その損害の全てを加害者に負担させるのは酷であるとして、賠償金が減額されることがあります。
そのため、加害者側が素因減額を主張してきても、それが本当に損害賠償金を減額させるべき事情なのかどうか、適切に反論・立証を行うことが大切です。
なお、素因減額が主張されやすいケースや、素因減額が主張された場合に弁護士に相談するメリットについては、以下の記事もぜひご覧ください。
3.適正な示談金を獲得するためのポイント

示談金は交渉次第で変動するので、適正な示談金を獲得するためには、いくつか注意しなければならないことがあります。
主なポイントは以下のとおりです。
- 完治または症状固定まで治療を継続する
- 後遺症が残れば後遺障害等級の認定申請を行うことを検討する
- 保険会社の提示する金額を鵜呑みにしない
順に解説します。
なお、適正な示談金を受け取るためのポイントや要素については、以下の記事でも解説しています。
(1)完治または症状固定まで治療を継続する
完治または症状固定まで治療を継続することが重要です。
症状固定とは、医学上一般に承認された方法で怪我の治療を行っても改善が見込めないと判断された状態をいいます。
怪我の治療は、医師から完治または症状固定の診断を受けるまで、その症状や治療内容に照らして適切な期間・頻度にわたって行うことが何よりも大切で、通院頻度が少ない場合には、怪我の程度が重くないと判断されて賠償金を減額される可能性があります。
また、通院頻度が多すぎると過剰診療を疑われてその分の治療費を示談金に含められなくなるおそれがあります。
これに加えて、保険会社から治療費の一括対応を打ち切られるリスクもある点に注意しましょう。
このように、通院頻度は多すぎても少なすぎても賠償金が減額されることがある点を押さえておく必要があります。
なお、治療費の一括対応を打ち切られても、医師が治療継続の必要性を認めている場合には、通院を途中でやめる必要はありません。
通院を途中でやめた後に後遺症が残存した場合は、通院をやめたことによって症状が悪化したと捉えられ、後述する後遺障害等級の認定で不利に扱われる可能性が高まります。
通院頻度の考え方については、以下の記事もあわせてご参照ください。
(2)後遺症が残れば後遺障害等級の認定申請を行うことを検討する
症状固定の診断を受けた場合は、残存している症状の内容や程度に応じて後遺障害等級の認定申請を行うことを検討しましょう。
後遺障害等級の認定を受けることができれば、後遺障害に関する損害項目についても賠償を受けることが可能です。
もっとも、残存している症状が後遺障害等級の認定基準に定められている症状に該当する場合でも、必要な書面や記載が欠けているなど、申請のやり方次第では希望する等級認定が受けられないケースもあるので、手続は適切に行うことが重要です。
手続の流れやポイントについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
(3)保険会社の提示する金額を鵜呑みにしない
示談交渉では、加害者側の保険会社が算定した示談金を提示してきますが、鵜呑みにしないことが大切です。
保険会社は、なるべく支出を抑えようとするので、被害者に不利になるように示談金を算定します。
そのため、提示された金額は相場よりも低額であることが多く、その内容で示談に応じてしまうと適正な賠償金を受け取ることができない可能性が高いです。
交渉を継続することで示談金が増加する可能性もあるので、保険会社から金額を提示されてもその場で応じないようにしましょう。
4.示談金について弁護士に相談するメリット

加害者側の保険会社から示談金の提示があった場合や提示された示談金を受け入れてよいかに疑問などがある場合には、保険会社と交渉を行い、適正な金額を求めることが重要です。
もっとも、交渉に習熟した保険会社を相手に示談交渉を有利に進めることは容易ではありません。
そのため、示談金に不安や疑問がある場合には、まずは弁護士に相談することが何よりも大切です。
弁護士に相談するメリットは、以下のとおりです。
- 示談金の項目について不足なく請求を行うことができる
- 示談交渉を一任できる
- 裁判所基準を用いた交渉ができる
順にご説明します。
(1)示談金の項目について不足なく請求を行うことができる
弁護士に相談することで、加害者に請求すべき損害項目を不足なく請求できるようになります。
上記で述べたように、示談金といっても様々な項目の費用が含まれており、一つ一つ交渉しなければなりません。
被害者側が直接示談交渉に臨むと、本来であれば請求できたはずの項目を漏らしてしまうことも十分考えられます。
弁護士であれば、どのような損害項目を請求することができるかを熟知しているため、適切な補償を受けることが可能です。
(2)示談交渉を一任できる
相談の流れから、弁護士にそのまま示談交渉を一任することができます。
弁護士であれば、保険会社が主張する過失割合や減額事由などに対しても、法的根拠に基づきながら適切に反論・立証が可能です。
示談交渉では精神的に大きな負担がかかるものですが、弁護士に示談交渉を一任することで、交渉に関する不安を解消し、怪我の治療などに安心して専念できます。
(3)裁判所基準を用いた交渉ができる
弁護士であれば、裁判所基準を用いた交渉が可能です。
裁判所基準は、自賠責基準や任意保険基準に比べ、最も高額な賠償額を請求することができるものです。
被害者ご自身で裁判所基準を用いて示談金の算定を行い、保険会社と交渉を行うことも可能ですが、そのような場合には保険会社が交渉に応じることはほとんどありません。
弁護士に交渉を依頼することで、裁判所基準を用いた適正な示談金を請求し、受け取ることができるのです。
これによって、最終的に受け取ることができる示談金の増額が期待できます。
まとめ
交通事故の示談金には、治療費や慰謝料など様々な項目が含まれています。
示談金の金額は、示談交渉次第で大きく変動するため、少しでも多くの示談金を受け取りたい方はまずは弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼することで、適正な示談金を請求できるだけでなく、示談交渉にかかる負担を軽減することもできます。
保険会社との交渉などの精神的不安を取り除き、怪我の治療や私生活に専念することができるため、交通事故の被害に遭われた方は、一度弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、示談金に関してお悩みの方はお気軽にご相談ください。
交通事故で
こんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、保険会社・相手方とどんな風に対応すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を受けたいけど、後遺障害認定申請や示談交渉などさっぱりわからない・・・

事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。