個人再生の流れやスケジュールとは?手続に関する注意点も解説
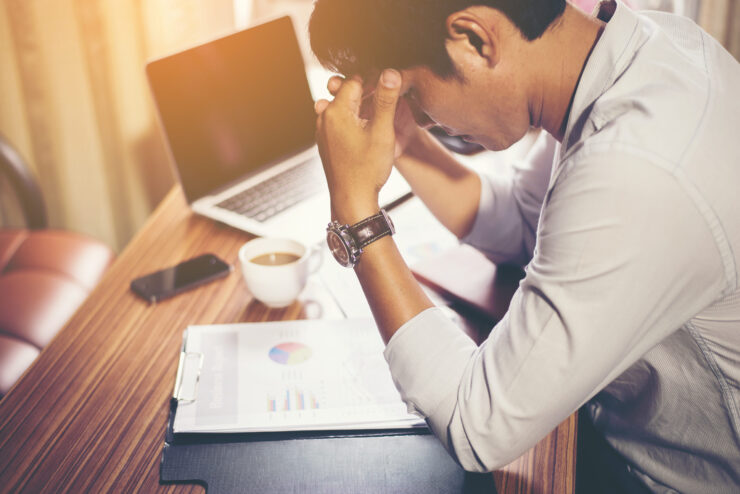
「個人再生はどのようなスケジュールで手続が進行するのか」
「個人再生の手続で押さえておくべきなのはどのような点なのか」
借金の返済ができなくなり、債務整理を行うことを検討されている方の中には、個人再生の手続について、このような疑問や悩みをお持ちの方もいると思います。
個人再生とは、債務整理の手続の1つで、借金の返済義務の軽減を受けることができます。
裁判所への申立てが必要となるものの、借金総額によっては最大で10分の1まで減額を受けることが可能です。
一方で、法律に従って、かつ、裁判所の定めるスケジュールのとおり手続を進めないと、失敗に終わってしまうリスクがあります。
本記事では、個人再生の手続の流れやスケジュールなどについて解説していきます。
1.個人再生のスケジュールと目安期間

個人再生は、裁判所に申し立てて借金の返済が困難であることが認められることにより開始する手続であり、借金総額に応じて減額された金額を原則3年にわたって返済する再生計画の認可を受け、計画どおりに返済をしていく手続です。
同じ債務整理の手続である任意整理と比較すると、個人再生では借金の元本部分まで減額することができるため、返済負担の大幅な軽減につながります。
また、同じく裁判所を介して行う自己破産の手続では、一定額以上の財産を所有している場合には、それらの財産は手続の中で売却され、お金に換えた上で(換価処分)、債権者への配当にあてられることになります。
具体的には、住宅や車、バイクなどが自己破産では換価処分の対象となることが多く、これらの財産を手放さなければならなくなります。
これに対して、個人再生では換価処分が行われることがないため、資産価値の高い財産を手元に残した状態で手続を行うことができる点に大きな特徴があります。
また、住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特則」)を利用することで、住宅ローンをそのまま支払い続け、そのほかの債務を減額することもできます。
このように、個人再生には、ほかの債務整理の手続にはないメリットがあります。
一方、手続は裁判所を通して進める必要があり、その流れは法律によって定められています。
弁護士に依頼する場合の大まかな手続のスケジュールは、以下のとおりです。
- 申立準備期間|2~3か月程度
- 裁判所での手続|6か月程度
- 再生計画に基づく返済|原則3年
以上のとおり、個人再生の手続は最短で進めたとしても、8か月程度の期間を要することになります。
以下、詳しく説明します。
なお、個人再生を行うメリット・デメリットについては、以下の記事をご参照ください。
(1)申立準備期間|2~3か月程度
裁判所への申立てを行うまでの準備には、概ね2~3か月程度の期間を要します。
具体的には、以下の流れで申立準備を進めていくことになります。
- 弁護士に相談・依頼
- 受任通知の送付・財産調査
- 申立書類の作成・資料の収集
申立書類の作成や資料収集に時間がかかることがあり、スムーズに申立てを行うためにはなるべく早期に弁護士に相談することがおすすめです。
なお、弁護士費用の積立てを行う場合には、それが完了するまで準備期間が必要となることもあります。
#1:弁護士に相談・依頼
個人再生は、裁判所を介して行う手続であるため、専門知識や実務経験がなければ手続をスムーズに進めることが困難といえます。
そのため、個人再生を行うことを検討されている場合には、まずは弁護士に相談した上で手続を依頼することがおすすめです。
特に債務整理に慣れた弁護士に相談することで、借金総額や収入状況などに照らし合わせて、個人再生を行うことが最適なのかについてのアドバイスを受けることができます。
債務整理の方法は、借金や収入等によって適切な方法が変わるため、弁護士のアドバイスを判断基準にすることが可能です。
また、個人再生を行う場合には、今後の手続の流れやポイントについても説明を受けることができるため、見通しを持って効率よく手続を進めていくことができます。
#2:受任通知の送付・財産調査
弁護士が手続を受任すると、債権者に対して受任通知が送付されます。
受任通知には、債権者が債務者に対して直接督促や取立てを行うことを禁止する法的効力があるため、受任通知の送付が行われると一時的に返済がストップします。
受任通知の送付に合わせ、債権者に対して債権額を通知するよう求め、債権額の調査も行います。
さらに、次の資料の収集に合わせ、債務者の財産の調査も弁護士が行うことになります。
#3:申立書類の作成・資料の収集
個人再生は裁判所への申立てを必要とし、その際には書類や資料を提出しなければなりません。
具体的には、以下のような書類や資料を作成・収集する必要があります。
- 申立書
- 債権者一覧表
- 陳述書
- 家計収支表
- 財産目録
- 給与明細書
- 源泉徴収票
- 住宅などの登記事項証明書
- 預貯金通帳の写し など
なお、上記以外にも、所有する財産の状況や住宅ローン特則の利用の有無などによって追加で書類・資料の提出を求められる場合もあります。
弁護士に手続を依頼していれば、書類の作成を任せたり、資料収集に関するサポートを受けたりすることも可能です。
申立ての際に必要となる書類・資料の詳細や入手方法については、以下の記事も参考になります。
(2)裁判所での手続|6か月程度
申立ての準備が終了したら、裁判所での手続に移ります。
裁判所における手続は、申立てに始まり、再生計画案の認可決定によって終了し、全体で6か月程度を要することが一般的です。
具体的には、以下の流れで進行します。
- 個人再生手続の開始申立て
- 手続開始決定
- 履行テスト
- 再生計画案の作成・提出
- 再生計画案の認可決定
順にご説明します。
#1:個人再生手続の開始申立て
申立書類を裁判所に提出し、個人再生の申立てを行います。
手続を弁護士に依頼した場合には、弁護士が申立てを行います。
なお、書類や資料に不備がある場合には、申立てが棄却されることもあるため、必ず債務整理に慣れた弁護士のサポートを受けるようにしましょう。
#2:手続開始決定
提出された申立書類や資料に基づき、裁判所が不備などがないことを確認し、手続を開始するための要件を満たしていると判断すると、手続開始決定が下されます。
手続開始決定は、申立てがなされてから1か月以内に出されることが一般的です。
なお、東京地方裁判所では、開始決定の際に裁判所によって個人再生委員が選任されることになり、開始決定の前後でこの個人再生委員と面談を行う必要があります。
個人再生委員となるのは弁護士であり、面談は個人再生委員の事務所で行われることがほとんどです。
面談では、個人再生を申し立てるに至った経緯や財産状況などについて、申立書類を補足する説明を行うことになります。
個人再生委員については、裁判所によっては再生計画どおりの返済の可能性に疑問がある場合などに限定して選任するなどの運用を行っている場合もあります。
そのため、あらかじめ弁護士に管轄の裁判所の運用について確認しておくことが大切です。
#3:履行テスト
申立てがなされた後には、再生計画が認可されるまでの間、履行テストが行われます。
履行テストとは、債務者が再生計画どおりに返済できるかを判断するための手続で、再生計画案で予定されている返済額を毎月指定の口座に振り込むことによって行われます。
これは、申立人に再生計画案が認可された後に継続的に返済を行うだけの支払能力があるかどうかを裁判所が判断するためのものです。
履行テストは一度でも支払を怠ってしまうと、その時点で手続が廃止(終了)となってしまうため、支払を怠ることなく対応することが最も大切です。
なお、個人再生委員が選任されている場合には、履行テストによって振り込んだ金額が個人再生委員の報酬にあてられます。
ただし、振り込んだ金額のすべてが報酬としてあてられるわけではなく、個人再生委員の報酬を除いた額は履行テストが終了すると申立人に返還されることになります。
#4:再生計画案の作成・提出
再生計画案は、総額に応じて減額された借金をどのように返済していくかについて記載した書面です。
個人再生では、借金総額に応じて、以下のように返済額(最低弁済額)が定められています。
| 借金総額 | 最低弁済額 |
| 100万円未満 | 借金総額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超え1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
| 1500万円超え3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円超え5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
再生計画案は、裁判所から提出期限を設定されるため、期日を守って作成・提出する必要があります。
期日を1日でも過ぎてしまうと、その時点で手続が廃止(終了)となってしまうことに注意が必要です。
また、住宅ローン特則を利用する場合には、その旨も再生計画案に記載する必要があります。
なお、後で説明するように、財産がある場合など、上記の最低弁済額以上の金額の返済を再生計画案に定めなければならないこともあります。
#5:再生計画案の認可決定
提出された再生計画案の内容を裁判所が審査し、再生計画案に基づく返済ができる見込みがあると判断し、かつ、債権者の過半数または債権額の過半数を有する債権者からの反対がなかった場合、認可決定が下されます。
認可決定が出されると裁判手続は終了し、認可決定から約1か月以内に返済が開始されるケースが多いです。
返済が再び始まれば、返済計画案に基づいて完済を目指しましょう。
(3)再生計画に基づく返済|原則3年
再生計画案の認可を受けた後は、その内容に従って返済を行わなければなりません。
返済の期間については原則として3年ですが、特別の事情がある場合には5年に延長されることもあります。
もっとも、収入や支出の状況から、3年で返済を終えることが困難であるような「特別の事情」が必要となるため、5年での返済が認められるケースはそれほど多くはありません。
なお、再生計画の内容に従った返済ができなくなった場合には、債権者が裁判所に対して再生計画の取消しを請求する可能性がある点に注意しましょう。
再生計画が取り消されてしまうと、もとの借金総額での返済を求められることになるため、個人再生を行った意味が損なわれてしまいます。
また、返済が滞ってしまうと債権者からの訴訟や差押えなどのリスクも高まるため、再生計画に従って返済を継続的に行うことが最も重要です。
2.個人再生を行う際の注意点

上記のように、個人再生の手続は裁判所を介して、法律および定められたスケジュールに従って進行するため、いくつかの注意点があります。
具体的な注意点は、以下のとおりです。
- 手続を行うためには要件を満たす必要がある
- 裁判所に費用を納付しなければならない
- 氏名や住所が官報に掲載される
- 必ずしも最低弁済額まで減額されるとは限らない
順にご説明します。
なお、これら以外にも、個人再生の手続中には避けなければならない行為もあります。
詳細については、以下の記事もご参照ください。
(1)手続を行うためには要件を満たす必要がある
個人再生は、必ず申立てが認められるわけではなく、要件を満たさなければなりません。
具体的には、個人再生には以下の2つの手続があります。
- 小規模個人再生手続
- 給与所得者等再生手続
このうち、2つの手続に共通する要件には、以下のものがあります。
- 支払不能の生ずるおそれがあること
- 住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えないこと
- 定期的な収入を得る見込みがあること
また、これらの要件のほかにも、再生計画案の認可決定を受けるための要件も満たすことが求められます。
そのため、個人再生を行い、借金の返済負担の軽減を受けるためには、さまざまな要件を満たす必要があることに注意しましょう。
個人再生を行うためのさまざまな要件については、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)裁判所に費用を納付しなければならない
個人再生を行う場合には、裁判所に費用を納付する必要があります。
費用項目と金額相場は、以下のとおりです。
| 裁判所費用の項目 | 金額相場 |
| 申立手数料(収入印紙代) | 1万円 |
| 予納金(官報公告費) | 1万3000円程度 |
| 郵券(切手)代 | 2,000円程度 |
| 個人再生委員の報酬 | 15万円~25万円 |
なお、裁判所に対する費用を納付できない場合には、その時点で手続が廃止(終了)となってしまうため、申立ての前までに準備しておきましょう。
また、弁護士に手続を依頼すると、裁判所費用に加えて弁護士費用も必要となります。
弁護士費用については、受任通知の送付によって返済が一時的にストップしている期間を利用して、積み立てることが可能なこともあります。
個人再生の費用の詳細や費用が払えない場合の対処法については、以下の記事もご覧ください。
(3)氏名や住所が官報に掲載される
個人再生を行うと、申立人の氏名や住所が官報に掲載されます。
官報を介して、周囲に個人再生をした事実が知られる可能性は否定できませんが、官報を日常的にチェックしている人はほんの一握りです。
そのため、官報をきっかけに個人再生の事実が知られるリスクは、そこまで気にする必要はないでしょう。
個人再生で官報公告が行われるタイミングや内容については、以下の記事で詳しく解説しています。
(4)必ずしも最低弁済額まで減額されるとは限らない
個人再生をしても、必ずしも最低弁済額まで減額されるとは限りません。
先ほども述べたように、個人再生では自己破産とは異なり、資産価値の高い財産について引き続き手元に残しながら借金の減額を受けることができます。
しかし、そうすると、一定額以上の財産について換価処分が行われ、債権者が配当を受けることができる自己破産の場合と比較して、債権者が受ける不利益が大きくなってしまいます。
そのため、個人再生によって定められる最低弁済額は、債務者が自己破産を選択した場合に債権者に対して行われる配当の額を下回ってはならないとする「清算価値保障原則」によって修正が図られるのです。
以上から、資産価値のある財産を保有している場合、最低弁済額ではなく清算価値による金額を返済する可能性があることを想定しておく必要があります。
どのような財産が清算価値として計上されるのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
3.個人再生を行った後の注意点

個人再生を行った後は、信用情報機関に事故情報が一時的に登録されることに注意しましょう。
信用情報機関とは、加盟している金融機関から顧客の借入れや返済に関する情報の提供を受けてこれを管理し、各金融機関から照会があれば情報を提供する機関です。
個人再生をはじめとする債務整理を行ったという事実は、その人の返済能力に問題があることを意味する事故情報として登録されます。
この事故情報は、金融機関に対して、借入れやローンの申込みがあった場合に与信調査を行う目的でその金融機関が照会を行い、これを知ることになります。
そうすると、金融機関は貸倒れのリスクを考慮して、借入れなどの申込みを拒否することになるのです。
そのため、信用情報機関に事故情報が登録されている間は、借入れやローンの利用、クレジットカードの作成や利用・更新ができなくなることに注意が必要となります。
なお、一定期間経過すると、信用情報機関から事故情報が削除されるので、個人再生をしたからといって永続的にクレジットカードの利用などができなくなるわけではありません。
個人再生における事故情報の登録機関や確認方法などについては、以下の記事をご覧ください。
4.弁護士に個人再生について相談するメリット

個人再生は、裁判所を介して行うため、さまざまな注意点があるほか、手続の期間が長期化する傾向にあります。
特に手続に関する知識や経験がなければ、スムーズに進めることができず、途中で失敗に終わってしまうリスクもあります。
そのため、個人再生を行うことを検討されている場合や手続に不安・疑問がある場合には、まずは専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 個人再生を行うことができるかについて説明を受けられる
- 書類作成や資料収集についてサポートを受けられる
- 裁判所とのやりとりを任せることができる
順に見ていきましょう。
(1)個人再生を行うことができるかについて説明を受けられる
弁護士に相談することで、個人再生を行うための要件を満たしているかについて説明を受けることができます。
先ほど述べたように、個人再生を行うためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。
個人再生をはじめとする債務整理の手続は、債務者本人が行うこともできますが、特に手続を行うための要件などについては専門知識が必要となるため、正確に判断することが難しいこともあります。
個人再生ができるかどうか不明なまま手続を進めてしまうと、申立てが棄却されたり手続が途中で失敗したりするリスクが高まります。
そのようなリスクを回避しながらスムーズに個人再生を行うためにも、まずは弁護士に説明やアドバイスを受けることが大切です。
また、収入や借入額、資産状況などによっては、ほかの手続を行うことが適しているケースも考えられます。
専門家である弁護士に相談することで、ご自身の選択肢を広げることができる場合もあるため、なるべく早期に相談されることがおすすめです。
(2)書類作成や資料収集についてサポートを受けられる
弁護士に相談の上で手続を依頼すると、書類作成や資料収集についてサポートを受けることができます。
個人再生を行う場合には、先ほども述べたように、申立準備の段階で、提出書類や資料を用意しなければなりません。
どのような書類や資料が必要になるかは、資産状況や住宅ローン特則の利用の有無などによって異なります。
そのため、知識や経験がない中で債務者自身で作成や収集を行うことは困難です。
債務整理に習熟した弁護士に手続を依頼することで、書類作成を任せたり、資料収集について的確なアドバイスを受けることができます。
これによって、申立書類や資料を効率的に作成・収集することができ、手続全体に要する期間を短縮することにもつながります。
(3)裁判所とのやりとりを任せることができる
弁護士に依頼することで、裁判所とのやりとりについても一任することが可能です。
弁護士に手続を依頼することで、申立書類や再生計画案の提出の対応などもすべて弁護士に一任することができます。
これによって、再生計画案の認可の可能性を高めることもでき、手続を失敗させることなく進めることができます。
まとめ
個人再生は裁判所を介して手続が進められるため、スムーズに進んでも、再生計画の認可を受けるまでに8か月程度の期間を要する可能性があります。
また、再生計画案が認可されても、そこから3~5年かけて返済を継続していく必要があることにも留意しておきましょう。
さらに、手続は複雑であり、スムーズに進めるためには法的な知識と実務経験が求められる場面も多いです。
正確かつ円滑に手続を進め、借金の返済義務の軽減を受けるためにも、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、個人再生を行うことを検討されている方はお気軽にご相談ください。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事



























