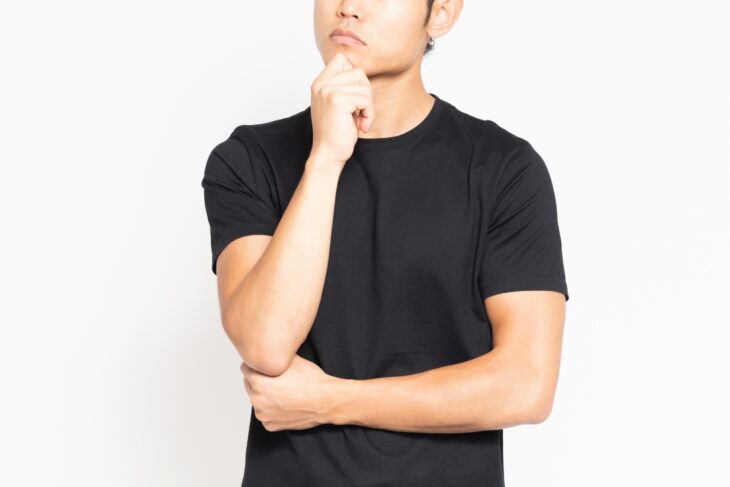カードローンの返済を延滞するとどうなる?放置するリスクや対処法についても解説

「カードローンを延滞している状態で放置するとどうなるのか」
「カードローンを延滞している状態を解決するにはどうしたらいいのか」
カードローンの返済で困っている方の中には、このような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。
手元にまとまったお金を用意することができない場合であっても、延滞の状態を放置してはいけません。
返済をしない状態が長く続くことで、最終的にはカードローン会社から訴訟や差押えなどの法的手続をとられ、財産を失う事態に陥ることもあるため、注意が必要です。
本記事では、カードローンの延滞を放置するリスクや延滞している状態の対処法等について解説します。
返済が難しい場合には、債務整理を行うことで、延滞の状態を解消し、借金の返済負担を軽減または免除してもらうことが可能です。
手続ごとの特徴やメリット・デメリットなどについても合わせて解説していますので、カードローンの返済にお困りの方の参考となれば幸いです。
1.カードローンの延滞を放置するリスク

カードローンの返済ができなくなり、延滞してしまうことでさまざまな法的リスクが生じます。
特にすでに返済を滞納しており、これを放置し続けた場合には、最終的に債権者から財産を差し押さえられてしまうリスクが高まる点に注意が必要です。
もし債権者から差押えを受けると、預貯金や車などの財産を失ってしまう可能性があります。
なお、返済を滞納した場合に直ちに差押えが行われるわけではありません。
具体的には、以下のような流れで段階的に差押えに至ります。
- 遅延損害金が発生する
- カードの利用停止や強制解約となる
- 信用情報機関に事故情報が登録される
- 一括返済を求められる
- 支払督促や訴訟などに移行する
- 財産を差し押さえられる
順にご説明します。
(1)遅延損害金が発生する
返済期日を1日でも超過すると、遅延損害金が発生します。
遅延損害金は、返済を徒過したことに対する制裁の意味合いもあるため、利息よりも高い利率が定められていることが一般的です。
また、返済期日を1日徒過していくごとに加算されていくため、返済期日を過ぎれば過ぎるほど遅延損害金が膨らんでいきます。
そのため、返済できていない残債務と利息に合わせて、遅延損害金についても支払を行わなければならず、放置することで返済負担が大きくなる点に注意しましょう。
遅延損害金の概要や具体的な利率などについては、以下の記事で解説しています。
また、カードローンの支払を延滞した場合の遅延損害金の計算方法やシミュレーションについては、以下の記事が参考になります。
(2)カードの利用停止や強制解約となる
カードローンの返済が期日までになされない場合、新たな借入れができなくなり、カードの利用が停止されてしまう可能性があります。
返済が滞ることで、延滞分の支払が終わるまでは新たな借入れができないことが多い点に注意しましょう。
なお、支払を行うことで再びカードローンの利用ができる場合もありますが、利用が再開されるまでに日数がかかる可能性もあります。
また、延滞期間が長期に及ぶ場合には、カードが強制解約となるリスクも高まる点に注意が必要です。
特にクレジットカードのローン(キャッシング枠)の返済が長期間滞っている場合には、クレジットカードが強制解約され、ショッピング枠についても利用できなくなることがあります。
(3)信用情報機関に事故情報が登録される
カードローンの延滞が2か月以上続いている場合には、信用情報機関に事故情報が登録されます。
信用情報機関は、加盟している金融機関から顧客の借入れや返済状況などの情報について提供を受けてこれを管理し、金融機関から照会があった場合には開示する機関です。
カードローンの返済を滞納している事実は、その人に返済能力がないことを示す事故情報として登録され、各金融機関が審査の過程で照会を行うことで知られてしまいます。
そのため、事故情報が登録されると、それ以降は新たな借入れやローンの利用ができません。
ただし、事故情報は一度登録されたとしても、一定期間が経過すると削除されます。
つまり、事故情報の登録が削除された後であれば、以前のように借入れやローンを利用できる可能性があるのです。
他方で、クレジットカードのローンや銀行などの金融機関のローンの場合には、信用情報機関とは独自に顧客情報を管理しているため、一度延滞をしてしまったカードローンは今後一切利用できなくなる可能性が高いといえます。
カードローンの滞納と事故情報の関係やほかの影響などについては、以下の記事でも解説しています。
(4)一括返済を求められる
通常、カードローンの返済を滞納すると、返済期日の翌日以降から電話やハガキなどで返済の督促が行われるようになり、場合によっては一括返済が求められます。
なお、いきなり一括返済が求められるわけではなく、督促に応じずに無視し続けた場合に、債権者が残債務について一括支払を求めることが一般的です。
本来、債務者には分割支払いの各返済期日を迎えるまでは支払を猶予されるという期限の利益がありますが、返済期日を徒過しても支払を行わないことによって、債務者は期限の利益を喪失します。
期限の利益を喪失した債務者は、債権者から一括返済を求められた場合、応じなければなりません。
なお、一括支払を求められた場合、これに応じなければ後述する法的措置に移行するリスクが高まります。
そのため、支払ができない場合には、遅くともこの時点までに弁護士に相談することが重要です。
(5)支払督促や訴訟などに移行する
債権者から一括請求が行われた後も支払をせずにいると、訴訟の提起などに移行するリスクが高まります。
訴訟が提起されると、裁判所から訴状が送達され、債務者は裁判所への出廷や答弁書の作成・提出を行わなければなりません。
そして、裁判所の求めにも応じない場合には、債権者の請求が認容され、債権者勝訴の確定判決が出されることになります。
そうなれば、債権者は勝訴の確定判決に基づいて強制執行などの手続に移行する可能性が高いです。
また、裁判所から支払督促が送付された場合には注意しなければなりません。
支払督促は、債権者からの申立てに基づいて、裁判所が債務者に対して支払を命じる手続です。
債務者に支払督促が送付されてから2週間以内に異議申立てを行わなければ、支払督促に仮執行宣言が付されることになります。
仮執行宣言が付されてから2週間以内に異議申立てを行わなければ、債務名義となり、債権者は仮執行宣言付支払督促に基づいて強制執行を申し立てることが可能です。
このように、支払督促は訴訟と比較すると簡便に手続を行うことができるため、債権者が選択しやすい法的手段といえます。
なお、支払督促の手続の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(6)財産を差し押さえられる
勝訴の確定判決や仮執行宣言付支払督促に基づき、債権者が強制執行の手続を申し立てると、債務者の財産が差し押さえられます。
特にカードローンの場合には、債権者に勤務先を知られていることが多いため、給与が差し押さえられることが多いです。
それだけでなく、裁判所から勤務先に対して差押えの通知がなされることにより、カードローンを滞納している事実が勤務先に知られるリスクがあります。
このように、生活や仕事などに影響が生じる可能性があるため、法的措置に移行する前に適切な対応を行うことが最も重要です。
差押えの対象となる財産の具体例や影響については、以下の記事もあわせてご覧ください。
また、差押えの流れや回避するための対処法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
2.延滞してしまった場合の対処法

カードローンの返済を滞納してしまった場合でも、早期に必要な対応を行うことで、訴訟や差押えなどに発展するリスクを抑えることができる場合があります。
具体的な対処法は以下のとおりです。
- 指定期日までに支払を行う
- 分割払いなどについて債権者と交渉を行う
順に解説します。
(1)指定期日までに支払を行う
督促や一括請求を受けたケースでも、支払を行うことができる場合には、債権者から送付された催告書の内容に従い、期日までに支払を行いましょう。
先ほども述べたように、カードの利用が停止された場合でも、なるべく早期に支払を行うことで利用停止の措置が解除されることがほとんどです。
そのため、延滞に気づいた時点や督促を受けた時点で速やかに返済を行うことで、生活などへの影響を最小限に食い止められる可能性があります。
なお、一括請求を受けた場合には、その時点ですでに事故情報が登録されていることが通常であるため、ほかの金融機関や貸金業者から借入れを行うことはできません。
したがって、指定期日までに支払を終えることができない場合には、家族などから援助を受けて支払を行うなどの対応が必要となるケースもあります。
(2)分割払いなどについて債権者と交渉を行う
一括支払が難しい状況でも分割払いによって返済ができる場合は、債権者にその旨の連絡を行い、分割で支払ができるように交渉を行いましょう。
債権者次第では、分割払いに応じてもらえる可能性があります。
例えば、以下のような対応を行うことで、分割払いに応じてもらえる可能性を高めることが可能です。
- 督促や一括請求がなされてから直ちに債権者に連絡をする
- 返済の意思を明らかにし状況を率直に伝える
- いつまでに支払を終えるかのスケジュールについて明確に伝える
ただし、すでに滞納の期間が長期に及んでいる場合やこれまでに何度か延滞を繰り返している場合には、応じてもらえないことが多いです。
そのような場合には、なるべく早期に弁護士に相談した上で、後に述べる債務整理を行うことを検討しましょう。
3.債務整理の種類と特徴

カードローンの返済の目途が立たない場合には、債務整理の手続を行うことで返済負担の軽減や借金の免除を受けることが可能です。
具体的には、以下のような手続があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
なお、手続ごとに効果や特徴が異なるため、どの手続を行うことがご自身に適しているかは、収入や資産の状況、借入額などによって左右されます。
そのため、ご自身に最適な方法で借金問題の解決を図りたい場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
なお、カードローンによる借金を債務整理した場合の主な注意点については、以下の記事もあわせてご覧ください。
(1)任意整理
任意整理とは、将来的に発生する利息のカットと返済スケジュールの再設定(概ね3~5年程度)をして毎月の返済金額を減額することを債権者と直接交渉し、交渉でまとまった合意に基づいて返済を行う手続です。
カードローンや借入れなどを返済する場合には、元本部分に利息も合わせて支払を行わなければなりません。
そのため、借入金額が大きくて利息の負担も大きい場合には、返済を行っても元本部分の返済がなかなか進まないことがあります。
そこで、任意整理によって将来的に発生する利息をカットすることで、元本部分を着実に返済していくことが可能です。
また、返済期間を長期に設定することで、月々の返済負担を軽減しながら完済を目指すことができる点にも特徴があります。
もっとも、交渉に応じるかは債権者次第であるため、滞納期間が長期にわたる場合やこれまでに何度も滞納している場合には、債権者が交渉に応じない可能性があります。
さらに、任意整理では継続して返済を行う必要があるため、返済を継続できるほどの収入を得る見込みがない場合には、手続を行うことができません。
なお、利息のカットと返済スケジュールの再設定を行っても、月々の返済負担が軽減できないほど残債務の金額が大きい場合には、任意整理が適していないケースもある点に注意しましょう。
任意整理を行うための条件や任意整理を行うことが適していないケースなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。
また、任意整理の対象に含めることができる債務や対象とした場合の影響などについては、以下の記事も参考になります。
(2)個人再生
個人再生は、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、借金の総額に応じて減額された金額を原則3年にわたって返済する再生計画案の認可を受け、その内容に従って返済を行う手続です。
任意整理とは異なり、元本部分まで減額を受けることができるため、返済負担の大幅な軽減につながります。
なお、個人再生を行った場合、返済する借金が減額されるものの、任意整理と同様に返済義務自体の免除を受けられるわけではないので、原則3年(最長で5年)にわたって返済を継続しなければなりません。
また、裁判所を通して行う手続であり、裁判所へ申し立てるためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
加えて、裁判所の関与の元で手続が進行するため、手続中にはいくつかの注意点があることにも注意しましょう。
個人再生を申し立てるための要件や手続の流れなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。
また、個人再生の手続中の注意点については、以下の記事もあわせてご参照ください。
(3)自己破産
自己破産は、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、裁判所から免責許可決定を受けて借金の全ての返済義務を免除してもらう手続です。
任意整理や個人再生とは異なり、返済義務の免除を受けることができるため、債務整理の中でも効果が最も大きい手続といえます。
ただし、一定額以上の財産を所有している場合には、手続の中で換価処分が行われ、債権者に配当が行われてしまうことに注意が必要です。
例えば、20万円以上の価値がある財産(住宅や車、預貯金など)が換価処分の対象となる可能性があります。
また、個人再生と同様に裁判所を介して行う手続であるため、一定の要件を満たさなければ申し立てることができません。
さらに、申立てを行えば誰でも返済義務の免除を受けられるわけではなく、免責不許可事由と呼ばれる事由に該当する場合には、免責を受けられない可能性もあります。
もっとも、免責不許可事由に該当する場合であっても、弁護士に相談の上で手続を依頼することで、裁判所から裁量免責を受けられる可能性を高めることが可能です。
自己破産を申し立てるための要件や免責不許可事由の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
4.債務整理について弁護士に相談・依頼するメリット

カードローンをはじめとする借金の返済が滞った場合には、放置することでさまざまな法的リスクが高まります。
そのため、なるべく早期に弁護士に相談し、債務整理の手続を行うことを検討しましょう。
弁護士に相談することで得られるメリットは、以下のとおりです。
- 無料で専門的なアドバイスを受けることができる
- 債権者からの督促や取立てを止めることができる
- 手続を一任することができる
順にご説明します。
なお、債務整理を行うことを検討すべきタイミングは、借金の返済が滞ったとき以外にもいくつか考えられます。
債務整理の手続を行うことや弁護士への相談のタイミングについては、以下の記事も参考になります。
(1)無料で専門的なアドバイスを受けることができる
弁護士に相談することで、無料で専門的なアドバイスを受けることができます。
特に借金問題や債務整理に関しては、相談料を無料としている法律事務所が多いです。
そのため、債務整理に慣れた弁護士に相談することで、どのような解決方法があるのかについて説明やアドバイスを受けることができます。
先ほど述べたように、債務整理には3つの手続があり、どの手続を選択するのが最適かは、債務者の支払能力や借入額などによって異なります。
また、各手続には条件や要件が設けられており、それらを満たしているかどうかを判断しなければなりません。
弁護士に相談すれば、ご自身の状況ではどの手続を行うことが最適なのかについてアドバイスを受けた上で、債務整理の手続を依頼することが可能です。
(2)債権者からの督促や取立てを止めることができる
弁護士に債務整理の手続を依頼することによって、債権者からの督促や取立てを止めることが可能です。
弁護士に手続を依頼すると、債権者に対して受任通知が送付されます。
受任通知を受け取った債権者は、それ以降債務整理の手続が終了するまで、債務者に対して直接督促や取立てができません。
債権者からの督促や取立てが止まっている間は、返済義務が一時的に停止するため、その間を利用して弁護士費用などの手続に関する費用を捻出することができます。
任意整理や個人再生に関しては、手続終了後は返済義務が再開するものの、それでも一時的に返済が止まることで、生活の立て直しや費用の工面ができ、精神的な負担も軽減される点も大きなメリットの1つです。
(3)手続を一任することができる
弁護士に相談した流れで、手続を一任することもできます。
任意整理であれば債権者と、個人再生や自己破産であれば裁判所を相手にやり取りすることになります。
しかし、債務者ご自身で交渉を行う場合、専門的な知識が求められ、十分な交渉や対応ができない可能性が高く、場合によっては、手続が失敗する可能性もあるのです。
債務整理に慣れた弁護士であれば、それぞれの手続を進めるにあたって、どのような点を押さえておくべきかを熟知しています。
そのため、手続が成功する可能性を高めるとともに、解決に至るまで円滑に進めることができます。
まとめ
カードローンの返済を延滞している場合、そのまま放置すると大きなリスクが生じます。
長期にわたって放置すると、財産の差押えまで発展する可能性もあるため、なるべく早急に対処することが大切です。
まずは、債権者から通知された指定期日までに支払を行い、場合によっては分割払いへの変更など債権者と交渉を行いましょう。
それでも対処が困難な場合には、債務整理を行うことで、返済負担の軽減や免除を受けられる可能性があります。
債務整理には3つの手続がありますが、適切に進めるためには法的知識や経験が求められるため、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、借金に関する相談を無料で受け付けておりますので、カードローンの返済でお困りの方はお気軽にご相談ください。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事