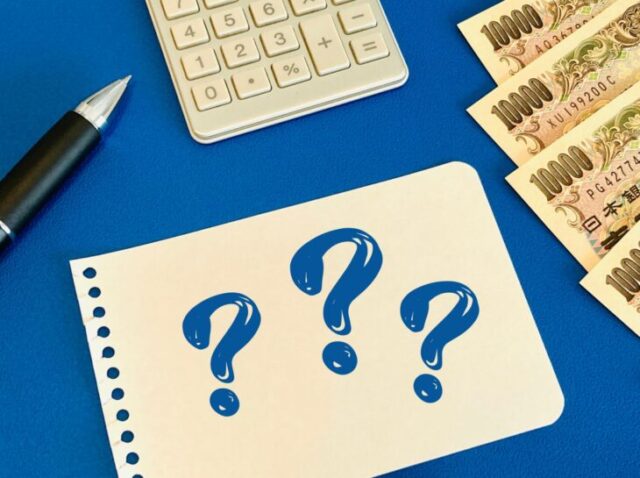交通事故の後から痛みが生じたときの対処法とは?病院を受診した後の流れ

執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「交通事故から数日経って痛みが生じたらどうしたらいいのか」
「すぐに病院に行かないとどうなるのか」
交通事故の被害に遭われた方の中には、事故から数日経って痛みや痺れなどの症状が現れ、どう対応したらいいか困っている方もいるのではないでしょうか。
交通事故が発生して時間が経過した後から徐々に症状が現れることは珍しいことではありません。
そのような場合には、直ちに病院を受診し、必要な検査や治療を行うことが後の賠償問題を有利に進めるためにも大切です。
本記事では、交通事故の後から痛みが生じたときの対処法やすぐに病院に行かないリスク、受診後の流れについて解説します。
- 交通事故に遭った数日後から痛みなどの症状が現れた場合には、速やかに整形外科などを受診して精密検査を受けることが大切
- 何らかの症状が現れても病院を受診しない場合、怪我と事故との因果関係を否定されて治療費などの賠償を受けられないリスクがある
- 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することで、加害者側の保険会社との対応を一任できるだけでなく、示談金の増額も期待できる
1.交通事故の数日後から痛みが生じたときの対処法

交通事故の数日後から痛みが生じた場合には、すぐに病院を受診し、痛みが生じる部位を検査してもらい、診断を受けることが大切です。
痛みが事故によって生じた場合、加害者側に対して治療費や慰謝料などの損害を請求することができます。
もっとも、その請求が認められるためには、事故と痛みとの間に因果関係があることを示す必要があります。
そして、因果関係を示すための資料として診断書が必要となります。
また、事故によって怪我を負ったとしても、事故後、長時間病院に行かないと、怪我が事故によって生じたものではないと判断されてしまう可能性があります。
そのため、軽い痛みの場合でも、事故と症状との因果関係を証明するために、直ちに病院に行き、治療を開始するようにしましょう。
なお、事故のときに頭を打ちつけている場合は、脳内出血を起こしている可能性があるため、脳神経外科を受診し、CT検査やMRI検査を受けておくことを推奨します。
痺れや動かしづらさがある場合にもMRI検査を受けておいた方が良いでしょう。
整形外科を受診する際の注意点などについては、以下の記事も参考になります。
また、怪我の内容や症状に応じて、どの診療科を受診すればよいかについては、以下の記事もあわせてご参照ください。
2.病院に行かないリスク

交通事故の後から痛みが生じても病院に行かない選択をする人がいるかもしれませんが、かなりリスクのある行為です。
痛みが生じた後にすぐ病院に行かないことで、以下のようなリスクが発生します。
- 怪我と事故との因果関係の証明が困難になる
- 症状が重大でないと判断される可能性がある
- 症状が悪化する可能性がある
- 人身事故に切り替えられない
順にご説明します。
(1)怪我と事故との因果関係の証明が困難になる
事故による痛みが生じても、すぐに病院に行かずに事故から数週間経過してしまうと、怪我と事故との因果関係の証明が困難になります。
病院に行くことが遅くなるほど、加害者側から怪我と事故との関係性を疑われやすくなり、加害者側から事故との因果関係を否定されることが多いです。
先ほども述べたように、怪我の治療などに関する費用は、交通事故と怪我との間の因果関係が認められれば加害者側に請求し、補償を受けることができます。
しかし、因果関係を証明できなければ、怪我を負っていたとしても交通事故とは関係がないものと評価されてしまい、本来ならば受け取ることができるはずの賠償を受けられない可能性が高まるのです。
具体的には、事故から1週間~2週間以内に病院を受診していない場合には、事故と怪我との因果関係が否定されやすくなるため、違和感が生じた時点で直ちに整形外科の診療科を受診するようにしましょう。
(2)症状が重大でないと判断される可能性がある
事故によって重症を負った場合、通常は事故直後に病院での治療をするはずです。
つまり、事故によって怪我をしたとしても、事故直後に病院に行かなかった場合、病院に行く必要がない程度の怪我であると判断されてしまう可能性があります。
そのため、事故にあった後はできるだけ早く病院に行くことをお勧めします。
事故後は興奮状態から痛みを感じにくくなるので、病院に行かなくても良いと判断してしまうかもしれませんが、後から痛みが出てくることはよくあることなので、自己判断せずに医師の診断を受けましょう。
(3)症状が悪化する可能性がある
怪我をした場合、適切な治療を受けなければよくなりません。
そのため、治療を開始するのが遅くなるほど、症状が悪化し完治までの期間が長引く可能性があります。
また、完治までの期間が長引くだけでなく、後遺症が残るリスクも否定できません。
後遺症が残ると治療終了後の日常生活にも大きな影響を及ぼし、生活スタイルの変更を余儀なくされる可能性もあるので、早めに治療を開始することが大切です。
(4)人身事故に切り替えられない
交通事故は、人身事故と物件事故の2種類があり、怪我の有無で区別されます。
交通事故が発生すると、当事者に明らかな受傷などがない場合には、警察は物件事故として処理を行います。
物件事故として処理された場合は、簡易的な事故状況が記載された物件事故報告書しか作成されず、事故が発生した状況や事故態様に関する捜査内容をまとめた実況見分調書が作成されないので、示談交渉で活用できる貴重な証拠を入手できなくなります。
実況見分調書は、人身事故として切り替えを申請し、受理されれば作成されることになります。
ただし、人身事故は人的損害が発生していることが前提となるため、医療機関を受診し、医師に診断書を作成してもらえなければ、人身事故の切り替えを行うことができません。
3.病院に行った後の流れ
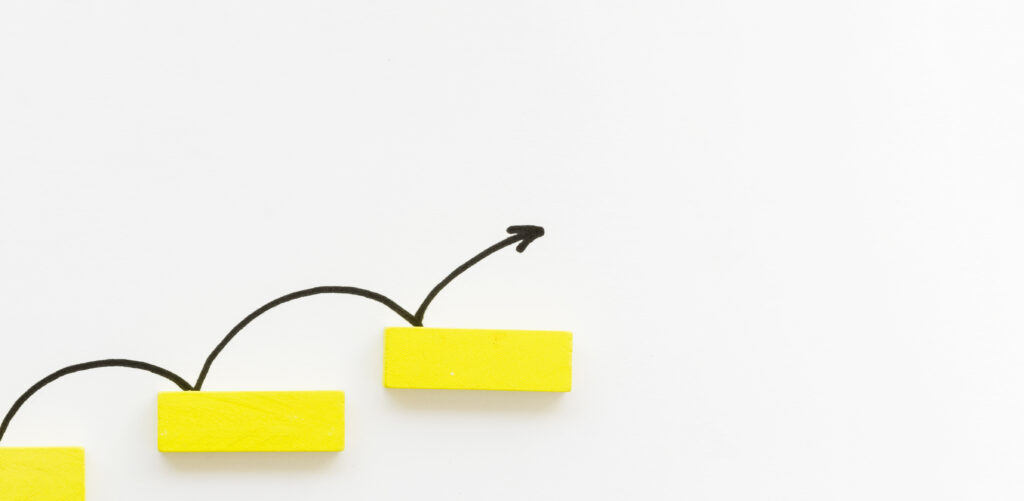
病院に行った後は、いくつかのステップを経て加害者側と示談交渉を行います。
示談交渉までの主な流れは以下のとおりです。
- 治療を開始する
- 医師に診断書を作成してもらう
- 加害者側の保険会社に連絡をする
- 必要に応じて人身事故に切り替える
- 後遺症が残った場合には後遺障害等級の認定申請を検討する
- 認定結果をもとに示談交渉を行う
順にご説明します。
(1)治療を開始する
まずは、完治を目指して治療を開始します。
医師の指示に従い、適切な期間と頻度にわたって通院することが大切です。
適切な通院期間や頻度については、怪我の内容や程度によっても異なります。
そのため、自己判断で通院をやめないことが怪我の治療と適正な賠償金を獲得するためにも重要です。
通院頻度が賠償金に与える影響や注意点などについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
(2)医師に診断書を作成してもらう
治療を開始したら、医師に診断書を作成してもらいましょう。
診断書は、加害者側に賠償金を請求するために必要な書類です。
適正な賠償金を請求するためにも、症状などについて詳細に記載してもらうことが大切です。
なお、診断書の主な記載事項や必要となる場面については、以下の記事も参考になるので、あわせてご参照ください。
(3)加害者側の保険会社に連絡をする
初診後、加害者側の保険会社に治療を開始した旨を連絡しましょう。
加害者側が任意保険に加入している場合には、保険会社が治療費の支払いを行う一括対応が行われることが一般的です。
加害者側の保険会社に連絡をせずに勝手に治療を開始すると、治療費の支払いでトラブルになる可能性があるので、病院に行く前、または初診後に必ず連絡しておきましょう。
(4)必要に応じて人身事故に切り替える
病院に行った後は、必要に応じて人身事故に切り替えましょう。
人身事故として処理が行われる最大のメリットは、実況見分調書が作成されることです。
事故が発生した路面状況や事故態様について詳細な記載がされるため、示談交渉において過失割合を主張・立証する際の資料とすることができます。
そのため、過失割合に争いがある事案で、ドライブレコーダーや防犯カメラなどの客観的な資料に乏しく、適切な過失割合の主張・立証を行うための証拠が不足している場合には、人身事故への切り替えをした方がよいでしょう。
なお、事故から日数が経過し過ぎると、現場の状況が変わり、受理されない可能性があります。
過失割合に争いがあり、客観的資料がない場合、痛みが生じたら、なるべく早い段階で警察に人身事故への切り替えの申請を行いましょう。
切り替えを行う際の手続の流れについては、以下の記事で解説しているので、あわせてご参照ください。
(5)後遺症が残った場合には後遺障害等級の認定申請を検討する
治療を継続したものの、完治せずに症状固定の診断を受けた場合は、残存する症状の内容や程度に応じて後遺障害等級の認定申請を行うことを検討しましょう。
症状固定とは、怪我の治療を一定期間継続したのち、症状が一進一退となって、これ以上治療を継続しても医学的に症状が改善しない状態のことです。
後遺障害等級の認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を受け取ることができます。
手続には後遺障害診断書が必要なので、症状固定の診断を受けるタイミングで医師に作成を依頼しましょう。
後遺障害の意義や手続の流れについては、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご参照ください。
また、後遺障害診断書の作成をしてもらう際の注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(6)認定結果をもとに示談交渉を行う
完治や症状固定の診断を受けたら、診断書や後遺障害等級の認定結果をもとに示談交渉を行います。
示談交渉では、過失割合や示談金について加害者側の保険会社と話し合うのが一般的です。
交通事故の示談交渉では、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つの算定基準が使用されます。
自賠責基準は被害者の最低限の補償を行うことを目的としており、3つの算定基準の中では最も低額です。
また、算定基準が非公開となっている任意保険基準も自賠責基準と同程度か少し上回る基準となっています。
そして、裁判所が使用する裁判所基準は最も高額な基準です。
加害者側の保険会社は自賠責基準か任意保険基準をもとに示談金の提示をしてくることがほとんどです。
弁護士に依頼すれば、裁判所基準によって算定した示談金の請求が可能となり、受け取ることができる示談金の増額が期待できます。
そのため、示談交渉を有利に進めて示談金の増額を図りたい方は、まずは弁護士に相談して、示談交渉の依頼を検討しましょう。
まとめ
交通事故から数日経過して痛みや痺れなどの症状が生じることはあります。
痛みなど何らかの異変を感じたら、すぐに病院に行って検査を受けましょう。
すぐ病院に行かなければ、交通事故と現れている症状との因果関係を証明できなくなり、示談交渉で不利になる可能性があります。
また、症状が悪化したり人身事故への切り替えができなかったりするので、軽度の痛みでもすぐに病院に行くことが大切です。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、交通事故後の対応でお困りの方はお気軽にご相談ください。
交通事故で
こんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、保険会社・相手方とどんな風に対応すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を受けたいけど、後遺障害認定申請や示談交渉などさっぱりわからない・・・

事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。