自己破産の手続に要する期間は?手続ごとの目安や長引いてしまう原因についても弁護士が解説

「自己破産の手続はどのくらいの期間がかかるのか」
「自己破産の手続が長引くのはどういったときなのか」
借金の返済に困っていて自己破産の手続を行うことを検討される中で、このような疑問やお悩みをお持ちの方もいると思います。
自己破産は、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、裁判所から免責許可決定を受けることによって、すべての借金の返済義務を免除してもらう手続です。
そのため、自己破産を行うためには裁判所への申立てが必要であり、手続は法律の定めに従って進められることから、裁判所から最終的に免責許可を受けるまでには1年程度の期間を要することもあります。
もっとも、自己破産の手続にはいくつかの種類があり、どの手続によって事案が処理されるかで手続全体に要する期間が異なってくることに注意が必要です。
本記事では、自己破産の手続に関する期間や手続の流れ等について解説します。
1.自己破産の手続に要する目安期間

自己破産を裁判所に対して申し立てると、債務者の財産の状況や免責不許可事由の有無などによって、手続の種類が裁判所によって振り分けられることになります。
具体的には、以下のいずれかの手続に振り分けられます。
- 同時廃止事件
- 管財事件
手続に要する期間は、どちらの手続に振り分けられるかによって変動します。
なお、免責不許可事由の詳細については、以下の記事もご参照ください。
(1)同時廃止事件
同時廃止事件は、債務者に一定以上の財産がなく、免責不許可事由が存在しないことが明らかなケースで運用がされる手続です。
そのため、財産の換価処分が予定されておらず、免責不許可事由の調査も省略することができるため、破産手続の申立てから免責を受けるまでは3~4か月程度となるのが通常です。
もっとも、手続に必要な書類や資料の作成・収集、費用の準備に時間を要することもあるため、これら手続の準備期間も含めると概ね6か月~1年程度かかることもあります。
同時廃止事件に振り分けられる基準や手続の特徴などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(2)管財事件
管財事件は、債務者に一定以上の財産があり、免責不許可事由がある場合やその有無が明らかでない場合に振り分けられる手続です。
自己破産においては基本となる手続であり、管財事件として処理が図られると、裁判所によって破産管財人が選任される点に特徴があります。
なお、管財事件では、裁判所によっては少額管財事件と呼ばれる運用が行われている場合もあり、通常の管財事件と比較すると目安となる期間に違いが見られます。
管財事件の概要や振り分けられる基準の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
#1:通常管財事件
通常管財事件では、同時廃止事件よりも長い期間を要することが一般的で、申立てから免責許可決定までは概ね4か月~1年程度を要します。
管財事件では、同時廃止事件とは異なり、債務者の財産の換価処分と債権者への配当、免責不許可事由の調査などが予定されており、手続全体が長期化する傾向にあることに注意が必要です。
また、財産が多岐にわたる場合や高額な財産がある場合には、財産の調査と換価処分にさらに時間がかかるケースもあります。
#2:少額管財事件
裁判所によっては、定型的な事案の処理を図ることができるものについては、少額管財事件の運用を行っている場合があり、概ね4~8か月程度で手続が終了することが多いです。
債務者に一定以上の財産がある場合や免責不許可事由の有無が申立時点で明らかでない場合など、振り分けに関する基準は通常管財事件と共通するものが多いです。
もっとも、少額管財事件の運用を行っている裁判所では、振り分けられる基準として弁護士に手続を依頼していることを前提としています。
弁護士に手続を依頼することによって、事案の見通しなどが整理されることで、手続が簡略化されることが手続に要する期間が短縮されている主な理由です。
少額管財事件の特徴やメリットなどについては、以下の記事もあわせてご参照ください。
2.同時廃止事件の流れ
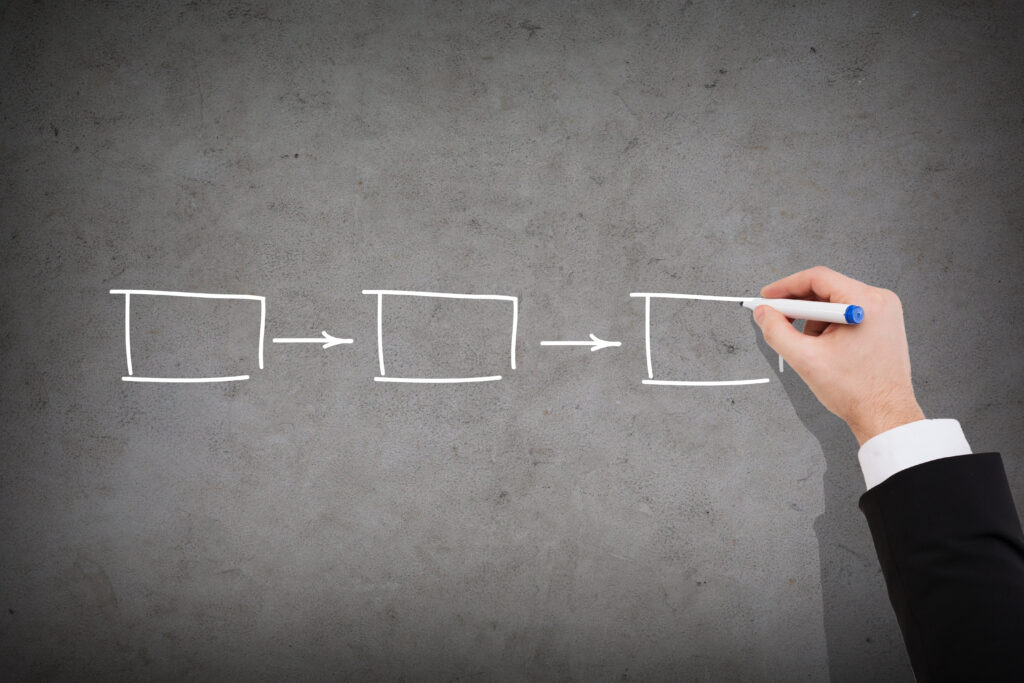
同時廃止事件では、管財事件の場合とは異なり、債務者の財産の換価処分と債権者への配当が予定されていません。
また、破産手続開始決定と同時に手続が廃止(終了)となる点にも特徴があります。
具体的には、以下の流れで手続が進行するのが一般的です。
- 弁護士に相談・依頼
- 受任通知の送付・申立準備
- 破産手続開始申立て
- 債務者審尋または即日面接
- 破産手続開始決定・廃止決定
- 意見申述期間
- 免責審尋・免責許可決定
順にご説明します。
(1)弁護士に相談・依頼
自己破産を行うことを検討されている場合には、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
自己破産をはじめとする債務整理の手続に関しては相談料を無料としている法律事務所が多くあります。
そのため、弁護士から無料で専門的なアドバイスやサポートを受けることが可能です。
また、自己破産は裁判所を通して行うため、手続を行うための要件を満たす必要があるほか、申立ての際に提出する資料も多岐にわたります。
弁護士に相談することで、これらについても丁寧な説明を受けることができ、不安や悩みを解消することができるのもメリットです。
さらに、相談後にそのまま手続を依頼することもできるため、破産に向けてスムーズに手続を進めていくことができます。
なお、自己破産について弁護士に相談・依頼するメリットについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
(2)受任通知の送付・申立準備
弁護士に自己破産の手続を依頼すると、弁護士から債権者に対して受任通知が送付されます。
債権者が受任通知を受け取ると、それ以降は債務者に対して直接督促や取立てを行うことが禁止されます。
受任通知が送付されると、一時的に督促や取立てが停止し、返済がストップするので、債務者はこの間を利用して、自己破産の申立てを行う準備を進めることになります。
準備として、弁護士のサポートを受けながら申立書類の作成や添付資料の収集を行うのが一例です。
例えば、必要となる申立書類や添付資料には、以下のようなものがあります。
- 自己破産申立書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 給与明細
- 源泉徴収票 など
このうち、申立書類の作成については、弁護士に一任することができるため、アドバイスやサポートを受けながら添付資料の収集を行うことが中心です。
なお、弁護士に依頼をして自己破産を行うためには、弁護士費用や裁判所へ納付する費用が必要となります。
弁護士費用や裁判所へ納付する費用の支払いができないと、自己破産手続を進めることができなくなってしまうため、返済がストップしている間に必要な費用を積み立てることが大切です。
自己破産の申立てに必要な書類と添付資料については、以下の記事もご覧ください。
また、自己破産の費用を捻出するための対処法については、以下の記事も参考になります。
(3)破産手続開始申立て
申立書類と添付資料の準備ができれば、これらを裁判所に提出することによって破産手続開始の申立てを行います。
この際に、手続に必要な裁判所費用を納付するため、必要な費用を準備しておかなければなりません。
(4)債務者審尋または即日面接
申立てを行った後は、裁判所から申立書類の内容について質問や面接が行われる場合があります。
基本的にこの面接は弁護士が対応します。
もし、手続を弁護士に依頼している場合でも、裁判所から呼び出しを受けた場合には必ず債務者本人が出廷して応じなければならないことに注意が必要です。
なお、東京地裁では審尋に代えて、申立ての当日か遅くとも3日以内に「即日面接」という期日が設けられ、この期日では裁判官と代理人弁護士との間で今後の手続の流れなどについて打ち合わせが行われます。
(5)破産手続開始決定・廃止決定
申立書類や添付資料に不備がなければ、裁判所から破産手続開始決定が出されます。
同時廃止事件として処理された場合には、開始決定と同時に手続の廃止(終了)決定が同時に出される点が大きな特徴です。
なお、即日面接の結果、同時廃止事件として処理されることが決定した場合には、即日面接の当日に破産手続開始決定と廃止決定が出されることもあります。
(6)意見申述期間
手続の廃止(終了)決定が出された後には、裁判所は債権者に対して意見申述の期間を設定します。
これは、債権者が自己破産の手続に対して意見を述べる機会を保障するものであり、2か月程度の期間が設けられるのが一般的です。
この期間中に債権者が意見や異議を述べた場合には、後述する免責審尋において債務者に免責を与えるかどうかの判断を行う際に参考とされます。
ただし、同時廃止事件は債務者に免責不許可事由に該当する事情が存在しないことが明らかな場合に振り分けられるため、債権者が意見を述べたとしても免責不許可決定が出されることはほとんどありません。
また、債権者から反対意見が出されることもほとんどないでしょう。
(7)免責審尋・免責許可決定
裁判所から指定された期日に免責審尋が行われます。
免責審尋には、債務者本人と弁護士が一緒に出席します。
免責審尋では、債務者本人に対して、以下の事項のうちいくつかについて質問、確認が行われるのが一般的です。
- 氏名や住所などの基本的な情報
- 破産に至った経緯
- 免責制度の趣旨を理解しているかどうか
- 債権者に迷惑をかけたことについてどのように考えているか
- 生活再建へ向けた意思
- 免責不許可事由の有無
実際の免責審尋はごく短時間の確認で終わるものの、聞かれたことに対して正直に答えることが求められます。
同時廃止事件の場合は、免責審尋を経て、そのまま免責許可決定が出されることがほとんどです。
3.管財事件の流れ

管財事件は、債務者に一定額以上の財産がある場合などに振り分けられる手続です。
手続の中で財産の換価処分と債権者への配当が予定されているため、手続が同時廃止事件と比べて複雑になります。
具体的な流れは以下のとおりです。
- 弁護士に相談・依頼
- 受任通知の送付・申立準備
- 破産手続開始申立て
- 債務者審尋または即日面接
- 破産手続開始決定・破産管財人の選任
- 財産調査・換価処分
- 債権者集会・配当
- 免責許可決定
順にご説明します。
(1)弁護士に相談・依頼
まずは、弁護士に相談し依頼することから始めましょう。
自己破産の手続は、債務者本人が行うことも可能ですが、債務者ご自身が手続の申立てを行ってしまうと、通常管財事件として処理され、手続が長期化する可能性があります。
また、知らないうちに不適切な対応を行ってしまい、後の免責許可に影響を及ぼすリスクもあるのです。
そのため、弁護士に相談の結果、管財事件として処理がなされる見通しであったとしても、手続を弁護士に依頼する方がスムーズな解決を目指すことができます。
また、裁判所によっては少額管財事件の運用を行っている場合もあるため、運用の有無も含めて弁護士に相談することが大切です。
(2)受任通知の送付・申立準備
弁護士に依頼することで、債権者に対して受任通知を送付します。
債務者ご自身で手続を行った場合には、弁護士からの受任通知が作成・送付されないため、債権者からの督促や取立てを止めることができない点に注意が必要です。
なお、一定以上の財産がある場合には、不動産や車、預貯金などについての資料も収集しなければなりません。
そのため、書類作成や資料収集に時間を要する可能性があることも考えておきましょう。
(3)破産手続開始申立て
同時廃止事件と同様に、申立書類や添付資料を裁判所に提出することによって、破産手続開始の申立てを行います。
この時点で裁判所に費用を納付する必要がある点は同時廃止と同じです。
もっとも、管財事件の場合には裁判所によって破産管財人が選任されるため、その管財人の報酬についても債務者が負担しなければなりません。
そのため、同時廃止事件の場合と比較すると、予納金が高額になる点に注意が必要です。
予納金の相場については、以下の記事も参考になります。
(4)債務者審尋または即日面接
申立ての後、債務者審尋または即日面接が行われることがあります。
即日面接が行われる際には弁護士が対応するため、債務者が出席する必要はありません。
ただし、債務者本人が出廷する必要はないものの、この面接で管財事件か同時廃止事件の振り分けが決められるため、重要な期日といえます。
(5)破産手続開始決定・破産管財人の選任
債務者審尋や即日面接の結果、管財事件に振り分けられた場合には、裁判所が破産管財人を選任します。
破産管財人は、債務者の財産を調査・管理し、それらを適正価格で換価した上で債権者に配当を行う役割を担っています。
そのため、破産管財人が選任されると、この時点で債務者の財産の管理は破産管財人が引き継ぐことになることに注意しましょう。
破産管財人の概要や手続で果たす役割などについては、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご参照ください。
(6)財産調査・換価処分
破産管財人は、債務者の生活に必要な一定の範囲の財産(自由財産)を除いたあらゆる財産について調査・管理を行います。
先ほども述べたように、破産管財人は債務者の財産を適正価格で換価し、債権者へ配当する役割を担っているのが特徴です。
さらに、債権者への配当の原資を確保して、その価値を維持・増加させる責務も負っています。
そのため、債務者が不当に配当原資から流出させた財産がある場合には、破産管財人はこれを債務者の手元に回復させるための「否認権」という権利を行使することが可能です。
否認権が行使される対象の行為としては、債務者が財産を売却・譲渡することで配当原資を減少させる行為や特定の債権者のみに返済や担保の供与を行う行為などが挙げられます。
否認権の意義や行使される具体的なケースについては、以下の記事でも解説しています。
(7)債権者集会・配当
債権者集会では、破産管財人が行った財産調査や換価処分の結果が裁判所に報告されます。
調査の結果、債権者に配当できるほどの財産がある場合には、配当の手続が行われます。
また、債権者集会には債務者本人も出席する義務があり、出席した債権者から質疑などがあればこれに答えなければなりません。
もっとも、債権者が実際に出席するケースはほとんどなく、10分程度で終了することも多いです。
なお、管財事件では、通常、債権者集会に続いて免責審尋が行われます。
免責審尋も債権者集会と同様に債務者は出席する義務を負い、裁判所や破産管財人の質問に対応しなければなりません。
同時廃止事件と同様に主に簡単な事項についての質問・確認で終わることが多いものの、聞かれたことに対しては誠実かつ正直に答えることが大切です。
(8)免責許可決定
免責審尋の内容を踏まえて、裁判所が以下のいずれかに該当すると判断した場合には免責許可決定が下されます。
- 免責不許可事由がない場合
- 免責不許可事由があるものの免責を与えてよいと判断した場合
免責不許可事由とは、借金の返済義務免除が認められなくなる事由のことであり、破産法に定められています。
具体的には、以下のような事由です。
- 借金の主な原因が浪費やギャンブルによること
- 特定の債権者のみに返済を行ったこと(偏頗弁済)
- 換金行為を行ったこと
- 財産の隠匿・処分を行ったこと
- 債権者一覧表に虚偽の記載を行ったこと
- 裁判所や破産管財人に対して虚偽の説明を行ったこと・説明を拒否したこと など
もっとも、これらの事由に該当していても、債務者が真摯に反省し、更生の余地があると裁判所が判断すれば、免責を受けられる裁量免責という制度があります。
実際には裁量免責によって免責を受けられるケースがほとんどであり、これらの事由に該当していたとしても、諦めずに弁護士に相談し、対策を行うことが大切です。
裁量免責を受けるためのポイントや注意点などについては、以下の記事も参考になります。
4.自己破産の手続が長期化する可能性がある要因

自己破産は、上記のようにどの手続に振り分けられるかによって手続全体に要する期間は異なります。
また、以下のような事情がある場合には、さらに手続が長期化する可能性もあるため、注意が必要です。
- 債務者自身で申立てを行っている
- 申立書類や添付資料に不備がある
- 所有する財産の価値が高い
順に見ていきましょう。
(1)債務者自身で申立てを行っている
自己破産の手続を債務者自身で行っている場合は、手続が長期化する可能性があります。
先ほども述べたように、自己破産の申立ては債務者本人が行うこともできます。
もっとも、裁判所や債権者とのやりとりが必要となる局面でも債務者ご自身がすべて対応しなければならないため、知識や実務経験がない場合には、その対処がスムーズに進められず、手続が滞ってしまう可能性があります。
また、手続を弁護士に依頼した場合には、弁護士から受任通知が送付され、債権者からの督促や取立てが停止するものの、債務者本人が手続を行う場合には債権者からの督促などを止めることはできません。
そのため、債権者からの対応と自己破産の申立ての準備を並行して行わなければならず、精神的負担も大きいといえるでしょう。
また、不適切な対応を行ったことによって免責が認められなくなってしまうリスクもあります。
自己破産の手続きを円滑に進めていくためには、弁護士に相談することが望ましいです。
(2)申立書類や添付資料に不備がある
提出した申立書類や添付資料に記載漏れなどの不備がある場合には、裁判所から補正や再提出・追加提出などを求められるため、その分期間が延びる可能性があります。
書類を書き直したり、不足していた資料を追加で取得したりすることで、手続の進行に影響を及ぼすことがあります。
特に債務者ご自身で手続を行う場合には、どのような書類を準備するのかをよく調べる必要があるでしょう。
なお、資料によっては、取得の時期に条件がついているものがあります。
具体的には、給与明細書や家計収支表などは、直近2か月分について作成しておかなければなりません。
ほかの申立書類や添付資料の作成・収集に時間を要し、上記のような期間を徒過したものについては、再度作成や収集を行わなければならなくなるため、さらに手続が遅延する可能性もありますので予め段取りをつけていくことが重要です。
(3)所有する財産の価値が高い
所有する財産の価値が高い場合には、財産調査や換価処分に時間を要するため、手続が長期化する可能性が生じます。
また、財産の換価処分が終わらない場合には、複数回にわたって債権者集会が開かれることもあります。
5.自己破産の申立てについて弁護士に相談・依頼するメリット

自己破産の手続に要する期間は、同時廃止事件か管財事件のどちらの手続に振り分けられて処理が図られるかによっても変動します。
しかし、どちらの手続によって処理が図られるかは知識や実務経験がなければ判断が難しいことも多いです。
そのため、自己破産の手続について、どちらの手続になりそうかの見通しをつけて準備を進めるためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
具体的に、弁護士に相談・依頼するメリットは以下のとおりです。
- 手続の見通しについて説明を受けることができる
- 書類作成や資料収集についてサポートを受けることができる
- 予納金を低く抑えて手続を行える可能性がある
順にご説明します。
(1)手続の見通しについて説明を受けることができる
弁護士に相談することで、手続の見通しについて説明を受けられる点がメリットです。
上で述べたように、自己破産の手続には同時廃止事件と管財事件の2種類があり、どちらの手続に振り分けられるかで、その後の流れが変わります。
弁護士に相談することで、債務者の方の借金の経緯や財産の状況などを確認し、どちらの手続に振り分けられる可能性が高いのか、手続のどこの問題の対応に時間がかかる見通しなのかをあらかじめ把握することができます。
そのため、相談の段階から手続の見通しや大まかな期間などについて具体的な説明を受けることができ、不安やお悩みの解消につながります。
(2)書類作成や資料収集についてサポートを受けることができる
弁護士に依頼することで、手続に必要な書類作成や資料収集について任せることや、サポートを受けることができます。
スムーズに手続を進めるためには、必要な書類を不備なく揃えることが必要です。
ご自身で手続を行った場合、どのような申立書類を作成し、どのような資料が必要となるのか判断に迷う場合もありますが、弁護士に相談・依頼することで申立書類の作成を任せ、必要となる資料の収集についてサポートを受けることができます。
(3)予納金を低く抑えて手続を行える可能性がある
弁護士に手続を依頼することで、管財事件に振り分けられる場合でも、予納金を低く抑えて手続を行うことができる場合があります。
通常の管財事件では、50万円近い予納金を納めなければならない場合がありますが、弁護士に依頼して申し立てることによって、内容の整理が図られていると裁判所に判断されて予納金が20万円程度に抑えられる可能性があります。
まとめ
自己破産は、どの手続に振り分けられるかで免責許可決定までの期間が変わります。
また、所有している財産の価値が高い場合や、申立書類や添付資料にに不備、不足がある場合には、手続期間が長期化する可能性が生じます。
自己破産をスムーズに進めるためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
また、弁護士に破産手続を依頼することで、書類作成や資料収集に関するサポートを受けたり、裁判所や破産管財人への対応を任せたりできるため、円滑に手続を進めて負担を減らすことができます。
弁護士法人みずきでは、自己破産に関する相談を無料で受け付けておりますので、破産手続を行うことに不安やお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事





























