自己破産で免責許可がおりなかった場合の影響は?主な原因と対処法について弁護士が解説

「自己破産で免責許可がおりなかったらどうすることもできないのか」
「自己破産で免責許可がおりない原因は何なのか」
自己破産を行うことを検討されている方の中には、免責許可決定が出されるかどうか、不安に思っている方もいると思います。
自己破産には、借金の返済義務の免除を受けることができる点に大きなメリットがありますが、そのためには裁判所から免責許可決定を受けることが必要です。
そして、どのような借金でも必ず免責を受けることができるというわけではなく、また、一定の事由がある場合には免責許可決定がされないこともあるため、注意が必要です。
本記事では、免責が受けられなかった場合の影響やその原因、対処法などについて解説します。
1.免責許可決定がおりなかった場合の影響

自己破産で免責許可決定がおりなかった場合、借金の返済義務の免除を受けられなくなります。
自己破産は、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、一定以上の価値のある破産をした人の財産を債権者に分配した上で、裁判所から免責許可決定を受けて借金の返済義務を免除してもらう手続です。
そのため、破産手続の申立てをするだけではなく、裁判所から免責許可決定を受けることではじめて借金の返済義務を免れることができます。
破産法に定められている免責不許可事由に該当する事実がある場合には、免責を受けることができないとされています。
免責不許可事由があると判断されれば、自己破産を行ったとしても、借金の返済義務は免除されず、引き続き返済を行わなければならなくなってしまう可能性があるのです。
もっとも、免責不許可事由がある場合に必ず免責を受けられないというわけではありません。
免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が自身の判断で免責決定をする「裁量免責」という制度があるからです。
具体的には、返済できないほどの借金を負ってしまったことを真摯に反省し、更生の余地があると裁判所が判断した場合には、裁量免責を受けられる可能性があります。
そのため、免責不許可事由に該当する行為を行ってしまったとしても、まずは弁護士に相談の上で裁量免責を受けられる可能性があるかどうかについて説明を受けることが大切です。
2.主な免責不許可事由

免責不許可事由に該当する事実については、破産法252条に定められています。
主な該当項目は以下のとおりです。
- 財産を隠匿・処分すること
- 特定の債権者のみに返済を行うこと(偏頗弁済)
- 換金行為を行うこと
- 借金の主な原因が浪費やギャンブルにあること
- 債権者一覧表に虚偽の記載を行うこと
- 裁判所や破産管財人に虚偽の説明を行ったり業務を妨害したりすること
- 免責許可決定を受けてから7年が経過していないこと
なお、免責不許可事由以外にも、自己破産の手続中には避けるべき行為がいくつかあります。
詳細については、以下の記事も合わせてご覧ください。
(1)財産を隠匿・処分すること
自己破産の手続前に財産を隠匿・処分することは免責不許可事由とされています。
破産手続を申し立てた場合、債務者が所有している一定以上の財産については手続の中で換価処分が行われ、債権者に平等に配当が行われます。
具体的には、33万円以上の現金、20万円以上の預貯金、保険の解約返戻金、自動車、装飾品などで、かつトータル99万円を超える部分は換価処分の対象となる可能性があります(裁判所により扱いは多少異なります。)。
財産を隠したり処分したりすると、換価処分の対象となる債務者の財産が減少することになり、債権者の利益が不当に害されることとなります。
そのため、このような行為は破産手続の中では問題があるため、免責不許可事由とされているのです。
なお、悪質性が高いと裁判所が判断した場合には、免責許可を受けられないだけでなく、刑事罰を科されることもあるため注意しましょう。
(2)特定の債権者のみに返済を行うこと(偏頗弁済)
特定の債権者のみに返済すること(偏頗弁済)も、免責不許可事由として、禁止されています。
自己破産の手続は、すべての債権者を平等に扱う「債権者平等の原則」という考えに基づいて進められます。
偏頗弁済は、この原則に反する行為であるため、免責不許可事由とされているのです。
自己破産の免責の対象となるのは、税金などの一部を除くすべての債務です。
このような免責の対象となる債務について、ほかの債権者に優先して返済する行為は禁止されることになります。
例えば、友人や親族からの借金を優先的に返済するような行為です。
また、住宅や車のローンの残債がある場合には、自己破産を行うことによって、住宅が競売されたり車が所有権留保に基づいて引き上げられたりしてしまいます。
このような不利益を避けるために、ローンの残債のみを返済してしまう行為も偏頗弁済にあたります。
なお、自己破産を行うことによって、住宅や車にどのような影響が生じるかは、以下の記事も合わせてご参照ください。
(3)換金行為を行うこと
クレジットカードを利用して購入した商品をすぐに廉価で売却する行為(換金行為)も免責不許可事由とされています。
このような換金行為を行っても、手元に入るお金はもとの金額よりも減少していることがほとんどであるため、かえって財産を目減りさせることにつながります。
財産を目減りさせると債権者の利益が害されますので、破産手続の中では不利益に取り扱われることになります。
その場しのぎのために換金行為を繰り返しても、借金が膨らむことにしかなりませんので、免責のことを考えずとも慎むべきでしょう。
なお、クレジットカードを利用した換金行為のリスクについては、以下の記事でも解説しています。
(4)借金の主な原因が浪費やギャンブルにあること
借金の主な原因が浪費やギャンブル等の射幸行為であった場合には、免責不許可事由に該当し、免責を受けられない可能性があります。
もっとも、借金の総額に対してどの程度の割合を占めているかなどの事情によっても免責不許可事由にあたらないケースもあるため、必ずしも免責許可が下りないわけではありません。
しかし、浪費やギャンブルによる借金であることを隠したりした場合には、裁判所から免責を受けられない可能性が高まるため、注意が必要です。
自己破産において、浪費やギャンブルと受け取られかねない行為については、以下の記事も合わせてご参照ください。
(5)債権者一覧表に虚偽の記載を行うこと
債権者一覧表に虚偽の記載を行うことも免責不許可事由にあたります。
自己破産を行う際には、債権者の情報をすべて記載した債権者一覧表を裁判所に提出しなければなりません。
このとき、故意に債権者一覧表に虚偽の記載をすると、免責不許可事由に該当してしまいます。
また、債権者一覧表に記載しなかった債務については、過失がなく記載できなかった場合を除いて免責の対象とはならず、返済義務が残ってしまいます。
そのため、債権者一覧表を作成する場合には、意図的に特定の債権者を記載しないことはもちろん、抜けや漏れなく債権者を申告するようにしなければなりません。
特定の債権者を申告しないことによるデメリットについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
(6)裁判所や破産管財人に虚偽の説明を行ったり業務を妨害したりすること
自己破産の手続の中では、裁判所や破産管財人から調査として質問を受けたり面談を要請されたりすることが多くなります。
債務者はこの調査に協力する義務があり、虚偽の説明や業務の妨害をすると免責を受けられない場合があります。
免責許可決定をしてもらうためには、裁判所や破産管財人に対して誠実に対応することが大切なので、協力を求められたときは素直に応じるようにしましょう。
破産管財人の役割や選任された場合の注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(7)免責許可決定を受けてから7年が経過していないこと
自己破産は、何度でも行うことができるものの、前回の免責許可から7年以内に申立てが行われた場合には、免責を受けられない可能性が高いです。
これは、前回の自己破産から時間を空けずに再び免責を認めてしまうと、債権者の利益を著しく害してしまうことが理由となっています。
また、過去7年以内に別の債務整理手続である個人再生のうち、給与所得者等再生手続を行っていた場合も、免責不許可事由とされているため注意が必要です。
2回目の自己破産の手続に関する要件や注意点などについては、以下の記事もご覧ください。
3.免責不許可に対する即時抗告の流れ
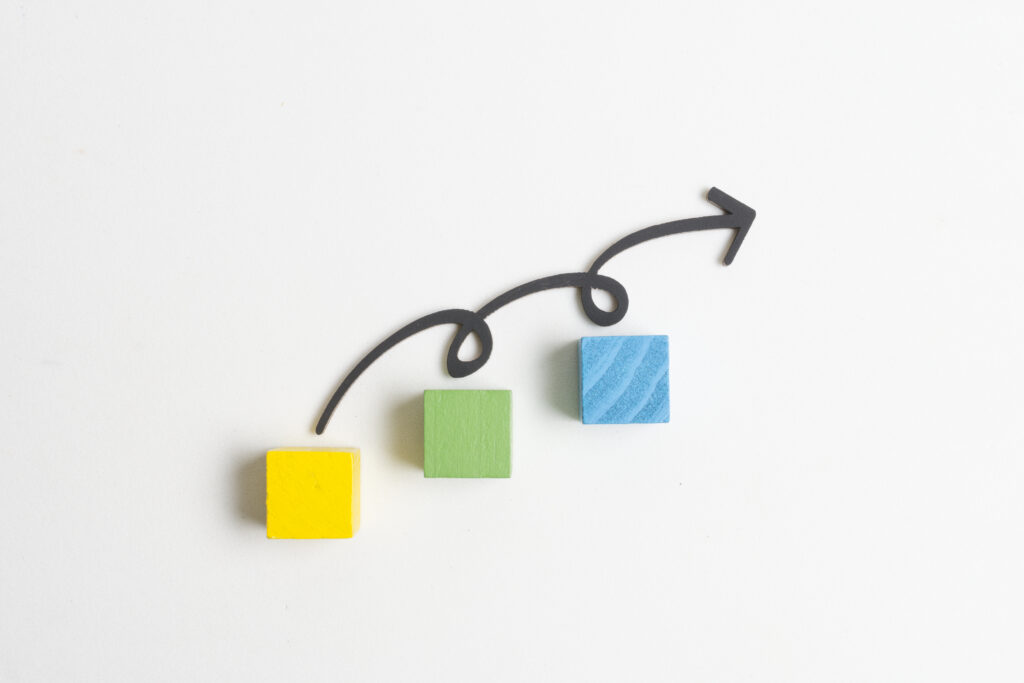
免責不許可となった場合には、異議申立て手続として、即時抗告という手続が用意されています。
これにより、判断が覆る可能性がありますが、そのハードルはかなり高いものとなっています。
即時抗告の流れは以下のとおりです。
- 即時抗告の申立て
- 審理
- 認容または棄却の決定
順にご説明します。
(1)即時抗告の申立て
まずは、即時抗告を申し立てます。
申立ては、管轄の高等裁判所宛の抗告状を、免責不許可の決定をした裁判所に対して提出することによって行います。
書面の宛先と提出先が異なる点に注意が必要です。
また、即時抗告を申し立てる場合には、免責不許可決定の通知がなされた日から1週間以内に行わなければなりません。
抗告状には免責許可が相当である理由を記載しなければならず、大きく分けると以下のどちらかを記載することになります。
- 免責不許可事由が存在しない
- 免責不許可事由は存在するものの裁量免責をすることが相当である
ただし、どのような記載をすべきか判断が難しいことも多いため、即時抗告を行う際には、弁護士に相談の上で手続を依頼することが重要です。
(2)審理
即時抗告の申立てを行うと、高等裁判所での審理が行われます。
審理では、自己破産の申立てに至った経緯や事情などを考慮した上で、免責不許可決定が適切であったかどうかが判断されます。
(3)認容または棄却の決定
審理ののち、認容または棄却の決定がされます。
申立てに基づき、免責許可を与えることが相当であると判断されれば、認容の決定が出されますが、冒頭に触れたように判断が覆されるためのハードルは高いものとなっています。
免責不許可事由に該当する場合であっても、裁量免責の制度によって、ほとんどの場合には免責されています。
そのため、免責を受けられないケースは実際はそれほど多くなく、特に悪質性の高いものに限って免責不許可決定がされているという実態があります。
そのため、即時抗告においても悪質性が重視され、判断が変わらないことが多いのです。
したがって、免責不許可決定を受けてしまった場合は、よほどのことがない限り、自己破産以外の債務整理の手続を行うべきということになります。
4.免責不許可となってしまった場合の対処法

免責不許可決定がされてしまった場合は、即時抗告を行っても決定が覆らないことが多いです。
したがって、このような場合には、別の手続を行うことを検討しましょう。
具体的な手続は、以下のとおりです。
- 個人再生を行う
- 任意整理を行う
なお、2つの手続の違いについては、以下の記事も参考になります。
(1)個人再生を行う
個人再生は、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、借金総額に応じて決まった割合で減額した金額を原則3年(最長で5年)にわたって返済を行う旨の再生計画の認可を受けて返済を行う手続です。
自己破産と同じく裁判所を介して行う手続であり、自己破産を行うことが難しい場合にとられることが多い傾向があります。
個人再生では、借金の理由に関しては問題とされず、免責不許可事由にあたるような行為を行っていたとしても、借金の減額を受けることができる点がメリットです。
また、財産については換価処分が行われることはないため、資産価値の高い財産を手元に残しながら手続を行うことができるのも大きな特徴といえます。
もっとも、自己破産とは異なり、減額された金額については返済する義務が残るものであり、借金の返済義務自体がなくなるわけではありません。
そのため、その金額を一定期間で返済できるだけの安定した収入がない場合には、個人再生を行うことができないことになってしまいます。
また、住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超える場合にも個人再生を行うことができません。
個人再生の手続の概要や手続を行うための要件については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
(2)任意整理を行う
任意整理は、将来的に発生する利息のカットと返済スケジュールの再設定(おおむね5年での分割払い)を債権者と直接交渉し、合意に基づいて返済を行う手続です。
借金の返済を行う際には、元本に合わせて利息も支払わなければならず、利息の負担が大きい場合にはなかなか元本部分の返済が進まないことがあります。
そのような場合には、任意整理で将来利息のカットと長期分割返済を合意することにより、月々の返済負担を減らし、着実に完済を目指すことが可能となることがあります。
この任意整理の場合にも借金の原因を問われることはありません。
そのため、免責不許可事由に該当する場合であっても手続を行うことができます。
しかし、任意整理を行うことができるかは債権者次第で、債権者が交渉に応じない場合には、手続を行うことができません。
また、個人再生と同様に一定期間は継続的に返済を行う必要があるので、安定した収入がない場合には手続を行えない可能性があります。
おおむね5年を目安として返済を行うため、借金の額が60回分割で完済できないほど大きい場合は、任意整理での解決には適していないといえるでしょう。
任意整理を行うための条件や行うことが適していないケースなどについては、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
5.弁護士に相談するメリット

自己破産をはじめとする債務整理の手続を行うことを検討されている方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
特に自己破産を行う際には、上記で解説したように、免責不許可事由に該当する場合に免責を受けられない可能性があります。
また、裁量免責を受けることができるようなケースであっても、知らないうちに不適切な対応を行って免責が受けられなくなってしまうこともあります。
自己破産手続を円滑に進めるためには、弁護士に相談の上で手続を依頼することが最も大切です。
弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。
- 免責を受けられる可能性があるかについて説明を受けることができる
- 裁量免責を受けるためのアドバイスやサポートを受けられる
順にご説明します。
(1)免責を受けられる可能性について説明を受けることができる
自己破産を行うことを検討されている場合には、弁護士に相談することで、免責を受けられる可能性があるかについて説明を受けられます。
たとえ、借金の原因が免責不許可事由に該当する場合でも、悪質なものといえなければ、裁量免責を受けられる可能性があります。
しかし、どのような事情があれば裁量免責を受けられる可能性があるかについては、実務経験がなければ判断が難しいことが多いです。
債務整理の手続に慣れた弁護士に相談することで、実務経験に基づいた的確なアドバイスを受けることができます。
(2)裁量免責を受けるためのアドバイスやサポートを受けられる
弁護士に相談し、手続を依頼することで、裁量免責を受けるためのアドバイスやサポートを受けることができます。
裁量免責を受けるためには、返済しきれない借金を負った経緯などについて真摯に反省し、更生の余地があると裁判所に判断してもらうことが大切です。
また、裁判所や破産管財人への対応も裁量免責を受けるためには重要です。
実務経験が豊富な弁護士であれば、裁判所とのやり取りの際に気を付ける点を把握しているため、適切な対応を行うことが可能になります。
弁護士のアドバイス等をもとに行動することで、裁量免責の確率を高めることにもつながります。
まとめ
自己破産の申立てを行っても、借金の理由や債務者への対応によって免責許可がおりないケースもあります。
免責許可がおりなければ、借金の返済義務を免れることはできず、返済義務が残ってしまうことに注意が必要です。
免責を受けられなかった場合には、状況に応じてほかの債務整理の手続を行うなど、まったく解決策がないわけではありません。
しかし、それよりも重要なのは、手続を申し立てる時点から免責を受けるための対策を行うことです。
免責不許可事由があり裁量免責を受ける必要がある場合、裁量免責を受けられるかどうかについては専門的な知識や実務経験が求められるため、ご自身で判断するのではなく、一度弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、自己破産に関するお悩みを抱えている方はお気軽にご相談ください。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事































