フランチャイザーである本部が破産したら加盟店はどうなる?FC契約は継続できるのか

この記事の内容を動画で解説しております。
あわせてご視聴いただければと思います。
「フランチャイズ本部が破産したら加盟店との契約はどうなるのか」
「フランチャイズ本部が破産してもフランチャイズ契約を継続できるのか」
フランチャイズ契約を結んでいるフランチャイズ加盟店のオーナーの中には、フランチャイザー(フランチャイズ本部)が破産したらどうなるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、フランチャイズ本部が破産した場合のフランチャイジー(加盟店)への影響などについてご紹介します。
1.フランチャイザーが破産したら

フランチャイズ本部が破産したからといって、必ずしもフランチャイズ契約が終了するわけではありません。
フランチャイズ本部が破産した場合、裁判所から選任された破産管財人が本部の権利について管理処分権を有することになります。その管財人が、加盟店との間を契約をどうするのか判断し、加盟店とやり取りをしていくことになります。
そのため、破産管財人がフランチャイズ契約を継続すると判断すれば、フランチャイズ加盟店もこれまでのように本部の指導援助、商品等の提供をうけながら店舗運営を行うことができます。
他方で、破産管財人がフランチャイズ契約の解約を選択すれば、本部から指導援助、商品等の提供を受けられなくなります。
また、加盟店からは破産管財人に対して、相当の期間内にフランチャイズ契約を解約するのか、解約をしないで契約を継続するのか等回答を催告することができます。
もし期間内に回答がない場合は、自動的にフランチャイズ契約が解除されたとみなされることになります。
本部が破産した際は、加盟店にフランチャイズ契約を解約するかどうか選択できる権限はなく、破産管財人の判断に従うことになる点を押さえておきましょう。
2.フランチャイズ契約が継続される場合

破産管財人がフランチャイズ契約を継続すると判断した場合は、基本的には本部の破産手続開始前と変わらず加盟店は本部からのノウハウや商品の提供を受けながら営業することができます。
もし契約継続が選択された後に加盟店から本部に対して債権が生じた場合は、優先的に支払いを受けられる権利として扱われます。
なお、破産管財人が破産する本部のフランチャイズ事業全体を事業譲渡という形で換価する方が良いと判断した場合は、譲り受ける候補者を選定し、本部のフランチャイズ事業全体を事業譲渡することもあります。
その場合は、破産を申し立てた本部に代わって、新たな経営者がフランチャイズ本部の事業譲渡を受け、加盟店とのフランチャイズ契約の関係を継続していくことになります。
加盟店の立場からすると、フランチャイズのシステムは維持されたまま、本部の経営主体が事業譲受人に引き継がれ、フランチャイズ契約の効力も新事業主に引き継がれるため店舗の運営に大きな影響はありません。
3.フランチャイズ契約が解除される場合
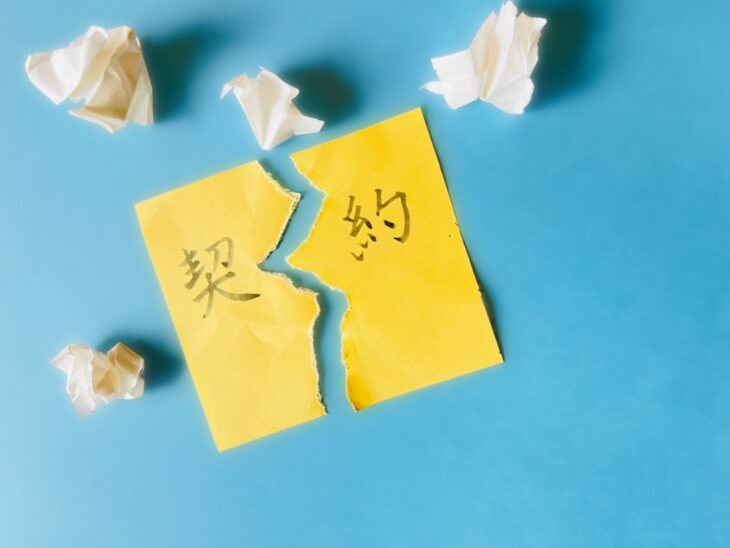
破産管財人がフランチャイズ契約を解除する場合は、加盟店もこれまでどおりに店舗の運営を継続することができなくなるでしょう。
この場合は本部の破産手続の前後で、加盟店側で気を付けなければならない点があります。
もしものケースとして確認しておきましょう。
(1)加盟店が本部の破産手続開始前に解除権を有する場合
本部の破産手続開始前に、加盟店がフランチャイズ契約の解除権を有している場合は、破産手続開始前であれば、加盟店自らFC契約の解除が可能です。
破産手続が開始されてしまうと、フランチャイズ契約を解除するかどうかは破産管財人が判断することになります。
つまり、破産管財人がFC契約の履行を選択した場合、加盟店側が契約の解除をすることは難しいと考えられます。
もし加盟店がフランチャイズ契約の解除権を有しており、契約の解除を希望している場合は、本部が破産手続を開始する前に解除権を行使しておきましょう。
(2)破産手続の開始後に本部に債務不履行が生じた場合
破産手続開始後に本部に債務不履行が生じた場合でも、それを理由に加盟店はフランチャイズ契約の解除ができません。
たとえば本部の商品供給が途絶えた場合など契約上は解約事由に当たるべき事実であっても、その債務不履行は破産手続内で処理されることになります。
ただし、破産管財人が契約の履行を選択したにもかかわらず、その後に本部に債務不履行が発生した場合は、加盟店はフランチャイズ契約を解除できると解されています。
そのため、破産手続の開始後であっても、破産管財人がフランチャイズ契約の継続を選択した後に生じた債務不履行を理由とした解除は認められます。
4.FC契約終了後の競業避止義務・秘密保持義務について

フランチャイズ契約においては、加盟店に対して、契約終了後も一定期間の競業行為を禁止する義務や、加盟店が本部から得た営業上の秘密を保持すべき義務を定めていることが一般的です。
これらの義務は、フランチャイズ本部の破産手続が開始された場合も同様です。
契約関係が存続する限りは、加盟店は競業避止義務・秘密保持義務を負うことになります。
また、破産管財人がフランチャイズ契約の解除を選択した場合や加盟店が契約解除を申し出た場合も、競業避止義務や秘密保持義務をそのまま負う可能性が高いです。
フランチャイズ本部とのフランチャイズ契約が解除された場合でも、事業譲渡等によりシステム自体が存続している限り、そのフランチャイズ事業を保護しなければならないことは変わりがないためです。
つまり、フランチャイズ事業が存続する間は、フランチャイズ契約から離脱した加盟店も継続して競業避止義務や秘密保持義務を負わなければなりません。
他方で、フランチャイズ事業が消滅した場合は、競業避止義務・秘密保持義務を負う必要がなくなります。
競業避止義務や秘密保持義務が存続するかどうかは、そのフランチャイズ事業が存続しているかどうかによって結論が変わると考えられます。
まとめ
フランチャイズ本部が破産手続を開始したからといって、必ずしもフランチャイズ契約を解除されるわけではありません。
破産手続が開始されると、破産管財人の判断によってフランチャイズ契約を継続するのか、解除するのかが定められます。
そのため、破産手続が開始された後は、加盟店の希望でフランチャイズ契約を解除することができない点に注意が必要です。
また、そのフランチャイズ事業が存続している間は、フランチャイズ契約から離脱した加盟店も競業避止義務や秘密保持義務を負うことに気を付けましょう。
関連記事

















