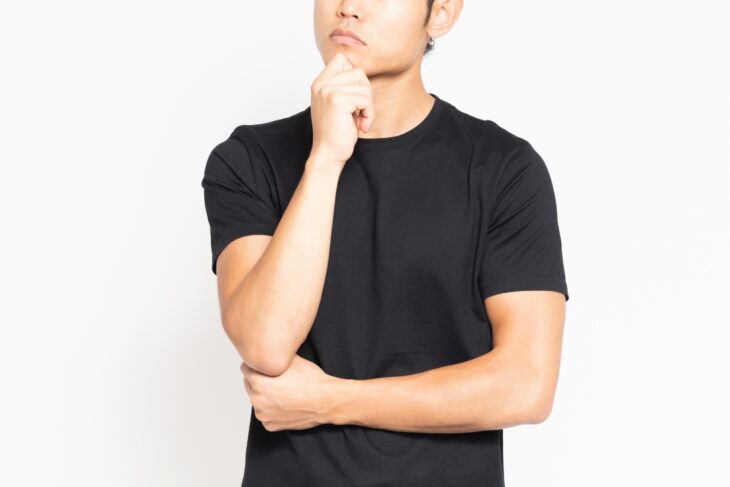個人再生を申し立てることができないケースとは?手続が失敗してしまうケースなどについても解説

「個人再生はどんなときにできないのか」
「個人再生が失敗するケースはどんな場合なのか」
借金の返済が滞り、個人再生を行うことを検討されている方の中には、手続が失敗するケース等を調べている方もいると思います。
個人再生は、裁判所への申立てが必要となる手続であり、一定の要件を満たす必要があります。
また、手続中にはさまざまな制約や注意点があり、一つひとつについて把握しておかなければ、途中で失敗してしまうケースもあるため、注意が必要です。
本記事では、個人再生を申し立てることができないケースや失敗するケース等について解説します。
1.個人再生を申し立てることができないケース

個人再生は、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、借金の総額に応じて減額された金額を原則3年(最長で5年)にわたって返済する再生計画案の認可を受けて返済を行う手続です。
減額される金額については、借金総額に応じて以下のように減額幅が定められています。
| 借金総額 | 最低弁済額 |
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円~500万円未満 | 100万円 |
| 500万円~1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
| 1500万円~3000万円未満 | 300万円 |
| 3000万円~5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
同じ債務整理の手続である任意整理とは異なり、借金の元本部分まで減額を受けることができるため、返済の負担を大幅に軽減させることが可能です。
また、自己破産とは異なり、住宅資金特別条項を利用することでローンが残っている住宅を手放すことなく手続を行えたり、ローンを完済した住宅や車などの資産価値が高い財産については、換価処分をせずに、手元に残した状態で手続を行うことができるのも大きなメリットといえます。
しかし、裁判所への申立ては、一定の要件を満たさなければなりません。
具体的には、以下に該当する場合には個人再生を裁判所に申し立てることができないため、注意が必要です。
- 借金の返済が困難な状態ではない
- 住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えている
- 安定した収入を得る見込みがない
- 過去7年間に個人再生や自己破産を行っている
順にご説明します。
なお、個人再生の概要や手続の流れ、要件などの詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(1)借金の返済が困難な状態ではない
個人再生を申し立てるためには、支払不能のおそれがあることが必要です。
具体的には、3年程度で分割返済(12か月×3年=36回返済)することができるかどうかが個人再生を申し立てるにあたっての目安となります。
そのため、一時的に返済が滞った場合や収入が少なくても家計のやりくりなどによってなお返済を行うことが可能な場合には、個人再生を申し立てることができません。
(2)住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えている
住宅ローンを除く、借金総額が5000万円を超えている場合も個人再生の申立てができません。
個人再生を行うための要件には、借金の総額に関するものがあり、具体的には、住宅ローンを除いた債務総額が5000万円を超えないことが要件です。
個人再生は、企業が対象となる民事再生手続を個人が利用できるように簡略化した制度で、債務総額が5000万円を超えるような大規模なものは個人再生の手続で処理することは想定されておらず、このような要件が設けられています。
5000万円を超える多額の借金がある場合、個人再生を申し立てることができなくなるため、個人再生を申し立てる際にはあらかじめ債務総額を正確に把握することが重要です。
(3)安定した収入を得る見込みがない
安定した収入を得る見込みがない場合も個人再生ができないケースの1つです。
個人再生では、再生計画案を裁判所に認可された後にその内容に従って返済を行う必要があります。
そのため、継続して返済を行えるほどの収入を得ていることが要件となり、これを満たしていない場合にも個人再生を行うことができません。
なお、個人再生には2つの手続があり、手続によって収入に関する要件は異なります。
- 小規模個人再生手続
- 給与所得者等再生手続
順にご説明します。
なお、2つの手続の具体的な違いについては、以下の記事もあわせてご参照ください。
#1:小規模個人再生手続
小規模個人再生手続は、個人事業主や給与所得者などの個人が利用することが念頭に置かれています。
収入の要件に関しては、「将来において継続的かつ反復的に収入を得る見込みがあること」が求められます。
具体的には、少なくとも3か月に1回の頻度で継続的に返済を行うことができるほどの収入を得ている必要があります。
#2:給与所得者等再生手続
給与所得者等再生手続は、その名のとおり会社員などの給与所得を得ている人が利用することができる手続です。
小規模個人再生手続よりも総支払額は増える傾向にはありますが、その分、債権者の同意が要らない等の大きなメリットがあります。
そのため、小規模個人再生手続と比較すると収入の要件が厳格に定められているのが特徴です。
具体的には、以下の2つの要件が求められます。
- 将来において継続的かつ反復的に収入を得る見込みがあること
- その額の変動の幅が小さいと見込まれること
変動幅については、申立前2年間の収入の変動が20%未満であることが必要です。
給与所得者であっても小規模個人再生手続を行うことは可能であるため、債権者の過半数が再生計画案に対して同意する限り、収入の変動幅が多い場合などには給与所得者等再生手続ではなく、小規模個人再生手続が選択される傾向があります。
(4)過去7年間に個人再生や自己破産を行っている
給与所得者等再生を行う場合には、申立から遡って過去7年間に、給与所得者等再生や自己破産を行っている場合又はハードシップ免責を受けた場合も再生手続をすることができません。
過去7年間に、これらのような事情がある場合には、任意整理など他の手続を選択する必要があります。
2.個人再生が失敗してしまう主なケース

個人再生は申立要件を満たしていたとしても、手続の途中で廃止(終了)となってしまうことがあります。
再生計画案の認可を受ける前に手続が廃止(終了)となった場合には、個人再生の手続を進めることができなくなってしまう点に注意が必要です。
また、再生計画案の認可を受けた場合であっても、その後の事情によっては再生計画を取り消されてしまい、個人再生を行った意味が失われてしまうこともあります。
これらのように個人再生が失敗してしまった場合には、失敗した原因を取り除いてから再度個人再生を申立てるか、又は自己破産等の他の債務整理手続きの実施を検討する必要があります。
手続の廃止(終了)や再生計画の取消しなどによって、個人再生が失敗してしまうケースの例は以下のとおりです。
- 一部の債権者のみに返済を行った(偏頗弁済)
- 個人再生の手続中に借入れやギャンブルなどを行った
- 手続費用を納付できなかった
- 再生計画案を期日までに提出できなかった
- 再生計画案の内容に問題があった
- 履行テストを怠った
- 再生計画案の内容に従った返済ができなくなった
順に見ていきましょう。
なお、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
(1)一部の債権者のみに返済を行った(偏頗弁済)
一部の債権者のみに返済を行うことを偏頗弁済(へんぱべんさい)と言います。
偏頗弁済をしてしまうと、本来他の債権者に対しても支払原資にできたはずの資産が流出し、特定の債権者のみ恩恵を受けることになります。
この場合、債権者間で不公平が生じてしまいます。
そのため、偏頗弁済を行ってしまった場合には、不当な申立ではないことをしっかりと説明しなければならず、その弁済額分を弁済額に上乗せしなければならなくなります。
これを行わずに再生計画を提出すると、手続が失敗する可能性があります。
個人再生手続と偏頗弁済の関係や偏頗弁済を行うリスクについては、以下の記事も参考になります。
(2)個人再生の手続中に借入れやギャンブルなどを行った
個人再生の手続中に借入れやギャンブルを行うと、再生計画案が認められなかったり、債務の圧縮幅が減らされたりする可能性があり、手続が失敗するリスクがあります。
個人再生の手続中に新たな借入れやギャンブルを行うリスクについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
(3)手続費用を納付できなかった
裁判所に対し、手続費用を納付できない場合にも、手続が失敗してしまいます。
個人再生は、裁判所を通じて行う手続であるため、裁判所へ費用を納付する必要があります。
具体的には、個人再生の申立てを行う際に、裁判所に対し、申立手数料や官報公告費などの費用を納付しなければならず、この費用を捻出することができなければ手続を進めることができなくなってしまうのです。
個人再生を行うために必要な費用の項目については、以下の記事もあわせてご覧ください。
また、裁判所に対する費用などが払えない場合の対処法については、以下の記事で解説しています。
(4)再生計画案を期日までに提出できなかった
再生計画案を期日までに提出できない場合も手続が失敗します。
提出期日から1日でも徒過してしまうと、その時点で手続が廃止(終了)となってしまうため、期日を守って作成・提出を行うことが大切です。
特に債務者本人が申立てを行うと、ほかの書類作成や資料収集に時間がかかり、再生計画案の作成が間に合わないケースもあります。
そのため、弁護士に手続を依頼することが最も重要です。
弁護士に依頼することで、書類作成を任せたり、資料収集についてのアドバイスやサポートを受けたりすることができるため、スムーズに手続を進めることにつながります。
(5)再生計画案の内容に問題があった
上記で見てきたように、再生計画案の内容に問題があると、手続が失敗してしまいます。
再生計画案では、裁判所から認可された後に返済を行う金額や返済期間などについて記載しなければなりません。
裁判所が再生計画案を認可するのは、債務者の収入状況などから継続的に返済を行うことが可能であるかどうかを基準とするため、返済計画が適切に定められていない場合には再生計画案が不認可とされ、手続が廃止(終了)となってしまうことに注意が必要です。
また、個人再生の手続では、財産目録の提出が義務付けられています。
この財産目録の記載が誤っていたり、記載が漏れていたりした場合は、手続きが廃止される可能性があります。
たとえ虚偽の申告をしたとしても、財産目録の内容は細かく調査されますので、必ず発覚するものだと考えた方がよいです。
財産目録の記載にも十分な注意が必要です。
(6)履行テストを怠った
履行テストを怠った場合も手続が失敗します。
履行テストとは、個人再生の手続で、再生計画案に基づく返済に先立って行われ、再生計画案通りに返済できる能力があるかを確認するための手続です。
債務者は一定期間、裁判所から指定された口座に積立を行うことが求められます。
これを怠ってしまった場合、返済を行う能力がないと裁判所に判断されてしまい、手続が途中で失敗してしまうため、支払を怠らないようにすることが重要です。
(7)再生計画案の内容に従った返済ができなくなった
再生計画案の内容に従った返済ができなくなった場合、債権者からの申立てによって再生計画が取り消されてしまう可能性があります。
再生計画が取り消されてしまうと、減額前の金額を返済しなければならなくなり、個人再生を申し立てた意味が失われてしまう点に注意しましょう。
そのため、再生計画に従った返済を継続するとともに、返済が滞りそうな場合には直ちに弁護士に相談することが重要です。
3.個人再生を行うことが適していないケース

個人再生を申し立てることで、借金の減額を図ることができますが、そもそも個人再生という手続自体が適していないケースがいくつかあります。
個人再生を行う要件を満たしている場合でも、以下のようなケースでは個人再生が適していない可能性が高いです。
- 借金の総額が100万円未満である
- 住宅資金特別条項を利用するための要件を満たしていない
- 資産価値の高い財産を有している
このようなケースでは、ほかの債務整理の手続である任意整理や自己破産を行うことを検討した方がよい場合もあります。
もっとも、どのような手続を選択すべきかは収入や借入れ、財産の状況などによって異なるため、ご自身に最適な解決方法を判断するのに迷う場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
(1)借金の総額が100万円未満である
たとえ個人再生を申し立てたとしても、借金総額が100万円未満の場合には、元金の減額を受けることができません。
そのため、個人再生を行うメリットはほとんどないといえます。
一方で、個人再生案が認可されると、3~5年の分割返済を行うことができる点ではメリットがまったくないわけではありません。
しかし、そのような場合には任意整理を行うことが一般的です。
任意整理と個人再生の具体的な違いやどちらの手続を行うべきかの判断基準については、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)住宅資金特別条項を利用するための要件を満たしていない
個人再生は住宅を残せる手続だと知られていますが、住宅資金特別条項を利用するための要件を満たしていない場合、住宅を失ってしまいます。
例えば、住宅ローンを組む際には、金融機関が住宅に抵当権を設定することが一般的です。
個人再生を行った場合、一般に、住宅ローン契約等により、抵当権が実行されてしまいます。
もっとも、住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特則」)を利用し、住宅ローンの支払いをそのまま続けることで住宅を手放さずに債務整理をすることができます。
住宅資金特別条項を利用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 住宅ローンの借入れであること
- 債務者が自己の居住用に所有する住宅であること(1軒まで)
- 対象の住宅をほかの借入れの担保としていないこと
- 保証会社が代位弁済した場合には、その履行日から6か月以内に再生手続を申し立てていること
これらの要件を1つでも満たさない場合には、住宅資金特別条項を利用することができず、住宅を手放さなければならないケースがあることに注意が必要です。
なお、住宅ローンなどの特定の債務を除外して手続を行いたい場合には、任意整理を行うことが適しているケースもあります。
住宅資金特別条項を利用するための要件の詳細や注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(3)資産価値の高い財産を有している
資産価値の高い財産を有している場合、個人再生による減額幅が少なくなる可能性があります。
先ほども述べたように、個人再生では自己破産の場合とは異なり、債務者の財産について換価処分が行われることはありません。
しかし、ローンを完済した住宅や車、高額な預貯金、生命保険、退職金などがある場合には、これらの価値を清算価値として、最低弁済額を超える返済が必要になることに注意が必要です。
これは、個人再生で定められる弁済額は、債務者が自己破産を選択した場合に債権者へ配当される金額を下回ってはならないとする「清算価値保障原則」という考え方に基づいています。
そのため、財産状況によっては、必ずしも最低弁済額まで減額されるとは限らないことを押さえておきましょう。
清算価値として計上される財産や清算価値の算定方法については、以下の記事も参考になります。
4.個人再生について弁護士に相談・依頼するメリット

個人再生を行う際には、申立てを行うための要件を満たさなければならないほか、手続が開始された後もいくつかの注意点があります。
債務者ご自身で手続を行うことも可能ではあるものの、申立要件や手続中の注意点にどのようなものがあるかについては、実務経験などがなければ判断が難しいことも多いです。
手続を遅滞なく進めるためには、専門家である弁護士に相談の上で手続を依頼することをおすすめします。
個人再生について、弁護士に相談・依頼するメリットは以下のとおりです。
- 個人再生を行う要件を満たしているか説明を受けられる
- 書類作成や資料収集に関するサポートを受けられる
- 手続が廃止(終了)とならないための対応ができる
順にご説明します。
(1)個人再生を行う要件を満たしているか説明を受けられる
弁護士から、個人再生を行う要件を満たしているか説明を受けることが可能です。
先ほど述べたように、個人再生を行うことが適していないケースがあり、場合によっては個人再生ができない場合もあります。
弁護士であれば、借金の状況や返済能力等から客観的に判断し、適切な解決方法についてアドバイスを行うことが可能です。
そのため、まずは弁護士に個人再生ができるのか、そしてそれが最適な手段なのかどうか確認してみましょう。
(2)書類作成や資料収集に関するサポートを受けられる
書類作成や資料収集に関するサポートを受けることができます。
個人再生の申立てには、揃えなければならない書類や資料がたくさんあり、専門知識や実務経験がなければ一から揃えるのはかなり大変な作業です。
弁護士に相談すれば、書類の作成方法や取得方法に関するアドバイスやサポートを受けることができ、弁護士に必要書類等の作成を依頼することもできます。
書類等に不備があれば、手続の進行に遅れが生じることもあるため、スムーズに解決するためにも弁護士に依頼するのがおすすめです。
(3)手続が廃止(終了)とならないための対応ができる
弁護士の力を借りることで、手続が廃止(終了)とならないための対策が可能です。
個人再生は、偏頗弁済のほかにも、書類や資料の記載漏れ・不備などによって手続が廃止(終了)となってしまうことがあります。
弁護士に手続を依頼することで、そのようなリスクのある行為についてあらかじめ説明を受けることができ、事前に対策を進めることができる点も大きなメリットといえるでしょう。
まとめ
個人再生ができないケースは、今回紹介したようにいくつものパターンがあります。
また、個人再生が最適ではないケースもあるため、個人再生の申立てを行う前に、最も適した解決手段が何か見出すことが大切です。
経験豊富な弁護士に相談すれば、借金の状況や返済能力等によって適した手段について提案を受けることができます。
また、手続のサポートや失敗しないための対策支援を受けることもできるので、借金の返済で困った方は弁護士にまずは相談するのがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、借金に関する相談を無料で受け付けておりますので、個人再生を行うことを検討されている方はお気軽にご相談ください。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事