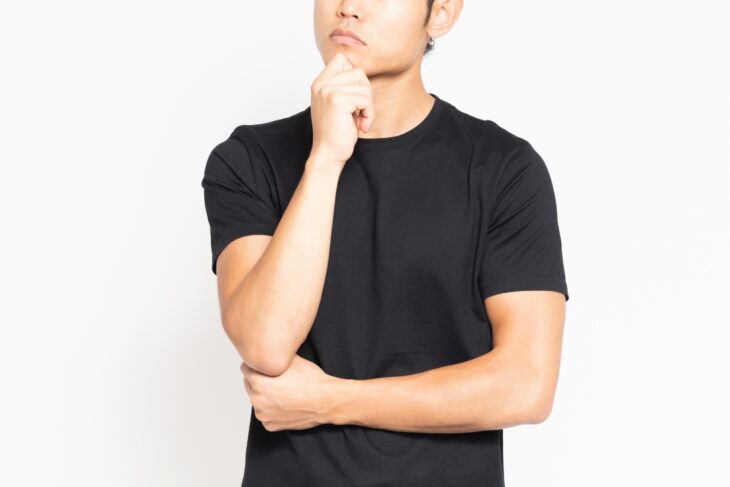借金を滞納するとどうなる?滞納しそうな場合の対処法や債務整理についても解説

「借金を滞納し続けたらどうなるのか」
「滞納している借金を解消するにはどうしたらいいのか」
借金の返済が滞り、その後の返済の目途が立たない状態に陥っている方の中には、このような疑問や悩みをお持ちの方もいると思います。
返済期日までに借金の返済ができない場合でも、早期に債権者に連絡することで、支払の猶予や分割返済に応じてもらえる可能性はあります。
しかし、滞納が続くことで、最終的には訴訟や差押えなどの法的リスクが高まり、財産を失うことになりかねません。
そのため、返済の目途が立たない場合には、なるべく早期に必要な対応を行いましょう。
本記事では、借金を滞納した場合のリスクや滞納しそうになった場合の対処法等について解説します。
1.借金を滞納した場合のリスク

借金を期日までに返済できず、滞納してしまった場合には、滞納期間が長くなればなるほど法的リスクが高まります。
具体的には、以下の流れでリスクが高まることに注意が必要です。
- 遅延損害金が発生する
- 債権者から督促や取立てを受ける
- 信用情報機関に事故情報が登録される
- 一括返済の請求を受ける
- 訴訟や差押えなどの法的手続に移行する
もっとも、早期に適切な対応を行うことで、訴訟や差押えなどへ移行されるリスクを抑えることが可能です。
そのため、返済が滞ってしまう前に、可能な限り早く、債権者への連絡や事情の説明を行うことが大切です。
(1)遅延損害金が発生する
期日までに借金の返済ができなかった場合、返済期日の翌日から支払いが終わるまで、遅延損害金が発生します。
金融機関や貸金業者など債権者によって遅延損害金の利率は異なりますが、利息と比較して遅延損害金の利率の方が高いことが多いです。
なぜなら、遅延損害金には、期日までに返済ができなかったことに対する制裁の意味合いが含まれているからです。
遅延損害金を算出するための計算式は以下のとおりです。
- 残債務額×遅延損害金利率÷365日×滞納日数
このように、滞納期間が長くなればなるほど遅延損害金の金額も大きくなるため、注意が必要です。
遅延損害金の計算方法については、以下の記事も参考になります。
(2)債権者から督促や取立てを受ける
債権者によっては、返済期日を経過した日の翌日から督促を行うことがあります。
督促は、最初のうちは電話や書面によって行われることが一般的です。
この時点で適切な対応を行うことで、分割払いや支払の猶予に応じてもらえる可能性があります。
そのため、まずは支払が行えなくなった事情や今後の見通しなどについて、債権者にしっかりと伝えることが大切です。
債権者からの連絡を無視し続けると、保証人を立てている場合には保証人に対して請求がなされたり、債権者が債務者の住居や職場を訪問して取り立てたりする可能性があります。
債権者から督促や取り立てを受けてお困りの場合は、弁護士にご相談ください。
なお、債権者からの督促や取立ての方法などについては、以下の記事でも解説しています。
(3)信用情報機関に事故情報が登録される
短くとも3か月以上滞納した場合には、信用情報機関に事故情報が一定期間登録されてしまいます。
信用情報機関とは、加盟している金融機関などから顧客の借入状況や返済に関する情報の提供を受けて管理し、照会があれば情報を提供する機関のことです。
金融機関は、借入れやローンの申込みなどを受けると、支払能力の調査のために信用情報機関に照会を行います。
これにより、借金の返済を滞納しているということが分かると、金融機関は貸倒れのリスクを回避するために借入れの申込みなどを拒否する場合があります。
そのため、事故情報が登録されている間は、すでに利用している金融機関や貸金業者からはもちろん、それ以外の業者からも借入れを行えなくなる可能性が高くなります。
事故情報の登録が行われることによる生活への影響については、以下の記事も参考になります。
(4)一括返済の請求を受ける
債権者からの電話や書面による連絡に対応せずに放置していると、残債務について一括で返済するよう請求を受けるリスクが高まります。
債務者には、返済期日が到来するまでは借金の支払をしなくてもよいとする期限の利益があります。
もっとも、返済期日を経過した場合、債務者は期限の利益を失い、債権者から一括返済の請求を受けても、これを拒むことはできません。
仮に一括返済を求められた場合には、残債務に利息や遅延損害金を加えた金額について支払を行わなければなりません。
なお、一括返済の請求を無視したまま放置してしまうと、訴訟や差し押さえといった法的措置へ移行されます。
一括返済の請求を受けてお困りの方は、専門家である弁護士にその後の対応について相談することをおすすめします。
なお、利息の計算方法については、以下の記事が参考になります。
(5)訴訟や差押えなどの法的手続に移行する
一括返済の請求がなされた後にも具体的な対応を行わずに放置すると、訴訟などの法的措置に移行します。
債権者から訴訟が提起されると、裁判所から債務者に対して訴状が送達されます。
債務者が、訴状を受け取った後にも定められた期限内に答弁書の提出などの必要な対応を行わなければ、裁判所は債権者に対し勝訴の判決を示すことになります。
そして、その判決が確定すると、債権者は判決に基づいて、債務者の財産に対して差押えを行うことが可能になります。
差押えの対象となる財産には、債務者の住宅などの不動産、車やバイクといった動産、預貯金や給与などの債権があります。
差押えが行われることで、これらの財産を失ってしまうリスクがあるため、法的措置に移行してしまう前に対応を行うことが重要です。
なお、給与については、全額が差押えの対象になるわけではなく、手取り額の4分の1までしか対象にできないなどと法令に定められています(民事執行法152条1項2号、民事執行法施行令2条)。
すなわち、月給の手取りが44万円以下の場合は手取りの4分の1の差押えが可能になります。
また、手取りが44万円を超える場合は、33万円を超えた部分が差し押さえ可能となります。
差押えの対象となる財産や給与が差し押さえられた場合の注意点などについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
2.借金の返済を滞納しそうになった場合の対処法

すでに述べたように借金の返済を滞納してしまうことで、財産が差し押さえられてしまう事態になりかねません。
そのような不利益を回避するためには、滞納しそうになった時点で早期に必要な対策を行うことが大切です。
具体的には、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 早期に債権者に連絡する
- 借金の総額を確認する
順にご説明します。
(1)早期に債権者に連絡する
返済期日までにお金を用意することができないことが分かった時点で、速やかに債権者に連絡することが最も重要です。
返済ができない事情や今後の見通しなども合わせて伝えることができれば、債権者によっては支払期日を猶予することもあります。
また、まとまったお金をすぐに用意することはできないものの、分割で支払うことができる場合には、その旨を伝えることで分割払いの対応をしてもらえる可能性もあるため、誠実な対応を心がけましょう。
(2)借金の総額を確認する
返済が厳しいと思った時点で、借金の総額を確認することも大切です。
特に複数社から借入れを行っている場合には、どの業者からどのくらいの借入れを行っているかを把握できていないこともあります。
各社からの借入額を確認し、ご自身の収入などと照らし合わせて、今後も継続して返済を行うことができるかについて把握しましょう。
なお、この時点で返済を継続することが困難であると判明した場合には、弁護士に相談して解決方法の提案を受けることをおすすめします。
3.借金の返済ができない場合の解決方法

すでに借金の返済を滞納してしまった場合には、放置することでさまざまな法的リスクが高まります。
例えば、借金の総額と比べて収入が少なくまとまったお金をすぐに用意できない場合や、借金の総額が大きい場合には、今後も返済を行うことができない可能性が高いです。
そのような場合には、債務整理を行うことを検討しましょう。
債務整理を行うことで、借金の返済義務の軽減や免除を受けることが可能です。
債務整理には、具体的に、以下のような手続があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
順にご説明します。
それぞれの手続のメリットやデメリットについては、以下の記事も参考になります。
(1)任意整理
任意整理とは、将来的に発生する利息のカットと返済期間の延長(概ね3~5年)について債権者と債務者が直接交渉を行い、合意に基づいて返済を行う手続です。
後に述べる個人再生と自己破産とは異なり、裁判所への申立てを要さず、比較的短い期間で手続を行うことができます。
通常、借金の返済を行うときは、元本に合わせて利息も支払わなければならないため、利息の負担が大きい場合には、返済を継続してもどんどん利息が発生し続け、元本部分の返済がなかなか終わらないことが多くあります。
そこで、任意整理を行い、将来的に発生する利息をカットすることができれば、元本及び既発生の利息部分の返済を着実に進めることができます。
また、返済スケジュールを3~5年の長期に設定し直すことができれば、月々の返済負担を軽減しながら完済を目指すことが可能です。
なお、任意整理では、債務者が手続の対象とする債権者を選ぶことができる点にも大きな特徴があります。
そのため、抵当権が設定されている住宅ローンや保証人を立てている借金を対象から除外することで、債務者の生活や保証人への影響を最小限に抑えながら手続を行うことが可能です。
もっとも、手続の対象から除外した借金については、これまでの契約内容に従って返済を行う必要があります。
また、任意整理の対象とした債務についても、返済義務自体がなくなるわけではないため、債権者との合意が成立したとしても返済を続けなければならないことにも注意が必要です。
任意整理を行うメリット・デメリット、手続を行う際の注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)個人再生
個人再生は、安定した収入があることを前提に、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、借金の総額に応じて減額された金額を原則3年で返済する旨の再生計画案の認可を受けて、返済を行う手続です。
任意整理では、将来的に発生する利息が減額となりますが、個人再生の場合には元本部分まで減額を受けることができます。
具体的には、借金総額に応じて、以下のように減額幅(最低弁済額)が定められているのが特徴です。
| 借金総額 | 最低弁済額 |
| 100万円未満 | 借金総額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超え1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
| 1500万円超え3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円超え5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
任意整理の場合と比較すると、借金の返済義務を大幅に軽減させることが可能ですが、返済義務自体がなくなるわけではない点は任意整理と共通しています。
また、任意整理とは異なり、手続の対象とする債権者を選ぶことはできず、原則としてすべての債権者が手続の対象となります。
そのため、保証人を立てている債務がある場合に個人再生の申立てを行うと、保証人に対して一括返済の請求がされてしまいます。
さらに、抵当権が設定されている住宅ローンも原則として個人再生手続の対象となるものの、住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特則」)を定めることで、居住している住宅を手元に残した状態で手続を行うことが可能です。
ただし、住宅資金特別条項を利用するためには一定の要件を満たさなければなりません。
個人再生の概要や手続を行うための要件、注意点などについては、以下の記事をご覧ください。
また、任意整理と個人再生の具体的な違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(3)自己破産
自己破産は、借金の返済ができないことを裁判所に申し立て、裁判所から免責許可決定を受けた上で、借金の返済義務を免除してもらう手続です。
免責許可決定を受けることができれば、任意整理と個人再生とは異なり、原則としてすべての借金の返済義務から解放される点に大きなメリットがあります。
一方で、債務者が一定額以上の財産を所有している場合には、その財産は換価され、債権者に配当される可能性がある点に注意しましょう。
具体的には、99万円を超える現金や20万円以上の価値のある財産については、原則として換価の対象となります。
そのため、住宅や車、バイクなどの資産価値の高い財産は手放さなければならなくなる可能性が高いです。
また、自己破産の申立てを行えば必ず借金の返済義務が免除されるわけではなく、一定の事由(免責不許可事由)がある場合には、免責を受けられない可能性があります。
自己破産の手続の概要や注意点などについては、以下の記事も参考になります。
自己破産を行うための要件や免責不許可事由の詳細については、以下の記事も合わせてご参照ください。
4.弁護士に相談するメリット

借金の総額が大きい場合や返済の目途が立たない場合には、債務整理を行うことで、早期に借金問題を解決することができます。
もっとも、債務整理を適切に行うためには、専門知識や実務経験が必要になります。
そのため、まずは専門家である弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談することで、そのまま手続を依頼することができるだけでなく、以下のようなメリットがあります。
- 無料で専門的なアドバイスを受けることができる
- 契約後は債権者からの督促や取立てがストップする
- 債務整理を行う準備についてサポートを受けることができる
- 債権者や裁判所とのやり取りを一任することができる
順に見ていきましょう。
(1)無料で専門的なアドバイスを受けることができる
債務整理については、相談料を無料としている法律事務所が多くあります。
そのため、経験豊富な弁護士に無料で専門的なアドバイスを受けることができる点が大きなメリットといえます。
上で述べたように、債務整理の手続には大きく3つあり、それぞれにメリットやデメリットがあります。
そして、どの手続を行うことが適しているかは、借金の総額や債務者の収入状況などによって異なります。
例えば、借金の返済を継続しなければならない任意整理と個人再生では、継続的に収入を得る見込みがなければ、手続を行うことは難しいです。
また、仮に継続的な収入を得ていたとしても、自己破産を行うことが適しているケースもあります。
このように、どのような手続を行うことが適しているかは判断が難しく、債務者ご自身で手続を行った場合には、適切な解決を図ることができない可能性もあります。
債務整理を行うことを検討される場合には、経験豊富な弁護士に相談することで、ご自身に最適な解決方法の提案を受けることができます。
(2)契約後は債権者からの督促や取立てがストップする
弁護士に債務整理の手続を正式に依頼すると、債権者に対して受任通知が送付されます。
貸金業者に対する受任通知には、債権者が債務者に対して直接督促や取立てを行うことを禁止する法的効力があります(貸金業法21条1項9号)。
また、貸金業者ではない保証会社等の金融機関に対する受任通知については、督促や取立てを止める明文の規定はありませんが、実際上督促等を止めることが一般的です。
このように、弁護士に手続を正式に依頼することで、債権者からの連絡がストップします。
督促や取立てが止まることで、返済に関する精神的なストレスから一時的に開放されます。
また、債務整理の手続を進めるにあたっては、書類の作成や資料の収集も必要です。
債権者からの督促や取立てが一時的に停止することで、これらの準備も安心して進めることが可能になります。
(3)債務整理を行う準備についてサポートを受けることができる
弁護士に相談・依頼することで、債務整理を行う準備について、アドバイスやサポートを受けることができます。
特に裁判所を通して行う個人再生と自己破産では、さまざまな書類や資料を作成・収集し、裁判所に提出する必要があります。
しかし、知識や経験がなければ、必要な書類や資料を過不足なく揃えることは困難なことが多いです。
また、書類や資料に不備があれば、債務整理の手続が遅延するだけでなく、途中で失敗してしまうリスクもあります。
しかし、弁護士に相談することで、書類作成や資料収集についてアドバイスやサポートを受けることができるため、このようなリスクを回避することが可能です。
さらに、必要な書類の作成を弁護士に依頼することもできるので、手続をスムーズに進めることにもつながります。
(4)債権者や裁判所とのやり取りを一任することができる
債務整理の手続を弁護士に依頼することで、債権者や裁判所とのやり取りを一任することができます。
債務整理を行うにあたっては、任意整理の場合には債権者と、個人再生と自己破産の場合には裁判所とやり取りを行うことになりますが、このやり取りを債務者本人が行うには困難が伴うことが多いです。
例えば、任意整理において、債務者本人がやり取りを行う場合、交渉に応じてもらえない可能性があり、不利な条件で合意してしまうリスクが高まります。
また、個人再生と自己破産は法律の定めにしたがって手続が進行するため、進行状況を適切に把握して対処する必要があります。
弁護士に債務整理の手続を依頼することで、債権者や裁判所への対応を一任することができるため、それぞれの手続の注意点を押さえた適切な対応を行うことが可能です。
これによって、債務整理が成功する可能性を高めることができます。
まとめ
借金の滞納が続くと、さまざまなリスクが生じます。
滞納が続いている場合や滞納しそうになった場合は、速やかに対策を講じることで、訴訟などの法的リスクを回避することが可能です。
もし返済が難しい場合には、債務整理を行うことによって借金の減額や免除を受けることができます。
債務整理の手続は専門的な知識が求められるほか、さまざまな準備が必要となるため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、借金の滞納で困っている方はお気軽にご相談ください。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事