任意整理と自己破産の違いは?どちらを行うべきかの基準や弁護士に相談するメリット

「任意整理と自己破産には具体的にどんな違いがあるのか」
「自分には任意整理と自己破産のどちらが適しているのか」
債務整理を行うことを検討されている方の中には、任意整理と自己破産のどちらを行うべきか分からず困っている方もいると思います。
任意整理は、債権者との直接交渉によって債務の負担を軽減する手続であり、自己破産は、裁判所に申立てを行って最終的にほぼすべての債務の支払義務について免除を受ける手続です。
大きな違いは、支払義務が残るかどうかという点です。
そのほかにも任意整理と自己破産にはいくつかの違いがあります。
本記事では、任意整理と自己破産の違いや共通の注意点等について解説します。
また、どちらの手続を行うべきかについての着目点についても合わせて解説します。
手続に迷った際に、最適な解決方法を考える参考となれば幸いです。
1.任意整理と自己破産
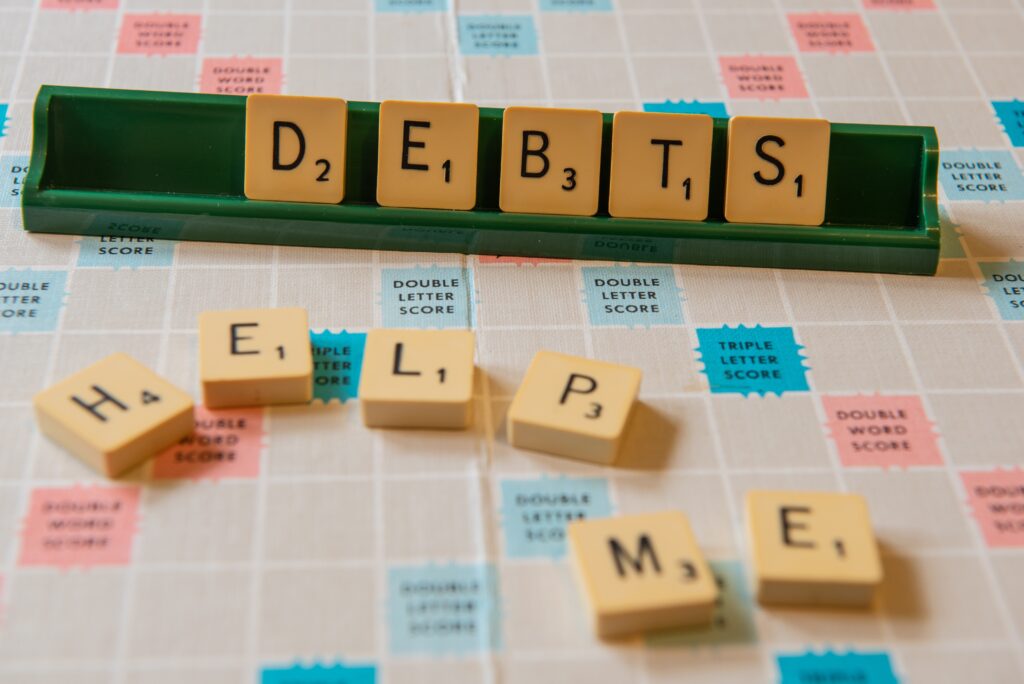
任意整理と自己破産は、いずれも借金の減額または免除を目指す手続の総称である、「債務整理」の1つです。
以下では、任意整理と自己破産の概要についてご説明します。
(1)任意整理
任意整理は、将来的に発生する利息の支払免除となるべく長期の分割期間の設定(概ね5年)について債権者と直接交渉を行って和解し、和解の内容に基づいて返済を行う手続です。
債権者との契約どおりに返済する場合、元本だけでなく、元本に応じて発生する利息の支払も行わなければなりません。
元本が大きくなって、利息の負担も大きくなってしまった場合には、返済を続けてもなかなか返済を終えることができなくなってしまいます。
このような場合に将来利息の支払免除ができれば、契約どおりの返済時に比べ、元本部分を着実に減らすことにつながり、債権者への支払総額も減らすことができます。
また、返済期間を長期に設定できれば、月々の返済額を減らし、返済を継続しやすくすることもできます。
一方で、支払義務自体がなくなるわけではないため、債権者と和解ができたとしても、その後も和解内容どおりに支払をしていく必要があることを忘れてはいけません。
また、任意整理の交渉に応じるかどうか、どのような内容を要求するかは債権者次第です。
そのため、債権者が交渉に応じない場合には支払義務を大きくは軽減できなかったり、和解自体ができなかったりする可能性がある点にも注意が必要です。
任意整理のメリットやデメリット、手続の流れなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)自己破産
自己破産は、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらって手続を開始し、一定以上の価値のある財産については換価して債権者に配当した上で、最終的に裁判所から債務の支払義務の免除(免責許可)の決定を受ける手続です。
任意整理とは異なって債務の支払義務自体がなくなるため、メリットの大きい手続といえます。
もっとも、自己破産は裁判所を通して行う手続であり、法律によって定められた方法に沿って進める必要があります。
また、自己破産を申し立てれば必ず免責許可を受けられるというわけではなく、借入れの原因が浪費である、借入れの際に詐欺的な方法を用いたなどの一定の事由(免責不許可事由)が存在する場合には免責を受けられない可能性があることにも気を付ける必要があります。
自己破産の手続の流れについては、以下の記事が参考になります。
手続中の注意点や免責不許可事由の詳細については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
2.任意整理と自己破産の具体的な違い

上記のように、任意整理と自己破産とでは、債務の支払義務の負担を軽減できるにとどまるのか、免除を受けることができるのかという点に大きな違いがあります。
さらに、以下のような違いも重要です。
- 手続を行うための条件
- 手続の対象となる債務
- 財産の処分
- 手続に要する費用
- 官報への掲載
- 手続中に仕事へ与える影響
順にご説明します。
(1)手続を行うための条件
任意整理と自己破産とでは、手続を行うための条件が異なります。
具体的な違いは以下のとおりです。
| 任意整理を行うための条件 | 自己破産を行うための要件 |
|
|
任意整理は、債権者と直接交渉を行うことによって手続を進めるため、任意整理を行うための法律上の要件は特にありません。
もっとも、債権者と和解したとおりに返済を継続する必要があることから、それが可能でなければ手続を行うことはできません。
一方の自己破産の手続は法律によって要件が定められており、その要件を満たす必要があります。
支払不能についていえば、借入総額が年収を超えていたり、3年(36回の分割)で返済できなかったりすることが一応の目安とされています。
任意整理を行うための条件の詳細については、以下の記事もあわせてご覧ください。
自己破産を申し立てるための要件については、以下の記事で詳しく解説しています。
(2)手続の対象となる債務
任意整理では、債務者が手続の対象とする債務を選ぶことができます。
例えば、住宅ローンについては、その住宅に金融機関などの債権者が抵当権を設定していることが一般的です。
債務者が残債務を支払えなくなった場合には、債権者は抵当権を実行して残債務の回収を図ることができます。
また、車やバイクなどのローンには、信販会社が所有権留保を付していることが通常で、債務者がローンの支払をできなくなった場合には、債権者は所有権留保に基づき、車やバイクを引き上げることができます。
したがって、住宅ローンや車・バイクローンを債務整理の対象にすると、それらの所有権を失ってしまうのが通常です。
しかし、任意整理の場合には、これらを手続の対象から除外することで、住宅や車などを失うことなく手続を行うことが可能です。
一方、自己破産の手続を行う際は免責を受けられるかどうかにかかわらず、すべての債務を対象とする必要があり、債務者に選択の余地はありません。
そのため、住宅ローンや車のローンの残債務がある状態で自己破産を行うと、住宅に設定されている抵当権が実行されたり、車が所有権留保に基づいて引き上げられたりすることに注意が必要です。
(3)財産の処分
ローンを完済している住宅や車などの資産価値の高い財産を所有している場合には、自己破産を行うとそれらの財産を失う可能性があります。
任意整理の場合には、資産価値の高い財産を債務者の手元に残しながら手続を行うことが可能です。
任意整理後も住宅に住み続けることはもちろん、車やバイクを使い続けることができるため、生活や仕事への影響は少ないということができます。
これに対して、自己破産では、債務者が一定以上の価値のある財産を所有している場合には、換価処分が行われ、債権者に平等に配当が行われることになります。
基準は裁判所によって異なることがありますが、ほとんどの場合、20万円を超える財産については、換価処分の対象となります。
もっとも、合計で99万円を超えない範囲の財産や、家具等の生活に必要な財産は手元に残すことができます。
自己破産における現金の取り扱いや手元に残すことができる財産については、以下の記事で詳しく解説しています。
(4)手続に要する費用
手続に要する費用も異なります。
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉する手続であるため、手続を弁護士に依頼した場合、生じる費用は弁護士費用のみです。
一方、自己破産では、手続を弁護士に依頼した場合、弁護士費用のほかに裁判所に納める手数料等(予納金)が必要となります。
特に債務者が一定額以上の財産を所有している場合に自己破産を行うと、管財事件となり、管財人の報酬として、最低でも20万円以上の予納金が必要となる可能性があります。
この予納金は申立ての際に納付する必要があり、一定の猶予期間を与えられることもありますが、支払ができなければ手続が進まなくなってしまいます。
自己破産における予納金の項目や相場については、以下の記事も参考になります。
また、予納金を捻出できない場合の対処法については、以下の記事で解説しています。
(5)官報への掲載
官報に掲載されるかどうかも違いの一つです。
自己破産の場合、手続の進捗状況を申立人の氏名や住所とともに、国の機関誌である官報に掲載して公告することが、法律上決められています。
そのため、官報を見たことにより、自己破産の手続を行ったことを周囲に知られる可能性も否定できません。
もっとも、官報は誰でも見ることができるものですが、わざわざこれを見ようという人は一部の職業の人以外にほとんどいません。
したがって、自己破産を選択したとしても、官報公告によって家族や職場などの近しい人に知られてしまうことはほとんどありません。
また、任意整理は裁判所を介さずに行う手続であり、官報公告を定める法律がないため、官報公告は行われません。
そのため、官報公告により家族や職場などの周りの人に手続を知られるリスクはありません。
自己破産において官報公告がされるタイミングやその内容については、以下の記事も参考になります。
(6)手続中に仕事へ与える影響
自己破産を行うと、手続開始決定から免責許可決定までの間、一定の資格や職業が制限されることになります。
具体的には、以下のような資格・職業が制限されます。
- 弁護士
- 税理士
- 司法書士
- 公認会計士
- 証券外務員
- 旅行業者
- 生命保険募集人
- 警備員 など
そのため、これらの仕事を行っている場合には、免責許可決定を受けるまでは業務を行えなくなり、一時的に休職や転職をしなければなりません。
なお、任意整理の場合には、このような資格・職業の制限はないため、手続中であっても問題なく仕事を行うことが可能です。
自己破産と資格・職業制限の関係については、以下の記事もご覧ください。
3.任意整理と自己破産に共通する注意点

上記のように、任意整理と自己破産には手続の内容などに違いが見られる一方で、共通する注意点もいくつかあります。
具体的には、以下のとおりです。
- 信用情報機関に事故情報が登録される
- 手続の効果が及ばない債務がある
順に解説します。
(1)信用情報機関に事故情報が登録される
任意整理と自己破産のどちらの手続を行ったとしても、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆる「ブラックリスト入り」)。
信用情報機関は、各金融機関から顧客の借入状況や返済に関する情報の提供を受けてこれを管理し、加入している金融機関から照会を受けた場合には開示する機関です。
金融機関は、借入れやローンの申込みを受けた場合には、その人の信用力や返済能力を確認するために、信用情報機関へ照会を行います。
任意整理や自己破産を行ったという事実はその人の返済能力に問題があることを示す情報(事故情報)ですので、照会によってこれを知った金融機関申込みを拒否することになります。
任意整理や自己破産を行うと、信用情報の照会が行われ、借入れやクレジットカードの利用などができなくなります。
なお、事故情報は以下の期間が経過すると削除されます。
| 手続の種類 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) | 全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
| 任意整理 | 完済から5年 | 完済から5年 (ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年) |
完済から5年 |
| 自己破産 | 免責許可決定確定日から5年 | 免責許可決定確定日から5年 | 手続開始決定日から10年 |
そのため、任意整理または自己破産のどちらの手続を行ったとしても、5年から10年ほどで新たな借入れやクレジットカードの発行や利用を再開できることになります。
(2)手続の効果が及ばない債務がある
任意整理または自己破産を行ったとしても、支払義務の軽減や免除を受けられない債務があることには注意が必要です。
債務整理の効果が及ばない債務には、以下のようなものがあります。
- 税金
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料 など
これらについては、任意整理と自己破産のいずれを行ったとしても、引き続き支払が必要となります。
なお、任意整理の対象とすることができない債務については、以下の記事も参考になります。
また、自己破産の手続において免責の対象とならない債務(非免責債権)の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
4.任意整理と自己破産のどちらを行うべきかの基準
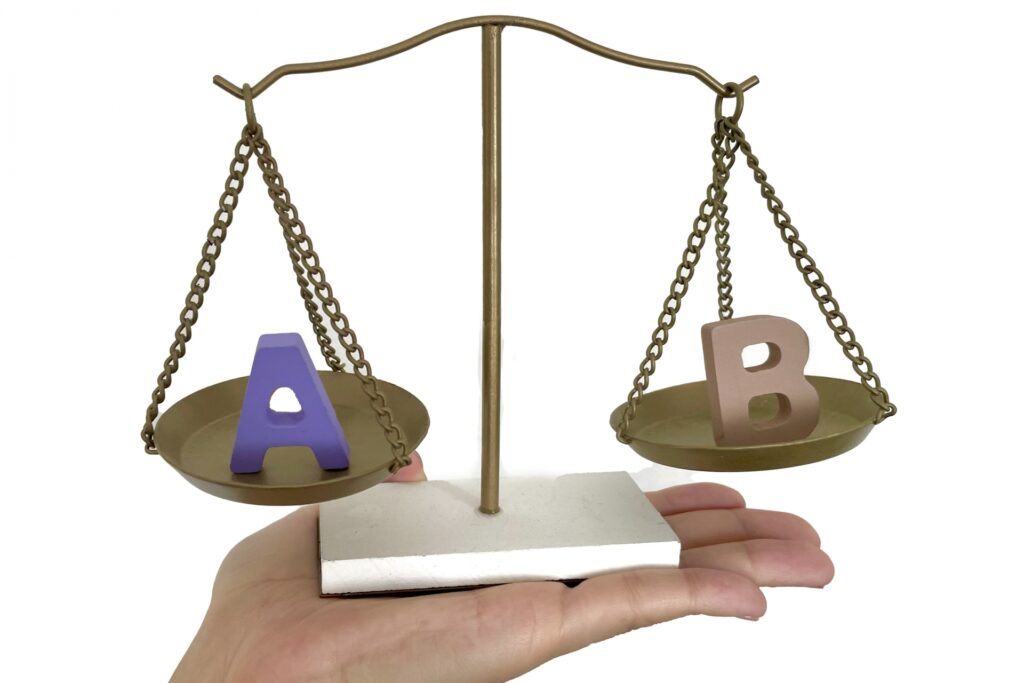
任意整理と自己破産とでは、手続を行うことによる効果や注意点など、さまざまな点で違いが見られるほか、共通するデメリットなどもあります。
そのため、どちらの手続を行うべきかは、以下のポイントを踏まえて検討するようにしましょう。
- 返済能力
- 手続の対象から除外したい債務の有無
- 手元に残したい特定の財産の有無
順にご説明します。
(1)返済能力
任意整理では、債務の支払義務自体がなくなるわけではなく、手続を行ったとしても返済を継続しなければなりません。
具体的には、継続的に収入があり、余裕をもって5年(60回払い)で完済できる見込みがあるならば、任意整理を行うことが適しているといえます。
反対に、継続的な収入がない場合や分割払いによっても完済を行うことが難しいほど債務総額が大きい場合には、任意整理ではなく、自己破産を行うことを検討した方がよいでしょう。
また、病気や怪我などを理由として、現在だけでなく将来的にも収入を得る見込みがない場合にも、自己破産を行うことを検討した方が望ましいです。
もっとも、債務者自身では、支払を継続できるかどうかを客観的に判断することが難しいことも考えられます。
そのような場合には、どのような解決方法が適しているかについて、専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
(2)手続の対象から除外したい債務の有無
債務整理の対象から除外したい債務があるかどうかも1つの基準になります。
自己破産では、すべての債務が手続の対象となるため、住宅ローンや車のローンなどの残債務がある状態で自己破産を行うと、住宅や車などを手放さなくてはなりません。
また、保証人や連帯保証人がついている債務についても手続の対象に含まれることから、それらの人物などに支払を強いることにもなります。
一方、任意整理では、上記のような債務を手続から除外して、保証人への影響などを回避することが可能です。
保証人への影響などから、特定の債務を手続から除外したい場合には、任意整理を行うことが適しているといえます。
もっとも、任意整理の手続から除外した債務については、これまでの契約内容に従った返済を行う必要があるため、その点については留意しておきましょう。
(3)手元に残したい特定の財産の有無
手元に残したい特定の財産の有無も1つの判断材料です。
自己破産では、ローンを完済している住宅や車、バイクなどについては、20万円を超える場合には原則として換価処分がされてしまいます。
一方、任意整理では債務者の財産については換価処分が行われず、住宅や車などを手放さなければならないという事態には陥りません。
そのため、特定の財産について手元に残して手続を行いたい場合には、任意整理を行うことが適しているといえます。
特に、車やバイクが換価処分されてしまうと生活や仕事への大きな影響が生じるという場合には、自己破産ではなく任意整理を行うことで、手続による不利益を回避することが可能です。
5.弁護士に相談・依頼するメリット

上記のように、任意整理と自己破産のどちらを行うべきかについては、それぞれの手続のメリット・デメリットを比較しながら検討する必要があります。
しかし、個別具体的な事情によって、どちらの手続を行うことが望ましいかは異なり、ご自身で判断することが難しいことも多いです。
そのような場合には、まずは専門家である弁護士に相談することが大切です。
債務整理について、弁護士に相談・依頼するメリットには、以下のものが挙げられます。
- 収入や借入状況に応じた最適な解決方法の提案を受けられる
- 債権者からの督促や取立てがストップする
- 手続の準備や対応についてサポートを受けることができる
順にご説明します。
(1)収入や借入状況に応じた最適な解決方法の提案を受けられる
弁護士に相談することで、収入や借入状況、財産状況に応じた最適な解決方法の提案を受けることができます。
これまで任意整理と自己破産の違いを述べましたが、どちらを行うことが望ましいのかは、債務者の借入額や収入、財産状況などによって異なります。
債務整理の経験のある弁護士であれば、債務者の支払能力や財産状況などから適切な解決方法を判断することができます。
そのような弁護士へ相談すれば、どちらを選択すべきかについての的確なアドバイスを受けることが可能です。
(2)債権者からの督促や取立てがストップする
債務整理の依頼を受けた弁護士は、債権者に対して受任通知を送付します。
この受任通知の送付を受けた債権者は、債務者に対して直接の督促や取立てを行うことができなくなることが法律上定められています。
弁護士に手続を依頼し、受任通知が債権者に送付されることで、債権者からの督促や取立てから解放されるので、精神的なストレスも緩和されるでしょう。
また、ほとんどの場合、弁護士の介入により、一時的な返済の猶予を受けることができます。
裁判所費用や弁護士費用について、返済の猶予を受けている間に積み立てて準備することもできるようになります。
(3)手続の準備や対応についてサポートを受けることができる
弁護士に手続の準備や対応についてサポートを受けることができます。
任意整理を行う場合には、債権者と直接交渉を行わなければなりません。
しかし、債務者自身で手続を行うと、交渉に応じない債権者もいるほか、知らないうちに不利な条件で債権者と合意してしまうリスクもあります。
そうすると、任意整理を行ったとしても、債務の負担を軽減することにならない可能性もあります。
また、自己破産に関しては申立ての際にさまざまな書類や資料を用意する必要があり、裁判所とのやり取りも適切に行わなければなりません。
手続を適切に進めるためには、法的知識はもちろん、実務経験が求められる場面も多くあり、対応を誤った場合には免責許可を受けられないリスクがあります。
弁護士に手続を依頼することで、書類作成や資料収集などの準備から債権者や裁判所への対応まで、サポートを受けることができます。
特に債務整理に慣れた弁護士に依頼することで、要点をおさえたサポートを受けることができるため、手続が成功する可能性を高めることもできます。
まとめ
任意整理と自己破産はどちらも債務整理の手段ですが、手続の条件や対象、財産の処分内容、費用など異なる点がいくつもあります。
そのため、どちらを行うかは、返済能力や手続の対象から除外したい債務の有無、手元に残したい特定の財産の有無などで選択することが一般的です。
債務者自身で適切な手続を判断できない場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士であれば、債務者ごとに最適な解決方法を判断することができるほか、要点をおさえた対応を行うことで、手続が成功する可能性を高めることも可能です。
弁護士法人みずきは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、任意整理や自己破産を行うことを検討されている方はお気軽にご相談ください。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事





























