交通事故における定期金賠償方式とは?
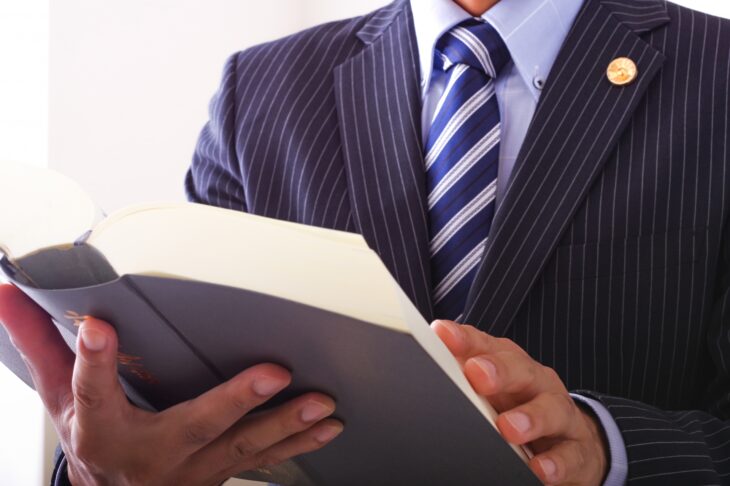
「交通事故の賠償に関する定期金賠償方式ってなに?」
「定期金賠償方式による賠償を請求する際の注意点は?」
交通事故に遭い、これから損害賠償請求をしようとしている方の中には、定期金賠償という言葉を耳にしたことがある方もいるかもしれません。
賠償金の支払いは、原則、すべての損害項目について計算したうえで一括払いとする一時金賠償方式です。
しかし、将来発生する損害項目については、一括ではなく毎月支払義務が発生する定期金賠償方式による賠償が認められる場合があります。
具体的には、将来介護費や逸失利益については、判例で定期金賠償が認められたものもあります。
本記事では、損害賠償における定期金賠償方式の特徴や賠償になじむ損害項目、定期金賠償のメリットやデメリットなどについてご説明します。
1.定期金賠償の概要と対象となりうる損害項目

交通事故における損害賠償は、原則として一時金による賠償(一括払い)です。
逸失利益などの将来にわたって発生する損害も、事故発生時に発生していると考えて計算されます。
もっとも、高次脳機能障害などの重度の後遺障害を負ったようなケースなどでは、一括で賠償金をもらっても将来必要となった時に残っているか等の不安が生じます。
そのため、例外的に定期金賠償方式が認められることがあります。
以下では、定期金賠償の概要や示談金に含まれる損害項目の中でも定期金による賠償となる可能性があるものを紹介します。
(1)定期金賠償とは
定期金賠償とは、一定期間において繰り返し賠償の履行が行われることをいいます。
交通事故の損害賠償については、様々な損害項目が含まれますが、それらがすべて事故のときに発生し、具体的な損害額が確定するものとして、一括で支払う一時金賠償がほとんどです。
しかし、中には将来発生する損害も含まれており、そのような損害については交通事故が生じた時点で厳密に損害額を確定することは困難です。
そのため、一定期間にわたって毎月損害が発生し、そのたびに損害額が確定していくものとして支払いを行う方法が定期金賠償です。
この意味で、定期金賠償は一時金賠償の分割払いとは異なるものであることを押さえておきましょう。
(2)定期金賠償が認められる可能性がある損害項目
損害賠償の中には、様々な損害項目が含まれています。
上記のような定期金賠償の性質に鑑みて、以下のような項目については定期金による賠償が認められる場合があります。
- 将来介護費
- 後遺障害逸失利益
順に見ていきましょう。
#1:将来介護費
将来介護費とは、後遺障害を負ったことによる将来にわたる介護費用です。
介護の必要性については、被害者の後遺障害の内容や程度、日常生活における不都合の度合いなどを基準にして考慮・判断がなされます。
例えば、半身不随になってしまったような場合には、日常的に介護士を雇わなければならないかもしれません。
このような場合、介護費用は月額〇〇円という形で発生していくため、定期金賠償の方式に馴染みます。
また、この方式によると、将来の症状の変化や介護の実態に合わせて受け取る金額を変更することができます。
さらに、一時金方式の場合には平均余命を基に総額を計算することになりますが、定期金賠償方式の場合には、被害者が死亡するまで賠償が継続することになります。
#2:後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって、本来であれば将来得ることができたであろう収入から減少した損害を指します。
収入は給与を例に考えてみると、毎月一定額が発生します。
その一定額に対する減少であると考えると、毎月発生し続けるものといえそうです。
逸失利益が定期金賠償方式による支払いの対象になるかは議論があるところでしたが、令和2年に最高裁が定期金賠償方式による賠償を認めました(最判令和2年7月9日民集74巻4号1204頁)。
2.定期金賠償のメリット・デメリット

定期金による賠償には、一時金賠償と比較するとメリットやデメリットがあります。
以下でそれぞれまとめていますので、見ていきましょう。
(1)定期金賠償によるメリット
定期金による賠償には、以下のようなメリットがあります。
- 中間利息が控除されない
- 被害者の実態に即した賠償がされる
順にご紹介します。
#1:中間利息が控除されない
後遺障害逸失利益や将来介護費など、本来は将来生じる損害を一時金賠償として算定する場合、中間利息が控除されます。
これは、将来発生するはずの金額を現在にまとめて受け取ることによる、価値の調整を目的にしています。
ごく単純に言えば、今すぐにもらえる100万円と、1年後にもらえる100万円は、今すぐにもらえる100万円の方が価値が高いと考えられるため、本来1年後にもらうべき100万円を今貰うなら95万円にしましょう、というようなことになります。
この中間利息の控除というのはライプニッツ係数というものを用いてややこしい計算を行うことになります。
例えば月額10万円の損害が10年間発生するという場合、単純計算すれば以下のようになります。
10万円×12ヶ月×10年=1200万0000円
しかし、中間利息の控除をする場合には、以下のようになります。
10万円×12ヶ月×8.5302(10年間のライプニッツ係数)=1023万6240円
そのため、その差は176万円にもなります。
これに対して、定期金賠償では毎月損害が発生するものとされるため、中間利息の控除が行われません。
そのため、一時金賠償と比べて、受け取れる総額が減少しないという点が大きなメリットです。
#2:被害者の実態に即した賠償がされる
一時金賠償においては、本来将来発生する損害についても現在時点を基準に計算します。
そして、この支払がなされれば、その後の状況変化は基本的には関係ありません。
そのため、被害者の症状や物価などに変化が生じたとしても、これを損害額に反映することは原則としてできません。
これに対して、定期金賠償では毎月支払いを受けることができるため、状況が大きく変わりこれまでの定期金額が不相当となった場合には賠償額を変更するなどの対応が可能となります。
このような対応は、損害の公平な分担という、損害賠償制度が目指すべき目的にも整合するといえます。
(2)定期金賠償によるデメリット
定期金による賠償には、以下のようなデメリットもあります。
- 相手方の支払いが滞るリスクがある
- 定期金の額が減少する可能性がある
- 定期的な接触による精神的ストレス
順にご説明します。
#1:相手方の資力悪化のリスクがある
定期金賠償は、判決が下った後、将来にわたって継続的に支払いをしてもらう必要があります。
この間に加害者や保険会社の支払いが滞るリスクがあります。
任意保険がついていれば、資産状況が悪化して払えなくなることはないだろう、とも思えますが、保険会社が数十年先まで安泰かというと、確実とは言えません。
そのため、支払いの終期に到達する前に加害者の自己破産や保険会社の経営破綻などが起こった場合には、残りの賠償金を受け取れないリスクがあることがデメリットとして挙げられます。
#2:定期金の額が減少する可能性がある
支払いの終期までに平均収入の低下や被害者の症状の回復などの事情があれば、その事情が金額に反映されて減額される可能性もあります。
これは、メリットの部分でも述べた事柄と表裏一体の関係にあるといえます。
#3:定期的な接触による精神的ストレス
定期金賠償方式の場合、保険会社や加害者から定期的に入金がなされることになります。
また、将来介護費等の賠償の場合、被害者が存命であるか、介護費用に変動はないかなどの確認が定期的になされるでしょう。
そのため、被害者やその家族にとっては、加害者側からの連絡のたびに事故のことを思い出すなどの精神的ストレスがあります。
このような心理的負担についても、デメリットとして挙げられます。
3.定期金による賠償を請求する際の注意点

定期金賠償方式による支払いを請求する場合には、いくつか注意点があります。
具体的には、以下のようなポイントです。
- 定期金賠償の対象となっている損害項目の確認
- 支払いの終期の定め方
リスクと対処法について押さえたうえで、適切に対応していきましょう。
(1)定期金賠償の対象となっている損害項目の確認
定期金賠償の対象となりうる損害項目は、将来介護費と後遺障害逸失利益など限定的なものです。
そのため、定期金方式による賠償の対象としている損害項目にこれら以外が含まれていないかを確認する必要があります。
たとえば、入通院慰謝料であれば、すでに損害額が確定しているものなので、これを定期金による賠償で受け取ることはできません。
(2)支払いの終期の定め方
定期金賠償による支払いの終期の定め方についても注意が必要です。
具体的には、将来介護費の支払終期は死亡時までですが、逸失利益に関しては67歳に到達するまでの期間となります。
このように、損害項目だけでなく、支払いの終期についての考え方も押さえたうえで、適切に請求を行う必要があります。
まとめ
本記事では、交通事故の損害賠償に関する定期金賠償方式の概要や対象となりうる損害項目、メリットやデメリット、賠償を受ける際の注意点についてご説明しました。
定期金による賠償には適切な損害の賠償という観点からメリットがある一方で、保険会社などの資力悪化による回収困難などのデメリットも存在します。
交通事故の損害賠償に関する交渉でお悩みの方は、まずは弁護士へ相談してみることをおすすめします。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの交通事故の問題やその後の交渉に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、交通事故に遭われた方はお気軽にご相談ください。
交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・

- ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
- ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。
関連記事

















