自己破産と税金の関係は?滞納するリスクと支払えない場合の対処法について弁護士が解説

「自己破産は税金を対象にして行うことができるのか」
「自己破産をしたら滞納している税金はどうなるのか」
自己破産を行うことを検討されている方の中には、滞納している税金がどうなるのか気になっている方もいると思います。
自己破産は、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、裁判所から免責許可決定を受けることによって、借金の返済義務を免除してもらう手続です。
返済義務が免除されるのは、金融機関などの法人や業者に対する債務だけでなく、親族や友人などの個人に対する債務も含まれます。
もっとも、すべての債務について返済や支払が免除されるわけではなく、中には免責許可決定を受けたとしても免除を受けられない債務があり、税金の支払義務がその代表例です。
また、税金以外にも免除を受けられないものがあり、「非免責債権」と呼ばれています。
本記事では、自己破産と税金の関係性や税金を支払えない場合の対処法などについて解説します。
なお、自己破産の手続の流れや自己破産を行うための要件などについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
1.自己破産を行うと税金の支払義務は免除されるか
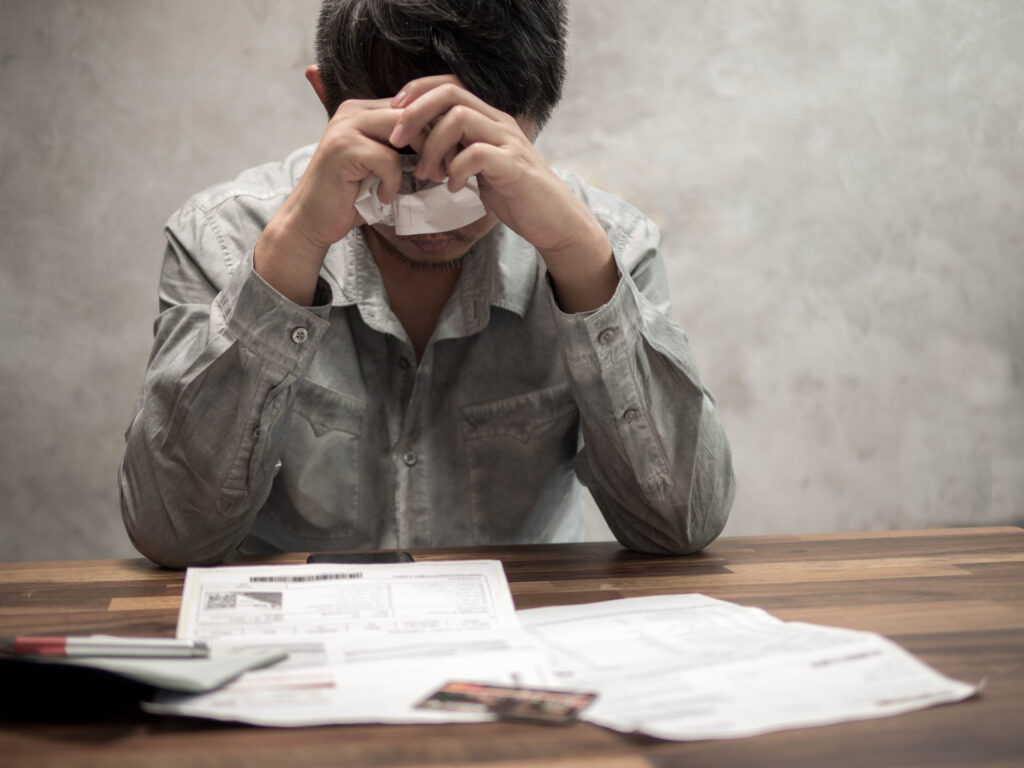
結論からいえば、自己破産を行っても税金の支払義務は免除されません。
そのため、自己破産を行う前に滞納していた税金がある場合には、自己破産を行って免責を受けたとしても、支払わなければならないことに注意が必要です。
具体的には、以下のようなものについては支払義務が残ります。
- 所得税
- 住民税
- 固定資産税
- 国民年金保険料
- 国民健康保険料
- 下水道料金 など
下水道料金は厳密には税金ではないものの、公益性が高いことから非免責債権に含まれています。
なお、これらの支払義務についても、通常の債権と同じく消滅時効があります。
消滅時効とは、一定期間にわたって支払わずにいた場合に、時効を援用することによって支払義務を免れることができる制度です。
税金の支払義務については、通常の納付期限から5年を経過すると、時効によって消滅します(国税通則法72条)。
もっとも、税金を滞納した場合には、督促状が送付されるのが通常であり、この督促状には時効の進行をストップ(完成猶予)させる効力がある点に注意が必要です。
さらに、督促状を受け取った時点から10日が経過することによって、今まで進行していた時効期間がリセットされることになります(時効の更新)。
このように、税金の支払義務が時効によって消滅することは事実上ありえません。
そのため、自己破産を行ったとしても、上記のような支払義務については引き続き残ってしまうことを押さえておきましょう。
2.税金以外の非免責債権

先ほど述べたように、税金の支払については非免責債権に該当するため、自己破産を行っても支払義務を免れることはできません。
また、非免責債権には、税金以外にも以下のような債権が含まれます(破産法253条)。
- 一部の不法行為に基づく損害賠償請求権
- 夫婦間の協力および扶助、婚姻費用の分担の義務に関する請求権
- 子の扶養および監護の義務に関する請求権
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および預り金の返還請求権
- 破産者が知りながら債権者一覧に記載しなかった請求権
- 罰金等
順にご説明します。
なお、非免責債権の種類については、以下の記事でも詳しく解説しているので、合わせてご参照ください。
(1)一部の不法行為に基づく損害賠償請求権
不法行為に基づく損害賠償請求権の中でも、悪意による不法行為や故意または重大な過失による不法行為に関するものは、非免責債権とされています。
そのため、上記のような損害賠償義務を負っている場合には、自己破産を行っても、支払義務の免除を受けることができません。
具体的には、「積極的な加害意思をもって行った不法行為による賠償債務」と、「故意または重大な過失によって人の生命・身体に対する不法行為を行ったことによる賠償債務」が、免責されません。
非免責債権に該当するかどうかの判断は難しいので、弁護士に相談して確認することがおすすめですが、単なる交通事故や不倫の賠償債務は免責される可能性が高いです。
なお、自己破産における慰謝料請求権の取り扱いについては、以下の記事も参考になります。
(2)夫婦間の協力および扶助、婚姻費用の分担の義務に関する請求権
夫婦間の協力および扶助、婚姻費用の分担の義務に関する請求権も非免責債権とされています。
そのため、自己破産をしても支払義務を免れることができない点を押さえておきましょう。
なお、具体的な金額については、家庭裁判所での調停や審判によって定めることができます。
また、当事者間で合意をすることができれば、合意に基づいて支払を行うことになります。
(3)子の扶養および監護の義務に関する請求権
子どもの扶養に関する費用や養育費の支払義務などは非免責債権にあたるため、自己破産後も支払を免れることはできません。
なお、自己破産を行う前から滞納している場合には、自己破産の手続において配当が行われ、差額分について支払義務が残ることになります。
また、自己破産後に到来する養育費の支払分については、手続の対象外となることから、滞納分と合わせて支払う必要があることに注意が必要です。
養育費の支払義務と自己破産手続の関係や支払うことができない場合の対処法については、以下の記事も合わせてご参照ください。
(4)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および預り金の返還請求権
未払の給与や退職金なども非免責債権にあたります。
これらの支払義務についても免責を与えてしまうと、使用人(従業員)の損失が大きく、生活に影響を与える可能性が高いからです。
そのため、個人事業主が従業員を雇用している場合に自己破産を行うと、従業員の給与などについては、引き続き支払を行う義務を負うことを押さえておきましょう。
なお、個人事業主の方が自己破産をはじめとする債務整理の手続を行う際の注意点については、以下の記事も参考になります。
(5)破産者が知りながら債権者一覧に記載しなかった請求権
破産者が知りながら債権者一覧に記載しなかった請求権も非免責債権です。
債権者一覧とは、自己破産を申し立てる際に裁判所に提出する書類であり、債権者をすべて記載する必要があります。
記載された債権者には、自己破産の手続において免責について意見を述べる機会が保障されますが、記載されなかった債権者にはそのような機会が与えられません。
そのため、債権者保護の観点から、債権者一覧に記載されなかった債権については、非免責債権となることに注意が必要です。
なお、債権者一覧にあえて特定の債権者を記載しなかった場合、免責不許可事由に該当してしまいます。
そうすると、記載しなかった債権だけでなく、ほかのものについても返済義務が免除されなくなってしまうリスクがあるため、注意が必要です。
このように、自己破産手続においては注意すべきポイントが多岐にわたります。
手続全般の注意点については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
(6)罰金等
法律違反等によって科された罰金や科料、過料なども非免責債権となります。
これらについては、刑事や行政上の制裁としての性質も持っているため、自己破産によって免責を与えることは適切ではないと考えられています。
そのため、自己破産を行い、免責を受けることができたとしても、罰金については支払義務を負ったままとなるため、注意が必要です。
3.自己破産後に税金を滞納するリスク

税金の支払義務は自己破産によっても免除されないだけでなく、放置することで差押えなどが行われるリスクが高まります。
ただし、滞納したからといって、直ちに差押えが行われるわけではありません。
具体的には、以下のような流れで手続が進行します。
- 延滞税・延滞金が発生する
- 督促や催告が行われる
- 滞納処分が行われて財産を差し押さえられる
なお、通常の債権であれば、債権者は訴訟などの法的手続によって勝訴の確定判決などの債務名義を取得した上で差押えなどの手続に移行します。
しかし、税金の場合には行政機関が滞納処分と呼ばれる手続を行い、債務名義の取得を待たずに直ちに差押えなどの手続に移ることが可能です。
そのため、税金の支払を滞納すると、最短で1か月程度で差押えが行われることが多いため注意しましょう。
(1)延滞税・延滞金が発生する
まず、税金を滞納すると、支払期限の翌日から延滞税や延滞金が発生します。
これは、支払期限から日数が経過するごとに加算されていくため、支払を行わない限りは延滞税の金額も増加していく点に注意しましょう。
そのため、最終的に支払うべき金額がもとの税額よりも大きくなってしまうことに注意が必要です。
(2)督促や催告が行われる
支払期限を経過しても納付が行われない場合には、督促や催告が行われます。
地方税なら期限から20日以内、国税なら期限から50日以内に督促状が送付されるのが一般的です。
督促状が送付されてから10日が経過すると、法律上では差押えを行うことができるようになります。
ただし、法律上で差押えができる状況でも、いきなり差押えが行われるわけではなく、催告書が送付され、自発的な支払を促すことが多いです。
(3)滞納処分が行われて財産を差し押さえられる
催告書が送付されても支払をしなかった場合、差押通知書が送付され、財産が差し押さえられてしまいます。
差押えの対象となる財産には、預貯金や給与などが挙げられます。
催告書を無視すると、これらの財産を失ってしまう可能性があるので、早急に対処しましょう。
4.税金を支払えない場合の対処法

税金を支払えない状態が続くと、差押えによって財産を失うリスクが高まってしまいます。
特に自己破産を行ったものの、滞納している税金が支払えない場合には、適切な対応を行うことが重要です。
もし税金を支払えない場合は、以下のような対処法を検討してみましょう。
- 自己破産の手続中に支払う
- 役所や税務署に相談する
順にご説明します。
(1)自己破産の手続中に支払う
すでに税金などの滞納がある状態で自己破産を行う場合、自己破産の手続中に滞納分を支払える可能性があります。
自己破産は、裁判所を通して行う手続であるため、債務者ご自身で手続を行うことには困難が生じることが多く、弁護士に手続を依頼することが一般的です。
弁護士に自己破産の手続を依頼すると、各債権者に対して受任通知が送付されます。
受任通知には、債権者からの督促や取立てをストップさせる法的効力があるため、一時的に債権者への返済が止まり、今まで返済に充てていた金額を滞納した税金の支払に回すことが可能です。
なお、自己破産においては、すべての債権者を平等に扱う「債権者平等の原則」という考え方に基づいて手続が進められます。
そのため、通常であれば、特定の債務について優先的に支払を行うこと(偏頗弁済)は、債権者平等の原則に反するため禁止されていますが、税金は偏波弁済にあたりません。
そのため、自己破産の手続中であっても支払を行うことができます。
なお、公共料金については、非免責債権にあたるものもあれば、そうでないものもあります。
非免責債権に該当しない公共料金を支払ってしまうと、偏頗弁済となってしまう場合があるため、弁護士にあらかじめ確認を行った上で支払を進めることが最も重要です。
(2)役所や税務署に相談する
納付期限までに税金を支払うことができない場合は、役所や税務署に相談しましょう。
国や地方公共団体は、たとえすぐに税金を支払うことができなくても将来支払う意思を示すことで、納付の猶予などが認められるケースもあります。
役所や税務署の窓口で納税に関する相談ができるようになっているので、督促や催告を受けた場合には、絶対に放置するのではなく、相談した上で支払の猶予などを受けるようにしましょう。
まとめ
自己破産を行い、免責を受けることができたとしても、滞納していた税金の支払義務については免除されません。
所得税や住民税などの税金だけでなく、国民健康保険料や下水道料金等についても支払義務を引き続き負うことになります。
また、損害賠償金や養育費なども非免責債権となり、自己破産をしても支払義務が残る点に注意が必要です。
税金の滞納状態が続くと、督促や催告を受けるだけでなく、最終的には財産を差し押えられる可能性があります。
借金等で税金の支払が困難な場合は、自己破産の手続中に支払うか、役所等の窓口で相談するようにしましょう。
また、自己破産の手続ではほかにもさまざまな注意点があります。
スムーズに手続を進めるためにも、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、自己破産を行うことを検討されている方はお気軽にご相談ください。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事
























