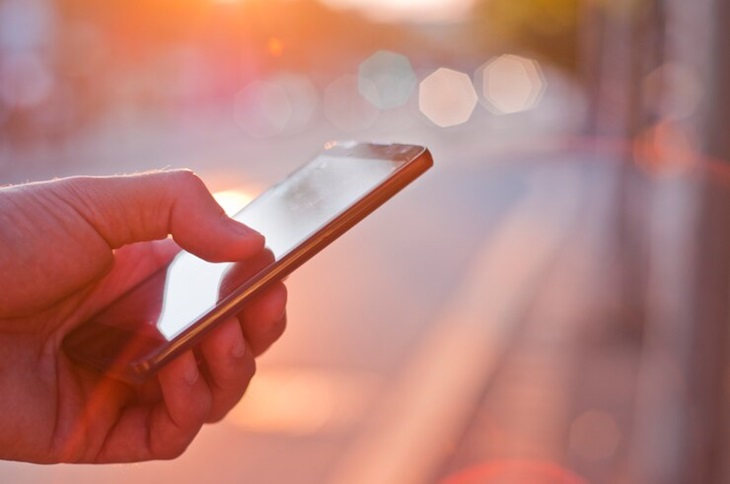相続における養子縁組とは?メリットやデメリットについてもご紹介

「養子縁組をした場合、相続にどのような影響があるの?」
「養子縁組の相続に関するメリット・デメリットは?」
養子縁組の制度を利用することで相続にどのような影響が生じるのかが気になる方もいらっしゃると思います。
本記事では、養子縁組について普通養子縁組と特別養子縁組の違い、養子縁組をした場合の相続がどうなるのか、また、養子縁組をした場合の相続に関するメリット・デメリットをご紹介します。
1.養子縁組とは

養子縁組とは、血縁関係とは無関係に血縁関係がないものとの間にも親子関係を持つことができる制度です。
養子は、養子縁組をすることで実子と同様法定相続人になり、親の財産を相続することができるのです。
養子縁組において、普通養子縁組と特別養子縁組についてご説明します。
(1)普通養子縁組
普通養子縁組とは、実親との法律上の親子関係を維持したまま新たな親子関係を生じさせる養子縁組を指します。
養親と養子の同意により成立します。
普通養子縁組の制度を利用した場合、養親との法律上の親子関係が成立する上、実親との親子関係も解消されることなく維持されます。
ですので、普通養子縁組では養親・実親が亡くなった場合、どちらの場合でも養子が法定相続人になることができます。
普通養子縁組は誰もがなれるわけではなく、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 養子縁組をする意思が合致していること
- 養親が成年者であること
- 養子が養親よりも年下であること
- 養子が養親の叔父や叔母といった尊属ではないこと
- 養子が未成年である場合は家庭裁判所の許可を得ていること
普通養子縁組においては、以上の他にも様々な要件があり、要件を満たしている者に限って制度を利用することができます。
普通養子縁組の特徴は、実親との法律上の親子関係に影響を与えないため、養子になった後でも実親の遺産を相続できる点です。
また、普通養子縁組においては複数人の養子になることも可能です。
(2)特別養子縁組
特別養子縁組とは、未成年者の福祉のために特に必要が生じた場合に未成年とその実親との法律上の親子関係を消滅させ、養親との間に法律上の親子関係を生じさせる制度です。
特別養子縁組は普通養子縁組とは異なり、実親との法律上の親子関係がなくなってしまいます。
つまり、特別養子縁組で養子になった者は養親の財産を相続することはできますが、実親の財産を相続することができなくなるのです。
特別養子縁組では、普通養子縁組とは異なり、家庭裁判所の決定が必要です。
特別養子縁組の要件は、以下のとおりです。
- 実親の同意があること。ただし、父母による虐待など子の利益を著しく害する事由がある場合は同意不要
- 養子となる者は、原則として15歳未満であること
- 実親の監護が困難または不適当であり子のために特別養子縁組が必要であること
このように、特別養子縁組は強力な効果を持っていることから、家庭裁判所がその適否を判断する手続きとなっています。
2.養子縁組をした場合の相続はどうなるのか

養子縁組の制度を利用した場合の相続について順にご説明します。
(1)養子が養親よりも先に死亡した場合の代襲相続について
養子が養親よりも先に死亡していた場合、養子の子どもが代襲相続する可能性があります。
代襲相続とは、本来相続人となる者が相続開始以前に死亡したり、一定の事由(相続欠格、排除)によって相続権を失った場合に、その者に代わって相続することを言います。
代襲相続ができるのは、被相続人(相続される人)の直系卑属(子ども、孫など)に限られます。
養子の子どもが代襲相続できるのは、養子の子どもが、養子縁組前に出生していた場合です。
この場合、養子の子どもは、被相続人(養親)の直系卑属だといえるため、代襲相続することができるのです。
一方、養子の子どもが、養子縁組前から出生していた場合、養子の子どもは、被相続人(養親)を代襲相続することができません。
養子縁組によって、養親と既に出生していた養子の子どもとは血族関係が生じないため、このような違いが生じていることになります。
(2)特別養子縁組の場合実親の遺産は相続できない
特別養子縁組の場合、養親の養子となった者は実親の遺産を相続できません。
上記のとおり、特別養子縁組の場合、実親との法律上の親子関係が消滅するため、実親の相続人ではなくなるからです。
ですので、養親が亡くなった場合は法定相続人になることができますが、実親が亡くなった場合は法定相続人になることができません。
3.養子縁組の相続におけるメリット

養子縁組の相続における代表的なメリットとデメリットをそれぞれご紹介します。
(1)法定相続人ではない人へ相続できる
ご自身が法定相続人ではない人へ相続をさせたい場合、養子縁組を行うことで遺産を相続させることができます。
つまり、法定相続人ではない孫や血の繋がりのない者に対してでも、養子縁組が成立すれば直接財産を相続させられるのです。
もちろん、生前贈与や遺贈によって血縁関係にない人や法定相続人に含まれない親族に対して財産を残すことは可能です。
しかし、仮に生前贈与や遺贈をしたことにより、他の相続人の遺留分を侵害してしまった場合は、他の相続人から遺留分侵害額請求権を行使されることで、実際に受け取った人が手元に残すことのできる財産が減ってしまいます。
養子縁組が成立した場合、養子は法定相続人として相続を受けることになるので、遺留分侵害額請求権を行使されて相続分が減ることはないのです。
(2)相続税の節税対策になる
養子縁組によって法定相続人が増えることにより、相続税の基礎控除額が600万円(令和4年6月現在)増加する等の理由から、相続税の節税対策となります。
例えば、被相続人の遺産が1億円、(1)実子が2人の場合と、(2)実子が2人で養子が1人の場合を比較してみましょう。
(1)実子が2人の場合、単純計算で、相続税の基礎控除額が4,200万円となりますから、課税相続財産は、5,800万円、相続税総額は770万円となります。
(2)実子が2人で養子が1人の場合、相続税の基礎控除額が4,800万円となりますから、課税相続財産は、5,200万円、相続税総額は630万円となります。
かなり単純化しましたが、上記の例であれば、140万円の節税効果が見込まれるため、一定の節税効果があるといえます。
※具体的に養子縁組による相続税対策をされたい方は、税金の専門家である「税理士」へご相談されることをお勧めいたします。
(3)遺留分を圧縮させられる
養子縁組は、特定の相続人(遺留分権利者)の遺留分を圧縮させるというメリットもあります。
具体例で説明しましょう。
例えば、Aには、BとCという子どもが2人いて、Aの総資産(相続財産)は1億円、AとCが不仲であり、Aが生前、Bに対し、全ての財産を相続させる旨の遺言(「特定財産承継遺言」)をしていたとします。このような例は少なくないと思います。
Aの死後、Bは、Aの総資産1億円を全て相続することになります。
もっとも、Cには、遺留分が認められる(Aの総資産の4分の1=2,500万円が遺留分侵害額となります。)ため、Bは、Cから遺留分侵害額請求をされることにより、Cに対して2,500万円を支払わなければならないことになってしまいます。
ここで、Aが生前、Dと養子縁組をしていたとしましょう。
Cが遺留分権利者であることは変わりませんが、Cの遺留分はAの総資産の6分の1(=約1667万円が遺留分侵害額)となりますので、Cが遺留分侵害額請求をした場合に、Cに支払わなければならない金額が、およそ約833万円違ってくることになります。
このように、遺留分侵害額請求に備えて、養子縁組が活用されることもあります。
4.養子縁組の相続におけるデメリット
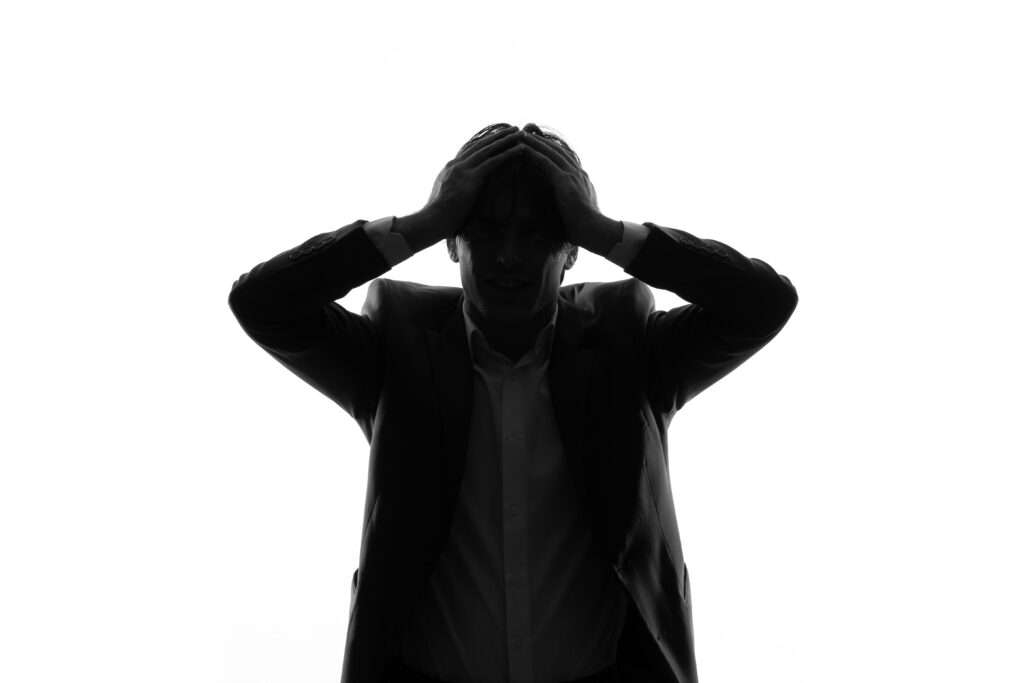
実子やその他親族との間でトラブルが起こる可能性があります。
養子縁組をすることにより、その他の実子や配偶者等の法定相続分や遺留分が減ってしまうことになります。
そのため、例えば、遺産分割調停において、養子縁組の有効性が争われることもあり、注意が必要です。
もしも子やその他の親族との間で、相続における養子に関するトラブルが発生しそうな場合は、専門家である弁護士へご相談ください。
5.相続と養子縁組に関するご相談は弁護士へ

相続と養子縁組に関するご相談は、専門家である弁護士へすることをおすすめします。
相続における養子縁組では、メリットもある一方で他の相続人と養子との間で紛争が起こる場合もあります。
遺産分割調停等でトラブルが発生すると、円満な相続をすることができなくなってしまいます。
また養子縁組をご検討の際は、実質的要件及び形式的要件を満たす必要があり、手続が複雑な場合もあります。
ですので、相続に関して養子縁組をお考えの方は、弁護士によるサポートを受けながら慎重に進めていくことを推奨します。
まとめ
本記事では、養子縁組と相続について、養子縁組の種類や相続時に与える影響などをご紹介しました。
相続に関する養子縁組は、それぞれの状況によってメリット・デメリットが異なるケースもありますので、まず一度弁護士へご相談ください。
関連記事