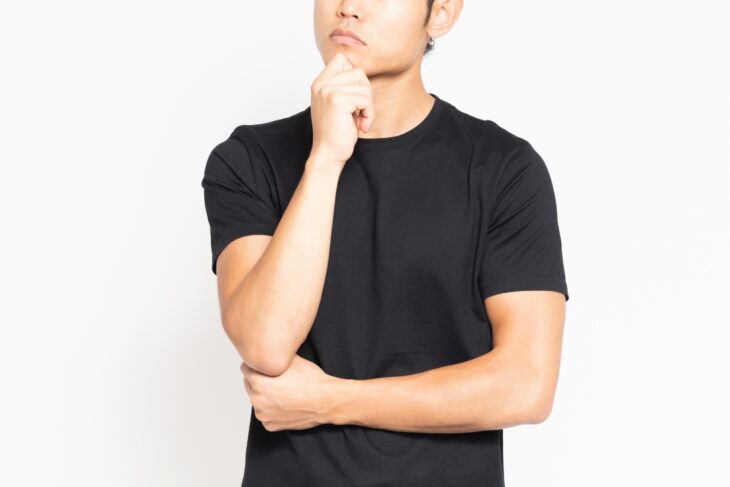個人再生に必要な家計簿の作り方とは?家計簿が必要な理由と作成時の注意点
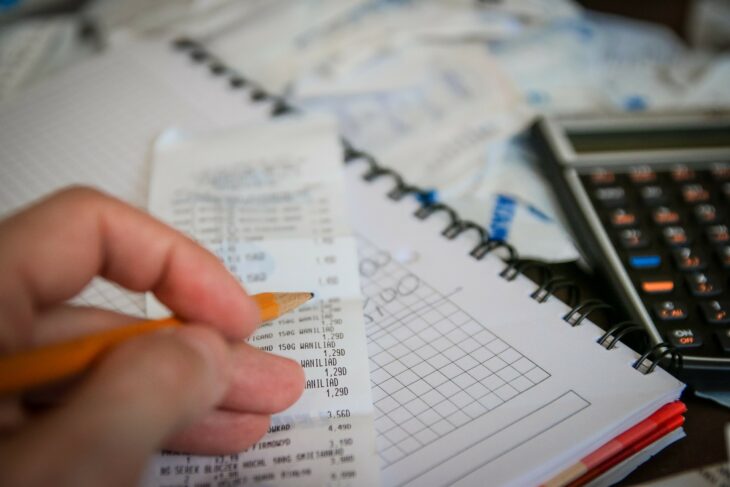
「個人再生で家計簿を作らないといけないって本当なのか」
「個人再生で必要な家計簿はどう作ればいいのか」
個人再生を行うことを検討している方の中には、家計簿が必要と聞いてどうしたらいいか分からず、困っている方もいるのではないでしょうか。
個人再生では、再生計画案が裁判所によって認可された後、原則3年にわたって再生計画の内容に従って返済を行わなければなりません。
そのため、個人再生を行うためには債務者に支払能力があることが前提となり、支払能力があるか否かを判断するために家計簿の提出が必要とされているのです。
本記事では、個人再生に家計簿が必要な理由や作成の流れについて解説します。
なお、個人再生は裁判所を通して行う手続であるため、手続を申し立てるためには一定の要件を満たす必要があります。
個人再生を行うための要件などについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
1.個人再生をするのに家計簿が必要な理由

個人再生を申し立てる際には、申立書類などと合わせて家計簿を作成し、裁判所に提出する必要があります。
その理由は以下のとおりです。
- 支払能力があるか否かを判断するため
- 偏頗弁済や財産隠しがないか確認するため
- 家族全員の収入を確認するため
順にご説明します。
なお、個人再生を申し立てる際に必要となる書類や資料については、以下の記事もあわせてご参照ください。
(1)支払能力があるか否かを判断するため
裁判所は、個人再生を申し立てた者に支払能力があるか否かを判断するために家計簿を確認します。
先ほども述べたように、個人再生は再生計画に従って原則3年(特別な事情がある場合には5年)にわたって減額された借金の完済を目指す手続です。
そのため、裁判所は申立人が今後継続して返済を行うことができるかどうかを判断した上で、再生計画案について認可するか否かを決定する必要があります。
具体的には、家計簿に記載された内容をもとに、収入に対して支出がどのくらいで余剰金がどのくらいあるのか、無駄な支出や生活費が過剰でないかなど様々な事情から、支払能力の有無を判断します。
また、収入の変動などの予期しなかった事態に陥ることで返済が滞らないように、貯蓄の有無なども確認されることを押さえておきましょう。
(2)偏頗弁済や財産隠しがないか確認するため
偏頗弁済や財産隠しがないか確認するために家計簿の提出を求められます。
偏頗弁済とは、一部の債権者にのみ返済することをいいます。
個人再生では、すべての債権者を平等に扱わなければならない「債権者平等の原則」を遵守する必要があります。
一部の債権者にのみ返済をすることは、この「債権者平等の原則」に反する行為であるため、禁止されているのです。
一方、財産隠しは、一部の財産を隠蔽し、虚偽の財産報告をすることをいいます。
個人再生は、借金全額を返済することが困難である場合の救済措置であり、債権者に不利益を被らせる手続です。
そのため、本当に借金全額を返済することが困難であるかを判断する必要があります。
財産隠しは、裁判所が債務者の所有財産を正確に把握し、借金全額を返済することが困難であるかを判断するという目的を阻害する行為なので、申立人の不誠実な対応と判断されます。
これらの行為を行ってしまうと、手続が廃止(終了)されてしまう場合があるため、特に注意が必要です。
なお、個人再生における偏頗弁済のリスクについては以下の記事も参考になるので、あわせてご参照ください。
(3)家族全員の収支を確認するため
家計簿の提出には、家族全員の収支を確認する目的もあります。
申立人の支出に問題がなかったとしても、配偶者や子供が浪費している場合には、申立人のみの収支状況を見ても支払能力の有無について正しい判断ができません。
そのため、家族全員の収支状況を確認する必要があるのです。
例えば、申立人本人が適切な支出を心がけていたとしても、同居家族の浪費などによって家計が圧迫されていた場合などには、支払能力があるとはいえないため、個人再生が認められない可能性があるのです。
そのため、申立人の収支状況だけではなく、同居している家族も含めた世帯全体の家計を記載する必要があることに注意が必要です。
もっとも、家族であっても家計が別になっている場合には、申立人の支払能力に関係がないため、その家族の収支状況を記載する必要はありません。
2.個人再生に必要な家計簿の作成の流れ

個人再生に必要な家計簿は、誰でも作成できるようになっています。
作成の流れは以下のとおりです。
- 個人再生用の家計簿フォーマットを入手する
- 指定の計上項目に関する情報を整理する
- 2か月分の家計簿を裁判所に提出する
順にご説明します。
(1)個人再生用の家計簿フォーマットを入手する
まずは、個人再生用の家計簿のフォーマットを入手しましょう。
家計簿のフォーマットは裁判所が提供しているので、管轄の地方裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
裁判所が提供しているフォーマットを必ず使用しなければならないわけではありませんが、家計簿を一から作成する手間を省くことができるので、こだわりがなければ裁判所のフォーマットをそのまま使うのがおすすめです。
(2)指定の計上項目に関する情報を整理する
家計簿のフォーマットを入手したら、家計簿に記入する項目を確認し、それに関する情報を整理しましょう。
記載しなければならない項目は大きく分けて収入と支出の2つです。
地方裁判所によって指定項目に多少の違いはありますが、主に収入と支出にはそれぞれ以下のような項目があります。
| 収入 | 支出 |
|
|
先ほども述べたように、世帯全員の収支状況を記入する必要があるため、間違いがないように一つずつ情報を整理していきましょう。
特に支出は、普段何にいくら使用したのか把握していない方も多いと思います。
そのため、個人再生手続をするとなった際には、何にいくら使用したのか分かるようにしておきましょう。
(3)2か月分の家計簿を裁判所に提出する
個人再生をする場合、申立時の直近2か月分の家計簿を提出する必要があります。
家計簿は、個人再生の申立時に裁判所に提出します。
一般的に個人再生の申立の準備には2~3か月程度かかるため、個人再生の準備を始めた時点で家計簿の作成をしましょう。
また、手続の期間中は、継続的に家計簿の提出を求められるため、提出するのは申立時の1回だけではありません。
一般的に、個人再生の手続期間は4~6か月といわれているので、時間のロスなく家計簿を提出できるように、手続期間中も早めに次の家計簿の作成に着手しておきましょう。
個人再生の手続に要する期間や流れなどの詳細については、以下の記事で解説しています。
3.家計簿を作るときの注意点

家計簿を作るときに気をつけなければならないことがいくつかあります。
主な注意点は以下のとおりです。
- すべての情報を正確に記載する
- 世帯全体の収支状況を報告する
- 領収書等を保管しておく
- 1円単位まで把握しておく
- 預金と現金を分ける
順に解説します。
(1)すべての情報を正確に記載する
すべての情報を正確に記載するように注意しましょう。
家計簿の内容に事実と異なる点があると、虚偽の報告をしたとして不誠実と判断され、申立が認められない可能性が高いです。
大雑把な計算をしていたり計算ミスをしていたりすると、手続がスムーズに進まないので、情報の正確性には注意を払いましょう。
(2)世帯全体の収支状況を報告する
世帯全体の収支状況を報告することが大切です。
先ほども述べたように、個人再生における支払能力は、申立人本人だけでなく家計を同じくする家族の収支状況も踏まえて判断されます。
そのため、申立人だけでなく、配偶者や両親などの収支状況についても報告が求められます。
例えば、子どもや両親も収入を得ている場合は、その収支に関する情報を漏れなく記載することが大切です。
(3)領収書等を保管しておく
支出した金額を証明できるように領収書等を保管しておくことも大切です。
水道光熱費や通信費などについては、家計簿と合わせて領収書の提出を求められます。
また、特に金額が大きいものについては、浪費等を疑われる可能性があるため、適切な支出であることを証明するためにも領収書が必要です。
場合によっては、水道光熱費以外の支出に関する領収書の提出を求められることがあるので、すぐに対応できるように一箇所にまとめておきましょう。
(4)1円単位まで把握しておく
金額は1円単位まで正確に把握しておきましょう。
裁判所は申立人の収支状況を正確に把握した上で再生計画案を認可するか否かを判断するため、その判断の基礎となる家計簿の金額はできる限り細かく記載することが望ましいです。
実際には給与や水道光熱費などの一部の費目を除いては1,000円単位で切り上げて記載することが多いですが、金額のズレが大きい場合には浪費や財産隠しなどを疑われる可能性もあります。
そのため、金額にズレがないかを確認できるように1円単位まで正確に把握しておくことが重要です。
(5)預金と現金を分ける
繰越額を記載するときは、預金と現金を分けることも重要です。
預金と現金の動きについて正確に把握しなければ、将来の収支をもとに再生計画を立てることが難しくなります。
繰越額の整合性を証明するために、預金通帳と齟齬が生じないようにしましょう。
まとめ
個人再生をする際は、裁判所に2か月分の家計簿を提出しなければなりません。
家計簿のフォーマットは裁判所が提供しているので、そこに記載されている項目に沿って情報を適切に整理することが大切です。
また、家計簿を大雑把に作成していると、実際の金額とズレが生じて、浪費や財産隠しを疑われる可能性があります。そうならないようにできる限り細かく計算しましょう。
もっとも、家計簿を作成する際には細かな点に注意を払わなければならず、ご自身で対応をすべて行ってしまうと、不備などが生じる可能性もあります。
個人再生を行うことを検討されている方は、手続をスムーズに進めるためにも、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、個人再生をはじめとする債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、個人再生における家計簿の作成でご不明な点がある方はお気軽にご相談ください。
債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

- ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
- ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。
関連記事