業務外の病気による休職・復職が生じた場合の休職制度について

「休職」とは、労働契約を存続させつつ、労働義務を一時的に免除することを言います。
法律上規定されている「産前・産後休業」「育児休業」「介護休業」などとは違い、必須ではありません。
もっとも、休職制度を採用するのであれば、これを明示する必要があります。
そのため、休職制度を採用するか否か、採用するとしてどのような内容にするかという点は、それぞれの使用者が判断し、労働協約や就業規則の中に明記することとなります。
労働義務を免除というと、労働者側にしかメリットがないようにきこえるかもしれません。
しかし、休職制度は使用者側・労働者側の双方にとってメリットがある制度です。
この記事では、休職制度についてご説明します。
休職制度を設けていないという医療機関の方は、是非一度読んでみていただければと思います。
1.休職制度とは

休職をどのような場合に認めるかという点も使用者の判断によりますが、一般に見られるのは以下のようなものです。
- 傷病休職(業務外の私傷病を原因とするもの)
- 事故休職(業務外の事故を原因とするもの)
- 起訴休職(刑事事件で起訴されたことを原因とするもの)
これらのうち、最も一般的なのが、傷病休職です。
2.休職制度のメリット

休職は、いずれの場合も、契約を解除することなく、労働義務を免除することになります。
つまり、傷病休職の場合、怪我や病気のために勤務できない者を、解雇や退職させることなく、契約を留保することになります。
一見、休職制度を採用するメリットがわかりづらいですが、労使ともにメリットがあります。
(1)労働者側のメリット
労働者側としては、就労が一時的に不能又は困難となっても、回復した後には復職することができます。
そのため、治療や療養に専念することができます。
(2)使用者側のメリット
使用者側としては、復職することが前提となれば、休職中の調整は必要とはなりますが、新たな人材を一から採用したりや教育したりするコスト・時間を節約することができます。
特に、医療機関では、医師、看護師、薬剤師、作業療法士等さまざまな資格者を雇用する関係上、退職後の穴埋めのために新たに適当な有資格者を見つけ出し採用するのは、一般企業よりも困難であることが少なくありません。
資格者以外でも、医療事務などは専門的な知識や経験を必要とすることから、同様のことが言えます。
3.休職制度の内容
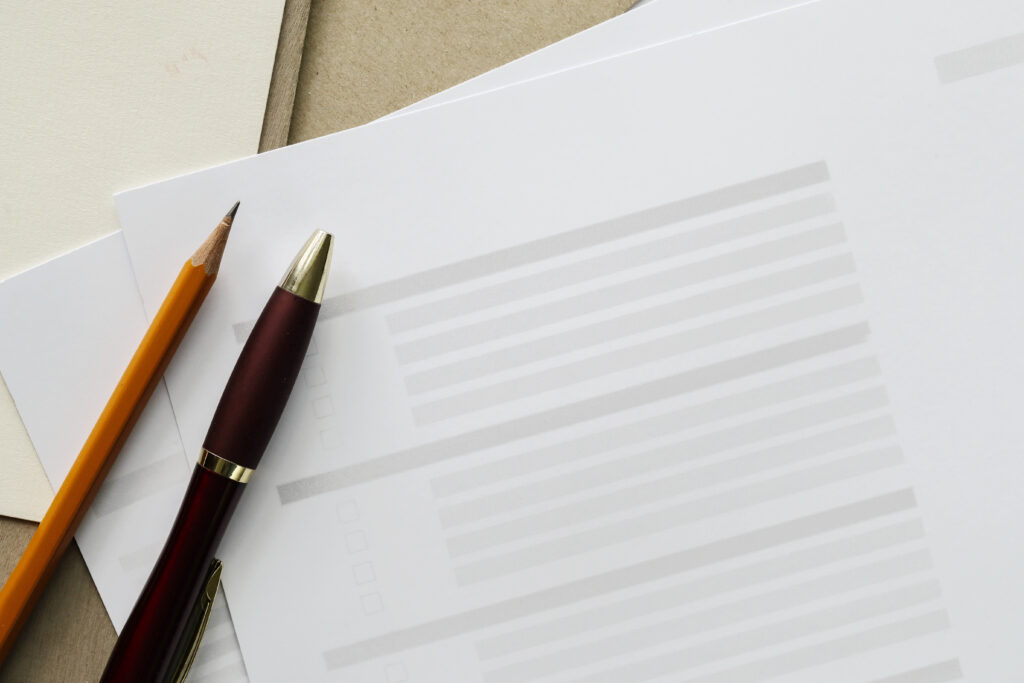
休職制度は、法的な規制がないので、不合理でない限りは使用者側が自由に決めることができます。
以下のような内容を決めておくことが多いです。
(1)休職事由
医師の診断書のみでよいか、産業医との面談を要するか
(2)休職期間
一律にするか、勤続年数によって差異を設けるか
(3)復職要件
どのような方法で傷病が治癒したと判断するか
(4)リハビリ勤務
復職の可能性を判断するために時短・軽作業勤務を認めるか
(5)退職への移行
どのような場合に復職が困難であるとするか、その場合の手続
まとめ
この記事では、休職制度のメリットとは何かと、休職制度を設けるにあたって取り決めておくべき事項についてご紹介しました。
休職制度を定めておくことは、使用者・労働者の双方にとってメリットがあることです。
時折「復職の目処のない休職者の対応に困っている」というご相談を受けることがありますが、休職制度をきちんと定めておくことでこのようなお悩みは解消されます。
当事務所では、休職制度の整備をはじめとした就業規則の作成サポートを行っています。
是非一度ご相談ください。
関連記事
















