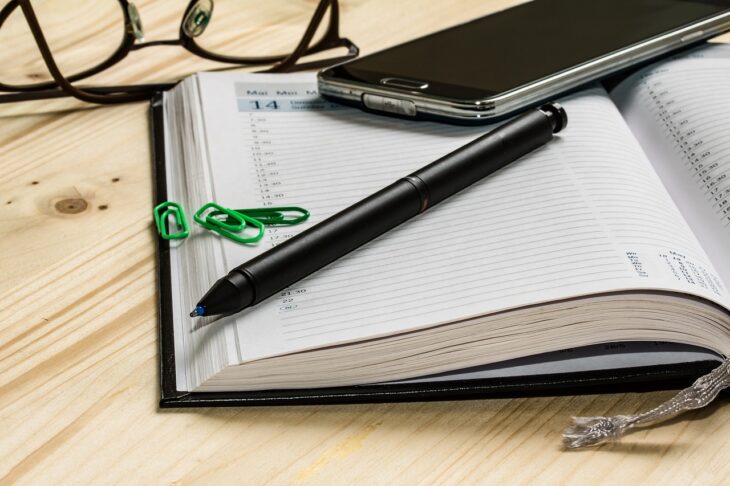M&Aによる事業承継について弁護士が徹底解説!

1.M&Aとは

M&Aとは、「Mergers」(合併)&「Acquisitions」(買収)の略です。
一昔前は、M&Aと聞くと、「会社を売るなんて信じられない」という反応をされる方が特に中小企業で多く見られました。
今でもそこまでの拒否反応は示さなくとも、中小企業の経営者の方や個人事業主の方では、「M&Aは上場企業だけのものでしょ。」などと考えている方も多くいらっしゃいます。
しかし、中小企業こそM&Aを活用するべきなのです。M&Aには、様々な使い方があります。
(1)攻めのM&A
スケールメリットが必要とされる事業分野ではM&Aが効果的です。
M&Aによって、仕入コスト、在庫コスト、販売コストなどを軽減して競争力をアップしたり、店舗のネットワークを拡充することで販売を拡大したりできます。
それ以外にも、人材、技術、許認可等を保有している会社を買収することで、効率的に経営の多角化を図ることができます。
(2)守りのM&A
後継者がいない人材不足、経営状態が悪化して資金不足になったときなどには、人材や資金を持っていて、その会社の技術や販路が欲しいという会社に、会社や事業を丸ごと買い取ってもらうことができます。
(3)海外進出のM&A
これからは国際化の時代であると言われるようになって久しいですが、海外での従業員や販路の確保は容易ではありません。
そんなときは、現地の会社を買い取ることでスムーズな海外進出ができます。
2.スキームの選択(ストラクチャリング)

一口にM&Aといっても、様々な種類があります。
どういった目的でM&Aをするかを明確にして、最も適切なスキームを選択する必要があります。
(1)資本移動を伴わないスキーム
#1:取引契約
ア 取引契約とは
取引契約とは、「業務提携契約」や「共同開発契約」など、会社同士で契約をし、取引をしたり、共同で事業を行ったりすることです。
イ 取引契約の必要性
M&Aは多くの金銭、人が動くので、失敗した場合には取り返しがつきません。
中小企業のM&Aでこのような失敗が起きるよくある原因は、「信頼関係の構築」という段階をおろそかにしていることにあります。
アドバイザーに全て任せてしまい、実際にM&Aをする当事者の会社同士では十分に信頼関係が構築できていないまま、手続が進んでしまうのです。
中小企業の多くは、社内や取引先の濃い人間関係の中で経営や業務が行われているので、お互いの信頼関係なしにM&Aは成功しません。
そこで、M&Aをいきなり行うのではなく、可能であればまずは「業務提携契約」や「共同開発契約」などを締結して、一定期間、実際に取引をしたり、業務を一緒に行ってみたりというモニタリングの期間を設けることをお勧めします。
#2:事業譲渡
ア 事業譲渡とは
事業譲渡とは、会社が特定の事業のみを取り出して他社に売却する方法で、中小企業のM&Aの中ではポピュラーな方法です。
たとえば、店舗を3つ持っている会社が、そのうちの1つの店舗の土地建物や什器、従業員などをパッケージとして売却する場合などがあります。
飲食店などで昔から行われている「居抜き」も事業譲渡の一種です。
イ 事業譲渡のメリット
・譲渡する資産や負債の切り分け可能:欲しい資産や引き継いでもいいと考えている負債のみを承継することができます。
・売却代金の取得:事業売却代金が手元に入ってきます。
・簡単な手続:事業譲渡契約のみ必要で、株主総会での議決や債権者への周知などは不要です。
(2)資本移動を伴うスキーム
#1:株式譲渡
ア 株式譲渡とは
株式譲渡とは、元々発行されている株式を買い手が買い取って経営権を取得する方法です。事業譲渡と並んで、中小企業のM&Aの中ではポピュラーな方法です。
イ 株式譲渡のメリット
・手続が簡単迅速:株式を売却するだけなので、手続が簡単で、時間的にも短期間で実行することができます。
・包括承継であること:個別の財産ごとに名義変更等を必要とせず、財産や経営権が包括承継されます
・取引の安定を維持しやすい:基本的には会社名、従業員はそのままで株主構成が変わるだけですので、外部から変化はわかりにくく、会社の信用や経営状態に影響を与えにくいことが多いです。
・許認可が影響を受けない:建設業や不動産業などの場合でも新たに許認可を取り直す必要はありません。
・買収資金の節約:最低でも過半数の株式を取得すれば経営権をほぼ取得できるので、コストが節約できます。
#2:新株発行
ア 新株発行とは
新株発行とは、新たに株式を発行して、買い手に買い取ってもらう方法です。
イ 新株発行のメリット
・売り手の資本増強:新たに発行した株式の対価が買い手から支払われます。
・手続が比較的簡易:売り手の会社の取締役会や株主に対する公示等で足りるので比較的簡易な手続です。
・売り手に反対株主がいても実行可能:反対株主がいても過半数の株式割合をとれれば実行可能です。
・取引安定、許認可の面でのメリットは事業譲渡と同じです。
#3:株式交換
ア 株式交換とは
株式交換とは、自社の株式を対価として交付する代わりに他社の株式すべてを取得する方法です。
イ 株式交換のメリット
資金が不要:自社の株式を対価とするので、買い手は資金を用意しなくても行えます
別法人としての運営:株式交換後も社内のシステム等を統合する必要がないので、異なる企業文化を保つことが可能です
#4:株式移転
ア 株式移転とは
株式移転とは、新たに持ち株会社を作り、1社又は2社以上の会社の発行済みの株式の全てを新たに作った持ち株会社に取得させる方法です。
イ 株式移転のメリット
資金が不要:株式交換と同様、新たな資金を用意する必要はありません。
スケールメリット:持ち株会社を作ることでグループ会社として統率がとれ、スケールメリットを活かした経営ができますし、取引先や金融機関等からの信用も得られることがあります。
#5:会社分割
ア 会社分割とは
会社分割には、株式会社又は合同会社が、事業の一部を切り離して新たな会社とする新設分割、事業の一部を他の会社に吸収させる吸収分割があります。
イ 会社分割のメリット
必要な部分だけ承継:既存の会社の特定の事業だけを選んで承継させられるのは、事業譲渡と同じです
包括承継:事業譲渡と異なるのは、分割する事業に関わる財産、従業員、契約上の地位、許認可等を個別に移転させる必要がなく、包括的に承継させられる点です。負債も全て移転されてしまいますが、有用な財産、人材を確実に取得できます。
#6:合併
ア 合併とは
合併には、2つの会社が1つになって新たな会社を作る新設合併と、1つの会社が存続して他の会社がそれに吸収される吸収合併があります。
イ 合併のメリット
スケールメリット:完全に同一の法人となるので、管理系の部門や仕入先を一本化するなどして経営の効率化が最も確実に図れます。取引先や金融機関等からの信用も高まることもあります。
包括承継:吸収合併では、消滅する会社の財産、従業員、契約上の地位、許認可等が包括的に承継されます。ただし、許認可では、行政当局からの個別の許可が必要な場合もあります。
3.M&Aの流れとデューデリジェンス

(1)M&Aの基本的な流れ
M&Aの基本的な流れは次のとおりです。
- 相手探し:M&Aの仲介業者を通して会社の売り手、買い手を探します。
- 検討段階:秘密保持契約を締結したうえで、お互いの会社の情報を開示します。
- 基本契約:お互いにM&Aに前向きであれば基本契約をし、独占交渉が始まります。
- デューデリジェンス:専門家によって財務、法務など様々な面から買収先を調査します。
- 本契約:デューデリジェンスの結果、問題がなければ本契約を締結します。
- M&A実行:実際にM&Aを実行します。
(2)デューデリジェンスの重要性と難しさ
M&Aをしてしまってから、買収先の思わぬリスクが発見されてしまうことは避けなければなりません。
多額の借入れや不良在庫が隠されている場合は珍しくありませんし、悪質な場合には、実は買収先が許認可を得ていない無免許営業だったなどということもあります。
その意味でM&Aの買い手にとって、デューデリジェンスは欠かせない工程です。
しかし、デューデリジェンスに時間をかけすぎると、M&Aの情報が漏れ、社内外から反対の声が上がることもあるので、中小企業であれば1か月以内を目安に集中的に行うことが必要です。
このように、デューデリジェンスはどこまでやるかという点と、どれだけの時間をかけるかというバランスをとるのが難しいところです。
(3)法務デューデリジェンスとは
法務デューデリジェンスでは、法的リスクの有無を調査します。
法務デューデリジェンスで調査するのは主に次の事項です。
①M&Aのスキーム自体に法律上の問題はないか
②買収対象の会社の価値に影響を与える法律上の問題はないか
③買収後の事業に影響を与える法律上の問題はないか
④買収後に改善すべき法律上の問題はないか
このようなリスクの有無を調査する際には、あらゆる自体を想定して、法律上の幅広い知識を駆使する必要があり、極めて専門性の高い分野です。
たとえば、①M&Aのスキーム自体に法律上の問題はないかという点での例を考えると、会社分割で収益性の低い事業を切り離したとき、状況によっては不当な債務逃れとして、詐害行為取消権や否認権という法律上の権利行使で会社分割の効果が取り消されてしまうこともあります。
法的なリスクを安易に考えず、弁護士に依頼する方が長い目で見れば専門家である弁護士に依頼する方がいいでしょう。
4.契約交渉

M&Aでは、ポイントとなるタイミングごとに秘密保持契約、基本契約、本契約といった契約が締結されます。
M&A特有のこれらの契約交渉にはどのような特徴があるのでしょうか。
(1)M&Aの契約書はオーダーメイド
M&Aでは、それぞれのケースに合った契約事項を考えなければなりません。
事業譲渡なのか、株式譲渡なのかといった大枠の事項、個々の財産をどの範囲でどのような方法でいつ承継させるかといった細かな事項など多岐にわたります。
また、何が適切な契約事項なのかは業態や規模、当事会社の意向によって変わってくるでしょう。
このように、M&Aでは事案に合った適切な契約事項を盛り込んだ契約書を作らなければなりません。
(2)弁護士ならではのスキーム-
会社再建などにM&Aを利用する場合、より効果的に行うために債務整理を併用することがあります。
たとえば、収益性は良いが、銀行からの借入れが多く資金繰りに苦しんでいる会社があったとします。
返済が滞れば担保に入れている不動産等の財産を差し押さえられ、事業を継続するのは難しいでしょう。
そこで、会社自体と銀行からの債務をセットで買い取ってもらう方法、会社分割や事業譲渡により残す事業のみを他社に移して残った部分を破産させて清算するということも考えられます。
これらの場合、通常のM&Aの交渉に加えて、金融機関との交渉や裁判所に破産申立を行うというステップが加わります。
これらは弁護士しかできないスキームです。
このように、M&Aと債務整理を併用するというスキームもあり、弁護士しかトータルサポートできないケースもあります。
まとめ
冒頭にも書きましたが、M&Aと聞くと中小企業や個人事業主の方には縁がないと考えている方が多くいらっしゃいますが、中小企業こそM&Aを活用すべきです。
日本の中小企業には、個々の会社で見れば優れた技術やアイディアを持っているのに、それをうまく活用できていない会社がたくさんあります。
また、高齢化によって跡継ぎ問題に悩む会社は今後も増えていくでしょう。
このような会社が、うまく他社と連携を取り合って自社の技術やアイディアをアピールしていけたら、優良な企業を廃業させずに残すことができたら、日本の中小企業はより元気になることができるのではないでしょうか。
是非、弁護士法人みずきにお任せください。
関連記事